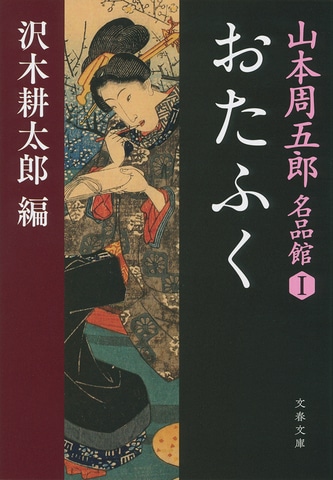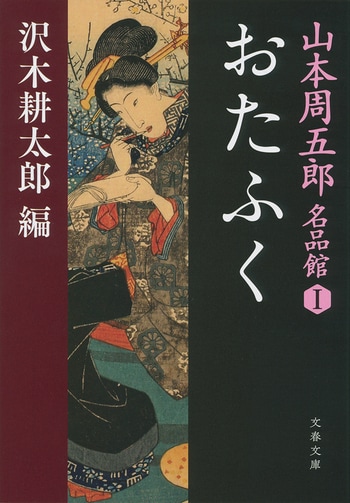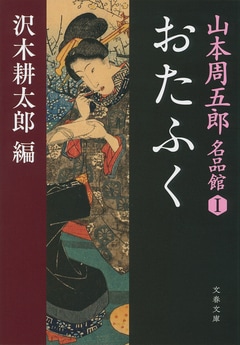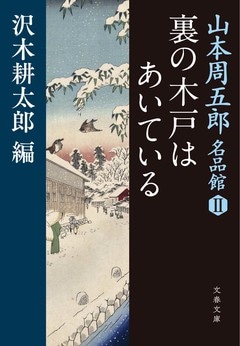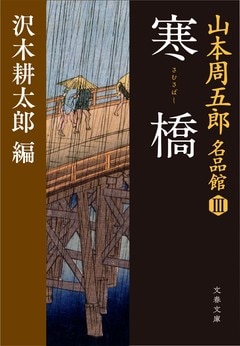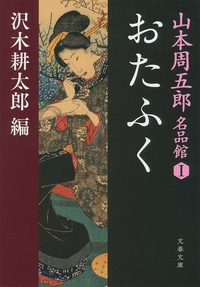
やすは、禄高千石もの大身の武家の妻として、夫に仕え、子を育て、大過なく家を守り、死んでいく。貞淑で、質実な、まさに「婦道」の鑑のような女性である。
だが、同時に、そのような妻の立場をまなじりを決するかのようにしてつとめているのではない、おっとりとした柔らかさを持っていた。だから、夫の佐野藤右衛門にも、自分の妻が千石の家を守るために陰でどのように心を砕き、心を配っていたかが死ぬまでわからなかったのだ。
そのやすの象徴的な行為として、嫁や使用人に高価な着物の贈り物をしながら、自分は粗末な木綿の服を洗い、繕い、着つづけていたということが述べられている。その結果、佐野藤右衛門は嫁や使用人にやすの形見分けをしようとして、箪笥にあまりにも貧しいものしか残っていないことに衝撃を受けることになるのだ。
そうしたやすに、山本周五郎は女性のあるべき姿を見ていたことは間違いないが、私がやすを山本周五郎の作品世界の一丁目一番地のひととするには他にも理由がある。
第一は、それが山本周五郎の母をモデルにしている女性であるらしいということである。
のちに、山本周五郎が「語る事なし」というエッセイで書いている。
故郷の山梨で母が死に、東京からかけつけた山本周五郎は、その通夜の席で近所のおかみさんたちが話しているのを耳にする。それは母から受けた小さな恩義についてのあれこれだった。しかし、父はその人たちのことも、母がそのようなことをしていたということも知らなかった。
《ずっとのちに、私はこのことを「婦道記」の一篇にヴァリエーションした。「松の花」というのがそれであるが、その中で、日本の女性のもっとも美しくたっといことは、その良人さえも気づかないところにあらわれている。ということを書いた。もちろん母のことを言ったわけではなく、日本の女性一般に対する献辞であったが──》
第二は、やすの造形には母だけではなく早くに死んだ先妻も大きくかかわっていたと自ら語っている点だ。
戦後、急速に親しくなり、晩年の山本周五郎に寄り添うようなかたちで共通の時間を過ごしてきた編集者に木村久邇典がいる。その木村が、あるときこんなことを聞いたという。
《『日本婦道記』のなかの『松の花』を書かせたのは、おふくろであるとぼくは書いた。だが大部分のモデルになったのは、前のひとだった、と山本さんはいった》(『人間山本周五郎』)
前のひととは、山本周五郎が再婚した夫人と区別するために用いた、先妻を指す言葉だったという。
第三に、その再婚した妻にもこんなことがあったと山本周五郎が驚きをこめてエッセイにしたためている。
晩年近く、金はあるていど入るようになったが、家計などにまったく顧慮することなく、酒のために右から左に使ってしまう。妻から特に文句も出ないので、それでなんとかやれるのだろうと思っていた。