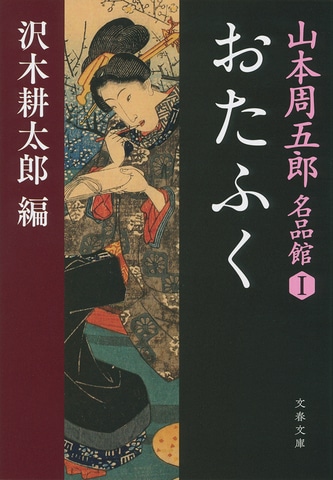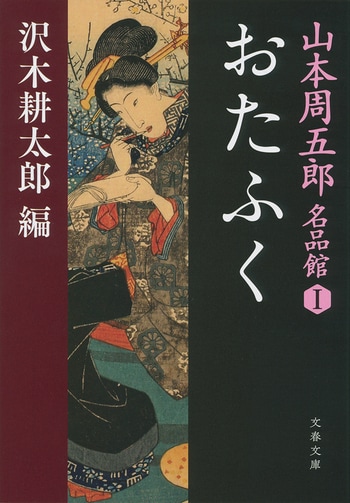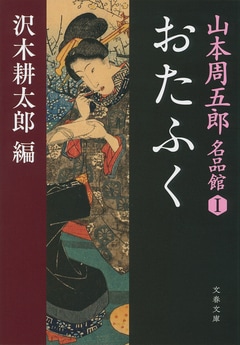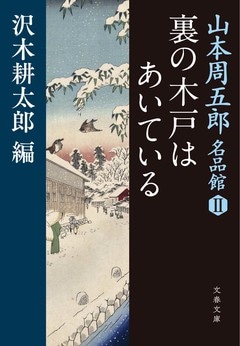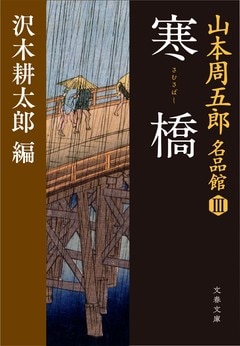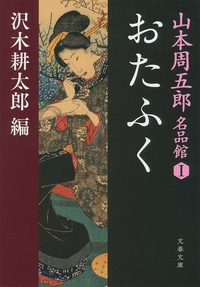
しかし、あるとき、と山本周五郎が書いている。
《私は家人の箪笥をあけてみて、自分の躯が唐竹割りにされたようなショックを受けた。彼女の母親から譲られたその古風な箪笥は、五つある抽出の全部がからっぽになっていたのである。(中略)ほんの常着用の物を幾らか残すだけで、きれいさっぱりなくなっていたのである》(「からっぽの箪笥」)
山本周五郎は、まさに「松の花」の佐野藤右衛門と同じような思いを味わっていたのだ。
これは、単なる偶然の一致かもしれないが、再婚した妻が山本周五郎の作品を読んで、夫の最も好む女性はこのようなひとだと察知し、そちらの方向に身を寄せていった結果だと考えられなくもない。虚構が現実を模しただけでなく、虚構が現実に模倣させる力を持ったかもしれないのだ。
そうしたいくつかの点から見ても、「松の花」のやすを山本周五郎作品の一丁目一番地に位置するひととすることにさほど大きな無理はないだろうと思われる。
もしこの「松の花」のやすを一丁目一番地のひととすれば、そこからの距離で、他の作品の女性の位置を計測することができるようになる。
たとえば、この『おたふく』の巻には、「松の花」のやす以外にも、「あだこ」のおいそ、「晩秋」の津留、「おたふく」のおしず、「菊千代抄」の菊千代、「その木戸を通って」のふさ、「ちゃん」のお直、「おさん」のおさん、「雨あがる」のおたよという八人の魅力的な女性たちが登場してくる。
この八人の中で、やすから最も遠くにいるのは誰か。たぶんそれは「おさん」のおさんだ。可愛い女だが、性の極限の瞬間に自らの官能を制御できないため、下降に下降を繰り返していかなくてはならない運命に見舞われる。「おたふく」のおしずは本質的にはおさんに近い女性だろう。しかし、やすに似た制御心の持ち合わせもあるところから、やすとおさんの間に位置することになる。「あだこ」のおいそはさらに「松の花」のやすに近いところにいる女性だろうと思われる。「雨あがる」のおたよは、もし夫が浪々の身にならなければやすと同じような人生を生きただろうし、「晩秋」の津留は父が生きていて、普通に結婚していたらやすと同じか、やすそのものの人生を生きたことだろう。そして、長屋のおかみさんである「ちゃん」のお直は、貧しさの中で、それでも夫が生きたいように生きることを願っているというところからすると、武家の妻ではないがやはりやすの近くに位置する女性だと思える。
では、「菊千代抄」の菊千代はどうか。女という自分の性を完璧に抑圧して生きなくてはならなかったという意味において、菊千代は、おさんとは正反対の方角の端に位置する女性と言えるかもしれない。