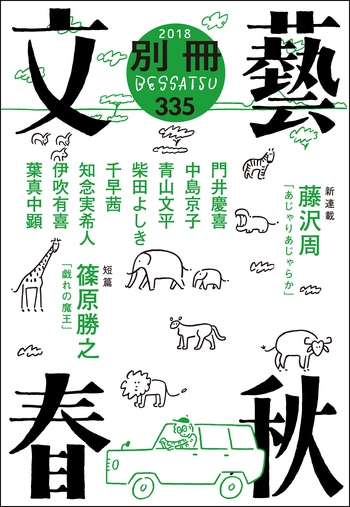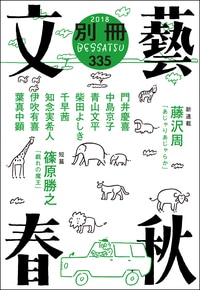
前回までのあらすじ
エイリアンハンドシンドロームという、片腕が何者かに乗っ取られたかのように動く奇妙な疾患に冒された高校生の岳士。しかし、腕から聞こえてくるのは亡くなった兄・海斗の声で、岳士はそれを嬉しく思う。家を飛び出した岳士は、ひとまず多摩川の河川敷に落ち着くも、そこで男性の刺殺体を発見し、殺人犯と目されることに。追われる立場となりながら、それでも事件の裏に危険ドラッグとそれを売りさばく集団「スネーク」の存在があることを突き止めるが、今度は売人カズマを張っていた刑事・番田に捕捉され、スパイになるよう持ちかけられる。事件解明のためその話に乗った岳士は首尾よくスネークの幹部に信頼されるが、ある日、自らが売ったドラッグを服用した女子高生がビルから飛び降りるのを目撃し、動揺する。そんな折に隣室に住む彩夏に誘われ、抗えずついに一線を越えてしまう。
第九章
1
「おい、聞こえているんだろ。なんとか言えって」
西に傾きはじめた太陽に照らされた住宅街を歩きながら、岳士は左手を見下ろす。
「悪かったって言っているだろ。そろそろ機嫌直してくれよ」
岳士はため息交じりに謝罪する。今朝からずっと、こうして話しかけているのだが一言も返事はなかった。
あまりにも反応がないので、サファイヤを飲んだときのように深く眠っているのかとも疑った。しかしいま、左手首から先の感覚はない。海斗が眠りについているなら、左手の「権利」も失うはずだ。やはり、へそを曲げて無視しているだけなのだろう。
当然といえば当然か。岳士は後頭部を掻く。
昨日、品川のカフェでサファイヤを飲んでから川崎のウィークリーマンションへ帰った岳士は、抑えきれない欲望を胸に彩夏の部屋の呼び鈴を鳴らしたが彩夏は留守だった。しかたがなく岳士は自室へと戻った。
凶暴な性欲を発散できなかったことは残念だったが、ベッドに横になり目を閉じれば、このうえない幸福感に包みこまれた。瞼の裏には万華鏡のごとく色とりどりの煌めきが輝いていた。
二、三時間、宝石がちりばめられているような世界に揺蕩っていた岳士の意識は、ドアの閉まる音で覚醒した。壁に耳をつけると、サファイヤにより鋭敏になっている聴覚が、かすかな足音をとらえた。