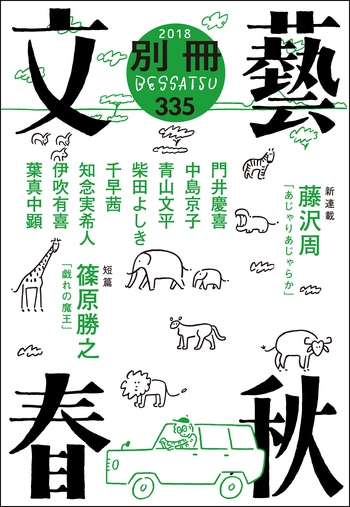「なあ、そんなに怒るなって」
『うるさい。話したくない』
「こんな追い詰められた状況で、頭がどうにかなっちゃいそうだったんだよ。だから、我慢できなくて……」
『追い詰められた状況だからこそ、冷静にならないといけないんだろ。けれどお前はクスリに逃げたんだよ。卑怯者』
「卑怯者って、そんな言い方ないだろ」
『本当のことだろ。こんな大変なときに、のんきにまたあのお姉さんと一晩中いちゃつくなんて、なに考えているんだよ』
「なんでそのことを!?」
昨日、品川のカフェでサファイヤを飲んでから今朝起きるまでの間に、左手の感覚は戻っていた。彩夏とのことは、海斗には分からないはずなのに。
『やっぱり、あのお姉さんと過ごしていたのか』
海斗が呆れ声で言う。かまをかけられたことに気づき、頬が引きつった。
『あのお姉さんには近づくなって、何度も言っているだろ』
「彩夏さんのなにが問題だって言うんだよ」
『一昨日の駐輪場でのことを忘れたのか? 完全に目がいっちゃっていただろ。まともじゃないよ』
手首を振る海斗を見ながら、岳士はぼそりと「仕方がないだろ」とつぶやいた。
『仕方がない?』
「あの人は、兄弟を亡くしたんだぞ。子供のときからずっと一緒に過ごしてきた兄弟を。それがどんな気持ちか分かるか?」
海斗は答えなかった。
「彩夏さんは『世界が壊れた』って言っていただろ。まさにそんな感じなんだよ。それまで生きてきた日常が、鏡が割れたみたいに音を立てて木っ端みじんになるんだ。まともでなんかいられるわけないだろ。あの人は俺と同じなんだよ」
『……お前は、おかしくなってなんかいないよ』
「おかしくなっていない? 俺は、死んだ兄貴に左手を乗っ取られたなんて言ってるんだぞ。どう考えてもまともじゃないだろ。実際、そのせいで俺は精神病院に強制入院させられそうになった。彩夏さんより俺の方がはるかにやばいんだ」
岳士は激情に突き動かされるままに、まくしたてる。
「俺と彩夏さんは似た者同士なんだよ。俺にはあの人の気持ちが分かるし、あの人も俺の気持ちを分かってくれる」
『だとしても、あのお姉さんには近づかない方がいい。あの人のせいで、お前はクスリに手を出したんだから』
海斗の声には苦悩が満ちていた。岳士はかぶりを振る。