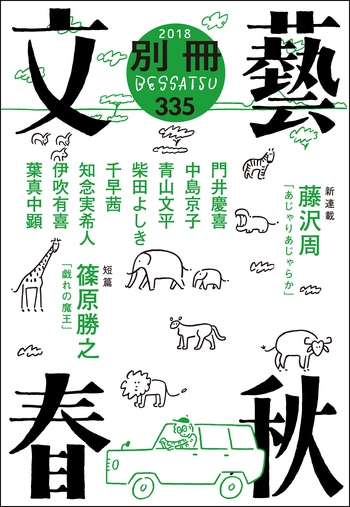ベッドから飛び起き、靴を履くこともせずに外廊下に出た岳士は、彩夏の部屋の玄関扉をノックした。インターホンを押すことすらもどかしかった。
開いた扉から彩夏の顔が覗いた瞬間、理性を保てなくなった。押し入るように部屋に入ると、目を見張っている彩夏を壁に押し付け、ドラッグで昂ぶっている気持ちのままに彼女の唇を奪った。
最初彩夏の唇は固く閉ざされていたが、執拗に舌で舐るうちにやがて力が抜けていき、やがて積極的にキスに応えはじめた。数十秒、お互いの舌を絡め合ったあと体を離すと、「驚いたじゃない」と艶やかに微笑み、岳士の手を取って部屋の奥へと連れて行った。
ベッドに押し倒そうとする岳士を「待って」と押しとどめると、彩夏はベッドサイドに置かれた鏡台の抽斗を開け、中からサファイヤを二つ取り出した。岳士がすでに飲んでいることを告げると、彩夏はわずかに不満そうな表情をして一本を抽斗にしまい、残りの一本を呷った。
そうして二人は、一昨日と同じように激しく、体力が続く限り交わった。疲れ果てて狭いベッドで重なりあうように数時間睡眠をとったあと、再びサファイヤを飲んで行為に及びさえしていた。
夜通し、断続的に求めあい、朝日がカーテンの隙間から差し込みはじめたころ、寝息を立てる彩夏を部屋に残し、ようやく岳士は自分の部屋に戻ったのだった。
肌に彩夏の感触を残したままベッドに倒れこみ、気絶するように眠りに落ちた。そして今朝、『いつまで寝てるつもりなんだよ! 今日は正午に取引があるんだろ!』という海斗の怒鳴り声で起こされたのだった。
壁時計の針がすでに十時を回っているのを見て飛び起きた岳士は、慌ててシャワーを浴びた。新しい服に着替えて部屋を出ようとしたとき、ヒロキから「相手の都合で取引が午後五時になった」と連絡があった。そのため、数時間部屋で時間を潰したあと、待ち合わせ場所である多摩川の河川敷へと向かっているのだった。
電車を乗り継いで駅に着き、こうして河川敷を目指して歩いているが、今朝怒鳴って以来、海斗は一言も言葉を発していなかった。
サファイヤを使った影響か、それとも単に睡眠不足のせいか、やけに重い頭を押さえながら、岳士はおずおずと訊ねる。
「海斗、まさかお前、サファイヤの影響で喋れなくなったとか、そういうことはないよな?」
『……そんなことないよ』
どこまでも不機嫌な声が返ってくる。