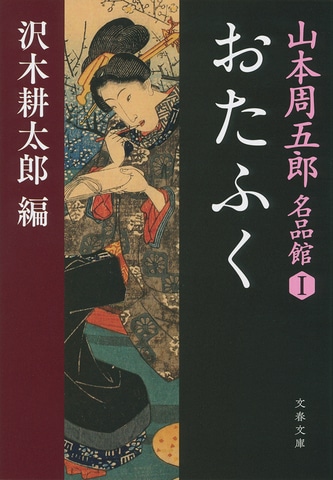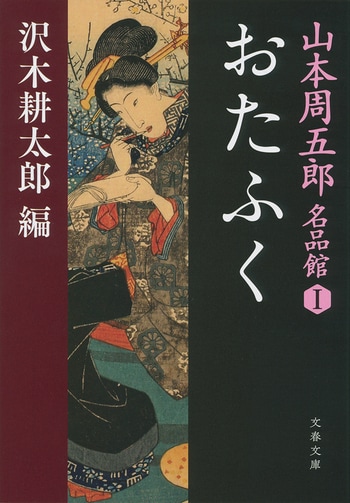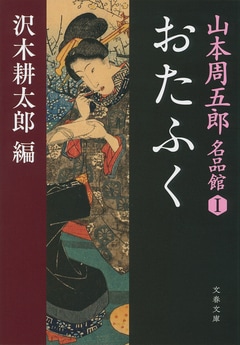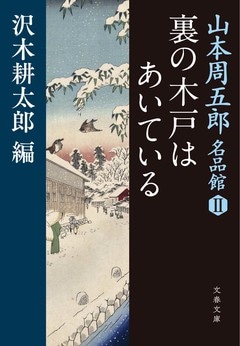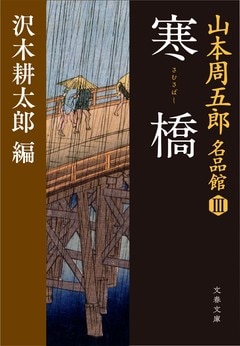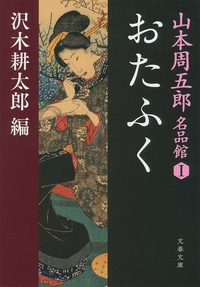
「松の花」
これは先に述べたように戦前に刊行された『日本婦道記』の一編であり、まさに婦道記というタイトルにふさわしい「女の生き方」が描かれていると言える。
しかし、一見、戦前の婦道記物という範疇にすっぽり入りそうに見えながら、夫が妻の本当の姿を知らなかったと驚愕するという展開には、現代の夫婦に置き換えても充分に通用する問題を包摂している。
夫の佐野藤右衛門は、妻のやすを、死の直前まで、いや、死んでからも、ごく普通の「貞女」だったと理解している。ところが、その通夜のときから、彼のまったく知らなかった一面が明らかになっていく。
それは「貞女」の枠を逸脱するものではないが、藤右衛門は、妻のやすが、家を守るために、自分のわからないところで、ある種の苛烈な戦いをしていたということを知っていくことになる。
これは、禄高千石の家を賢く切り盛りしていた「貞女の物語」ではなく、夫が妻を新たに発見していくという物語でもあるのだ。
「おさん」
ここには短編にもかかわらず、かなり実験的な手法が用いられている。
主人公の参太の一人称によって妻であったおさんについての「記憶」が語られる部分と、三人称で参太の上方から江戸への帰還の「道中」が述べられる部分が、交互に配置されている。それだけではなく、真の主人公といってよいおさんはついに登場しないまま終わるのだ。
おさんは参太に心から惚れている。しかし、性の陶酔が始まり、深く感じ切ると、そこにいなくなってしまう。
《男がもっとも男らしく、女がもっとも女らしくむすびあう瞬間に、むすびあう一点だけが眼をさました生き物のように躍動しはじめ、その他のものはすべて押しのけられるのだ。それは陶酔ではなく、むしろそのたびになにかを失なってゆくような感じだった》
そして、やがて、陶酔が頂点に達すると、誰とも知れない男の名前を口走るようになる。その名前に特別な意味がないとわかっていても、どうしても耐えられなくなった参太は上方に「逃げて」しまう。
そして三年、風の噂でおさんは男から男と渡り歩いているらしいと知りつつ、心を決めた参太は江戸に帰ろうとするのだ。
この作品には、おさんとは別に、参太が江戸へ帰る旅の途中で出会う、宿の飯盛り女が出てくる。この飯盛り女のおふさも魅力的だ。とりわけ、参太との、掛け合いのようなやりとりには、時代小説家としての山本周五郎の圧倒的な力量を示す見事な呼吸がある。
江戸まででいいから連れていってくれというおふさの頼みを仕方なく受け入れてしまった道中で、二人はこんなやりとりをする。