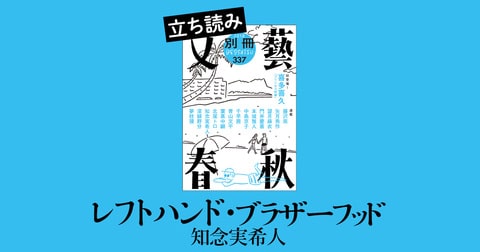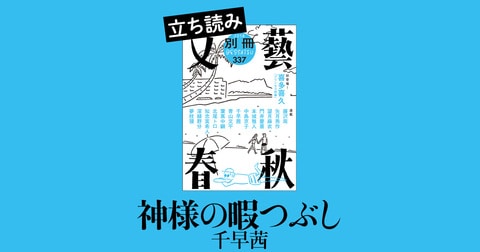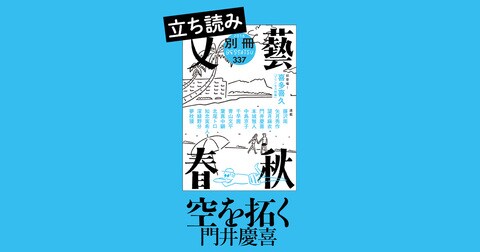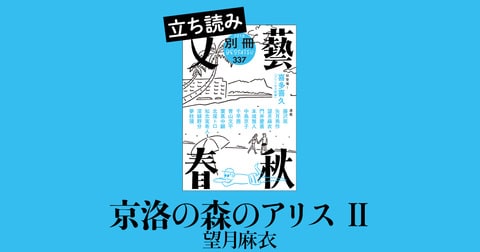ひと気のない歩道を並んで歩きながら、直斗はぽつりと言った。眩しい日差しで白く染め上げられた建物や街路樹を見ていると、とてもこの場所で殺人事件があったとは思えなくなってくる。
「昼間はな。街灯が少ないから、夜はかなり暗いんじゃないか」と鹿部が前を見たまま答える。「実際、三件の事件はすべて夜に起きているからな」
「……正直、まさかという感じです。自分がこんな重大事件に関わることになるとは思っていませんでした」
「芦原は刑事になって何年だ?」
「まだ二年目です」
「そうか。俺は十六年目だが、被害者が三人以上出た事件の捜査に加わるのはこれが二回目だ。巡り合わせとしか言いようがないな。どうだ? やりがいを感じるか?」
「それはもちろん、一刻も早く犯人を逮捕しなければと思っています」
鹿部が眉間にしわを寄せて首を振る。
「そんなのは当然だ。それにプラスして、血潮が沸き立つような感覚があるか、って訊いてるんだ。要は、犯人との戦いに興奮しているかどうか、ってことだ」
「そういう気持ちは、ありません」と直斗は正直に答えた。「そのような感情を抱くことは不謹慎ではないですか?」
「他人に言いふらせば、もちろん批判の対象になる。しかし、心の中でどう感じていようがそれは自由だろう」
「……鹿部さんは興奮しているんですか?」
鹿部は正面に視線を戻し、小さく頷いた。
「手柄を立ててやろうって思いはあるよ」
「刑事としてやっていくなら、そういう気持ちがあった方がいいと?」
「そうだな。熱さは必要だろう。『俺がやるんだ』っていう思いを常に胸の中に持っておくべきだ。じゃなければ、仕事のキツさに音を上げかねない」
「それは大丈夫です。自ら望んで就いた仕事ですから」
「それならいいんだが」と鹿部が神妙に言う。「悪いな、変な話をして。芦原を見ていると、がむしゃらさが足りない気がしたんでな」
「……あ、いえ、とても参考になりました」
直斗は鹿部の観察眼に動揺していた。ストレートに指摘されたわけではないが、彼は直斗の迷いを察知しているのかもしれない。自分が犯罪捜査に尻込みしてしまう理由を看破しているのではないか、とさえ思えた。
――この人に相談してみるべきだろうか。
その考えが心を掠めた時、「おっ、あそこに四人組がいるな」と鹿部が足を止めた。彼の指差す先に、テニスラケットを持った男女の集団がいた。
「え、あ、ああ……そうですね」
問題を先送りにするだけだと分かっていたが、悩みを打ち明けるタイミングを逸したことに直斗は安堵してしまった。
自分の不甲斐なさから目を逸らすように、「まだ話を聞いたことのない学生ですね。声を掛けてみましょう」と言って、直斗は彼らの方へと駆け出した。