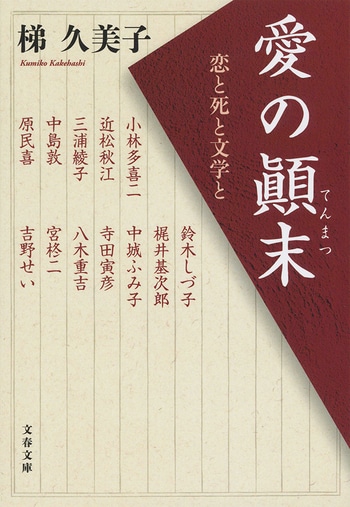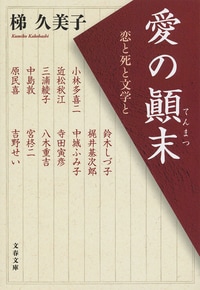
詳細はここでは述べないが、『狂うひと』を読みながら、さまざまのことを考えざるを得なかった。たとえば愛人との情事の日記を、ミホにたまたま見つけられたのではなく、島尾敏雄がわざとミホが見つけやすいように置いていたことが明かされる。つまり夫は妻の狂乱を演出したと言ってもいいだろう。この事実を読者はどのように小説『死の棘』のなかに組み込んでいけばいいのか。
一種の暴露本でもあるこの一書が決して品が悪くならないのは、それが小説を書くということの本質に届いているがためである。小説を読んでいるだけでは決して得られない情報が、小説の書かれた現場に密着することから得られる。しかも時にそれは、その作品の〈読み〉の根源に関わる思いもかけない発見であったりする。これは小説にとって幸なのか不幸なのか。小説の価値を高めるものなのか貶めることになるのか、いったいそうまでして書くという作業に作家を突き動かす力は何なのか、などなど、梯さんの『狂うひと』は、書くという行為はいったい何なのかという根源的な問いを読者に、そして現にモノを書いている作家にも突きつけることになったのだろう。