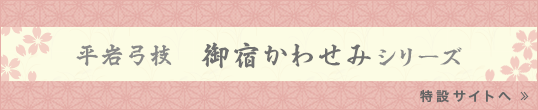〈留学・洋行〉
麻太郎は、二度にわたって留学した。大切なのは、彼が二度とも「かわせみ」に戻ってきたことである。最初の洋行から帰国した時、麻太郎の養父である通之進は、「まるで、東吾が戻って来たような……」と絶句した(「築地居留地の事件」)。帰国した麻太郎は、皆から「若先生」と呼ばれるが、これはかつて東吾のことだった。
そして、二度目の帰国は、「新・かわせみ」の人々を苦しめるトラウマ(畝源三郎殺害犯人との対決)が極大値に達したクライマックスの時点だった。
洋行していたはずの麻太郎が颯爽と姿を現す。その時、気持ちが動顛したお吉は、普段は「御新造様」と呼んでいるるいを、彼女の若い頃の呼び名である「お嬢さん」と呼びかける。お吉の心の中で、時間軸が一瞬、ひずんだ。麻太郎は、「お嬢さん=るい」と人生を共に歩んできた東吾が、時空の裂け目から新しい時代へと降臨してきた青年なのだ(『お伊勢まいり』)。
子の麻太郎は二度留学し、二度とも帰国した。父の東吾は、不在のまま、帰国できない。けれども、父の命は、子にしっかりと伝わっている。
《さわやかな眼差しを自分へ注いでいる麻太郎は若き日の夫に生き写しであった。自分が一生を賭けて愛した人の命はまぎれもなく、隣に立っている麻太郎に受け継がれている。》
「蘭陵王の恋」
るいの思いは、読者の思いでもある。
〈そして、三百話〉
三百話という、未踏の長編シリーズへと成長した「御宿かわせみ」は、近世と近代をまたぐ、新しいタイプの時代小説であり、家族小説であり、文明小説だった。明治維新の前後で、世の中は一変した。福沢諭吉は「一身にして二生(にしよう)を経(ふ)る」ようなものだと述懐している。人生は本来、一回きりであるはずだが、封建社会と近代社会の二つを経験できたのは、人生を二度生きたようなものだ、というのだ。
私は「かわせみ」を読むと、逆に、「三身にして一生を経る」という気持ちになる。江戸の爛熟した文化を生きる人間も、幕末の動乱期を生きる人間も、文明開化の新しい世の中を生きる人間も、つまるところは同じ人間である。江戸が東京と名前が変わっても、旧暦が新暦に切り替わっても、人々の喜びや悲しみはほとんど変わらない。多くの家庭が抱える不幸の火種と、旅籠「かわせみ」に集う人々が作り上げる理想の人間関係との対比も、変わらない。
読者は、「新・かわせみ」のさらに三世代くらい後の現代を生きている。その現代人が、「かわせみ」シリーズに一貫して求め続けたのは何だったのか。
「股旅物」を確立した長谷川伸の門下である平岩弓枝は、庶民の幸福と不幸を観察し続ける。平岩が定点観測の原点とした、大川端の旅籠「かわせみ」。そこは、悲しみが喜びへ、孤独が人間関係へと変貌する、不思議な坩堝(るつぼ)だったのではないか。
ふとしたはずみに心に生じた嫉妬や羨望が、大きなボタンの掛け違いとなって、悲惨な事件が起きる。けれども、被害者も加害者も、「かわせみ」という旅籠の温かさに包まれて、真っ白な心を取り戻す。客は来(きた)り、客は去る。そのつど、彼らの心は再生している。この癒しのシステムは、大川の流れが途絶えないように、現代まで続いている。
そして、ここにこそ、「かわせみ」が読者に愛され、ここまで長寿シリーズとなった秘密がある。悲しみや重荷を溶かして、生まれ変わりたいと願う強さは、現代人とて同じ、いや、現代人の方が強いだろう。
「かわせみ」シリーズの三百話は、現代人の心の再生装置である。心の重荷を少しでも下ろして楽になろうと、「かわせみ」を読み始める読者もいるだろう。だが、シリーズを読み進めるうちに、「重荷」に耐えて前向きに生きること、それが最も美しい生き方であることを、るいから教えられる。るいの心を共有できた読者は、自分の魂もカワセミとなって、大川の上を舞っているような喜びを感じる。眼下には、親しい人たちが見える。愛する人の心の重荷を軽くしてあげようという願いが湧いてくるのは、この時である。