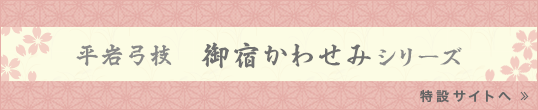優れた時代小説は、読者の願いや憧れを受け入れることで、シリーズ化する。
継続中の大シリーズに、平岩弓枝の「御宿かわせみ」がある。そして、平成二十八年(二〇一六)には三百話という大きな節目を越えた。昭和四十八年(一九七三)の開始から四十四年目、掲載誌を「オール讀物」に移してからだと三十五年目の到達である。
この三百話を、描かれている時代に着目すれば、大きく三つに分けられる。第一期は、鎖国期に爛熟した江戸の庶民文化を背景とした「るいと東吾の物語」の前半。第二期が、開国から幕府の瓦解(御一新)へと向かう激動の時代で、「るいと東吾の物語」の後半に当たる。そして第三期が、東吾の不在の中、明治時代の東京で、文明の坂を駆け上ってゆく「るいと東吾の子どもたちの物語」、すなわち「新・御宿かわせみ」である。
「大川」と親しまれ、江戸の人々の四季折々の暮らしを支えた隅田川が、まもなく海へと注ぎ入ろうとする豊海橋(とよみばし)のたもとに、一軒の旅籠があった。それが「御宿かわせみ」であり、るいという女主人が切り盛りしていた。
平岩弓枝は、江戸時代後期から明治時代までの大きな時代のうねりが、人々の心にどのような波紋を描いたのかを、「かわせみ」という旅籠から定点観測し続けた。その精緻な記録が、「御宿かわせみ」シリーズの三百話である。大川のほとりで、るいの目は多くの人々の喜怒哀楽と生老病死を見つめ続けた。
これほどまでに「かわせみ」シリーズが読者から愛され、書き継がれた理由は、どこにあるのだろうか。三つそれぞれの時期のキーワードに着目しつつ、このシリーズ全体の魅力と生命力に触れてみたい。
〈幼なじみ〉
シリーズが始まった頃のるいは、運命に翻弄される二十二歳の娘だった。彼女は「父を失った娘」であり、「武家から町人へと転じた女」であり、「経済的な自活を目指す女性」だった。るいを支えた一つ年下の恋人が、神林東吾。東吾もまた、未来の展望が開けない「部屋住みの次男坊」であり、鬱勃とした青春の悩みを抱えていた。
けれども、幸福になる遺伝子を天から与えられていた二人は、過酷な状況にも負けなかった。犯罪に手を染める周囲の人々を見つめ、その弱さを反面教師としながら、幸福な人生を作り出してゆく。旅籠「かわせみ」は、不幸と不如意(ふにょい)に満ちた世界の中で、唯一の幸福の砦だった。だからこそ、この場所を平岩弓枝は観測の拠点としたのだ。
二人の愛が芽生えたのは、彼らが「幼なじみ」だったからである。実は、このシリーズには「幼なじみ」という設定が多い。『江戸の子守唄』には、タイトルそのものが「幼なじみ」という短編がある。ここでは、「東吾とるい」、「清太郎とおてい」という二組の幼なじみが対比されている。
おていは、幼なじみの清太郎に心惹(ひ)かれていた。清太郎も同じだったが、明瞭な言葉にして結婚の約束をしたわけではない。その清太郎が主人の娘から好意を寄せられる。そのことを知ったおていは、自分も奉公先の主人と深い仲になり、彼と共謀して清太郎を無実の罪に落とすことを計画した。自分の愛をふみにじった幼なじみへの、おていの復讐だった。だが、彼女をそこまで絶望させたことを知った清太郎は、無実の罪に服そうとまで思う。やがて真実が明らかになり、軽い罪で釈放されたおていを、清太郎は出迎え、二人は新しく人生をやり直す。
この一部始終を、るいは見届ける。るい自身、東吾を愛していたが、彼は「嫁に来い」とか「行く末、夫婦になろう」などと、口にしてくれたことはあまりなかった。
《「馬鹿をいうな、俺は子供の頃から、女房にもらうなら、るいしかないときめていたんだ。どうして、お前にはわからなかったのか」
他人でなくなってから、東吾がいい、るいは、その都度、
「女は口に出していって下さらなくてはわかりません」
と幸せを怨みがましく答えて来た。》
「幼なじみ」
読者は、愕然として気づく。幼なじみの清太郎への絶望ゆえに、犯罪行為に走ったおていは、「もう一人のるい」なのだということに。そして、おていを許し、共にこれから生きようとする清太郎が、「もう一人の東吾」であることに。るいになれなかった女たち、東吾のように生きようとする男たち。彼らは「御宿かわせみ」という場に立ち寄り、やがて去ってゆく。大川端の旅籠「かわせみ」は、時の流れに翻弄される人々の希望と挫折の堆積地である。