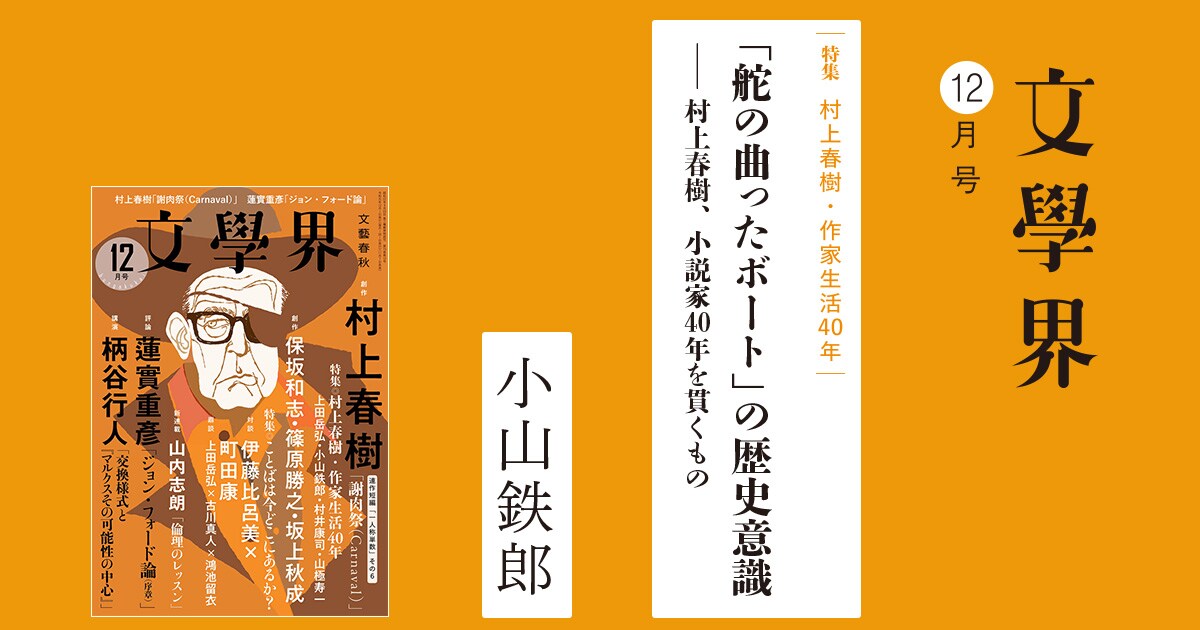そして、これに続いて「しかしそれでも私は舵の曲ったボートみたいに必ず同じ場所に戻ってきてしまうのだ。それは《私自身》だ。私自身はどこにも行かない。私自身はそこにいて、いつも私が戻ってくるのを待っているのだ」と書いています。
私が記者として、村上春樹にインタビューしたのは、同作の刊行時が初めてですが、この「舵の曲ったボートみたいに」という言葉が、とても印象に残りました。そうやって、必ず「《私自身》」に戻ってきてしまうのです。
続いて取材した『ノルウェイの森』(一九八七年)の冒頭部には十八年前に直子と歩いた草原の風景を思い出す場面があります。そこには「僕は僕自身のことを考え、そのときとなりを並んで歩いていた一人の美しい女のことを考え、僕と彼女とのことを考え、そしてまた僕自身のことを考えた。それは何を見ても何を感じても何を考えても、結局すべてはブーメランのように自分自身の手もとに戻ってくるという年代だったのだ」とあります。
その次の長篇『ダンス・ダンス・ダンス』でも取材しているのですが、この作品の「僕」は「一九六九年にはまだ世界は単純だった。機動隊員に石を投げるというだけのことで、ある場合には人は自己表明を果たすことができた」と思っています。でも、自分がいま生きる世界に対しては「隅から隅まで網が張られている。網の外にはまた別の網がある。何処にも行けない。石を投げれば、それはワープして自分のところに戻ってくる」と考えています。
この一九八八年刊行の『ダンス・ダンス・ダンス』で描かれる時代は「一九八三年」です。つまり、村上春樹が一九八〇年代とは何かということを考えた同時代小説で、「僕」が考えている「現在」は一九八〇年代のことです。