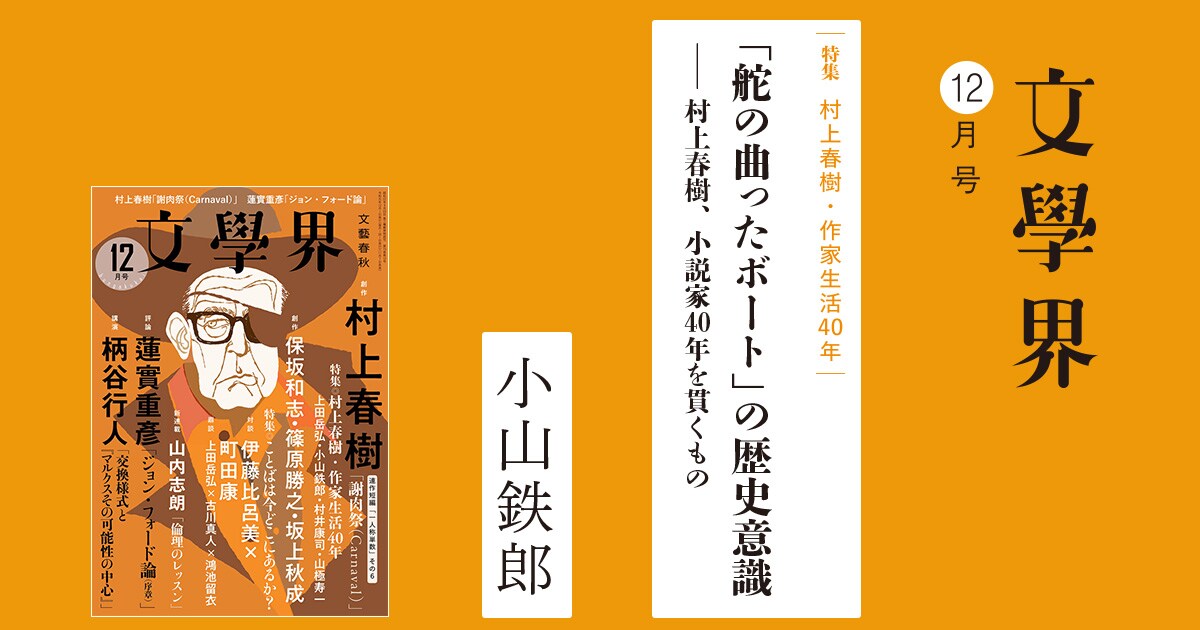同作の中に「牧村拓」という作家が出てきます。「牧村拓(MAKIMURAHIRAKU)」は「村上春樹(MURAKAMIHARUKI)」のアナグラムですので、この「牧村拓」は、村上春樹や「僕」の分身的な人物かと思いますが、彼は、大昔のこととして「樺美智子が死んだとき俺は国会の回りにいた」と語っています。つまり四十代半ばの「牧村拓」は六〇年安保の世代であり、三十四歳の「僕」は七〇年安保世代の人間です。
その「牧村拓」は「大昔には、何が正義で、何が正義じゃないかちゃんとわかっていた」「でも今はそうじゃない。何が正義かなんて誰にもわからん」と語っています。その状況に対して、「僕」は「石を投げれば、それはワープして自分のところに戻ってくる」という認識を持っているのです。この自覚の差が、たいへん印象的です。
☆
そして、これらの「舵の曲ったボートみたいに」「ブーメランのように」「ワープして」は同じ考えの延長線上に繋がる考えだと思います。つまり何かを相手に対して問うと、それと同じことを同時に自らに問うという形で、村上春樹の物語は進んでいくのです。
問題の相手、闘うべき敵は、常に向こう側にいて、こちら側の自分はその問題を問われることがないという考え方では、もう通用しない。そういう時代を生きているという認識を村上春樹は抱いて、書いてきたのだと思います。
村上春樹は、相手に問う問題を「舵の曲ったボートみたいに」「ブーメランのように」「ワープして」自分の問題として、同時に考えていく作家として登場してきました。そんな認識を明確に持って出発した作家が、村上春樹なのだと思います。村上春樹は二つの話が並行して進んでいく物語が好きですが、これも相手を問い、さらに自らを問うという、向こう側とこちら側の両端を同時に叩く意識の反映だろうと、私は考えています。