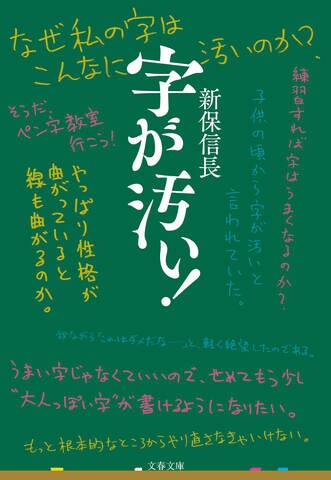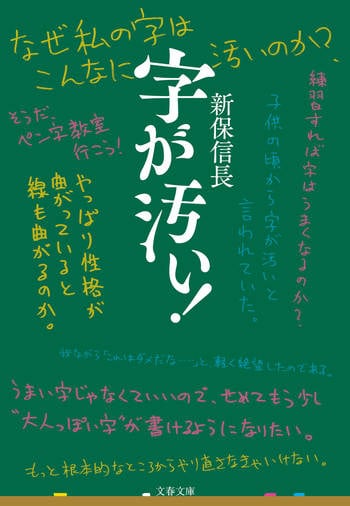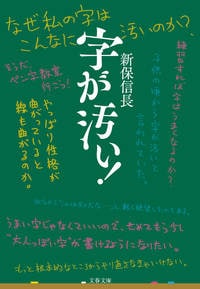
上手い字とはペン字練習帳に手本として載っている字のことなのだろうか。上手い字が魅力的とはかぎらないのではないだろうか。本書に出てくる読みにくくて下手な字の数々が持つインパクトの強さはなんだろうか。上手い下手の向こうに、いい字とそうではない字の世界が広がっているのではないだろうか。
「字が下手で情けないなあ、なんとかしたいなあ」と目先のことにこだわっているのに、字に対する思いが勝手に膨らんでくる。そこが本書の真骨頂だ。
この世に同じ顔がないように、字は書く人それぞれのものである。だから上達をあきらめろと言いたいのではない。
本書には字の先生が「自分の字には満足していません」(要旨)と語る場面が出てくる。そんなバカなと言いたくなるけど、きっと本音なのだ。あんなに上手くてもそうなるところに、人間の面白さが凝縮されている。
本書を書き上げても、新保さんの字が美麗になったという話は一向に僕の耳に入ってこない。おそらく相変わらず、世間の基準では下手に属するのではないか。根拠はないけど、僕には上手い字を書く新保さんが想像できないのだ。
でも、その字はかつて僕が見せられた、死んだような字ではなく、真剣にコンプレックスと向き合った者としての諦念と力強さが加わった字となっているだろう。そして、僕はそういう字のことを“いい感じの字”と呼ぶのだと思う。