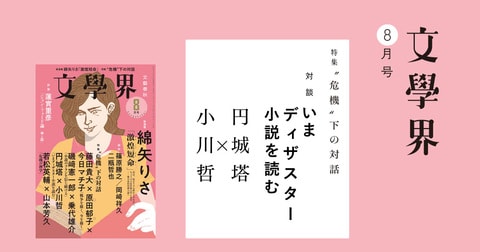松山 そうなると思います。放っておいても変化はあったと思いますが、コロナで一気にそれが加速したという印象ですね。
小川 具体的に、仏教の形がこれからどんな風に変化していくか、イメージはありますか。
松山 これからの社会で仏教が活躍する場所は、人生の終末期だと思っています。コロナの時代になって、志村けんさんや岡江久美子さんといった著名な方がお亡くなりになり、世間に衝撃を与えました。コロナに罹り入院すると、家族ですらお見舞いに行くことができません。亡くなるときも一緒に付き添えない。すぐに火葬され、ご遺体に対面することなく、突然ご遺骨で帰ってくる。いわば戦時中みたいなことが行われている。多くの人にとって“死ぬ”ということが、すごくリアリティのあることになったと思うんです。
むしろ、これまで死を遠ざけ過ぎてきたのではないかと。ある種、隠蔽してきた。でも、どんな生物であっても死亡率は一〇〇%。生まれたら死ぬわけで、死は当然の成り行きです。向き合う訓練をしてこなかったところに、突如やってきた死のリアリティ。これでは動揺が広がるのも当然です。
小川 お見舞いにも行けず、触れることすらできず、どこかプロセスが省かれた感覚のまま、最後の別れを迎えてしまう。
松山 そもそもお釈迦様は、「生老病死」という「四苦」について言葉を残されています。生きること、老いること、病に罹ること、死ぬこと、この四つが苦の根源であると。でも実はこれ、「苦」というのは苦しみのことじゃないんです。思い通りにならないという意味なんです。生きること、病に罹ること、老いること、死ぬことはコントロールできない。だからこそ、向き合い方を考えていきたい。
いままでは心臓が止まるまでがお医者さんの仕事で、私たちの仕事はその後だった。そこに断絶が生まれてしまっていたんです。人生というのは一つの流れなので、医療と宗教というのはもっと密接に関わったほうがいい。肉体だけでなく、心のケアについてちゃんと取り組んだほうがいい。私はそう思っています。

お寺でも「看取りの家」を
松山 実際、お寺で訪問看護ステーションなんていうものを始めたところもあります。
小川 訪問されて、その場でどういったことをされるんですか。
松山 基本は患者さんとの対話です。たとえばキリスト教には、チャプレンという方々がいます。チャプレンに胸のつかえを聞いてもらったり、死への準備をする時間があるんですね。でも、仏教ではなかなかそういう機会が持てなかった。でも、最近になって、和尚さんのお話が聞きたいと末期がんの方に呼ばれたりして、みなさんが「安心して旅立ちたい」という想いを強めておられるように感じます。
小川 なるほど。それは、時代の中で、みなの意識が変わってきたということなんでしょうか。少し話はそれますが、国家によっては安楽死合法化の議論が進んでいたり……。もちろん是非はあるでしょうが、どうやって死を迎えるのかということを考え、オープンに話し合うというのは悪くないことに思えます。
松山 そう思います。死ぬことを「縁起が悪い」と遠ざけるのではなく、日ごろから考える。死ぬということについて真剣に考えていると、真剣に生きられるようになるんですよ。私はもっと、中学生とか高校生のうちから、死について考える教育を受けられたらいいのにと思っています。
小川 確かにそうですよね。
松山 将来的にはお寺で、「看取りの家」のような活動ができたらなと考えていて。
小川 そういう例が、世界ではあるものなんですか?
松山 私はいま、ブータンでお寺の修復のお手伝いをしているんですが、ブータンの病院には、お坊さんの部屋があるんですよ。患者さんやそのご家族がいつでも相談に行けるように。
小川 カウンセラーみたいな役割ということですか。
松山 まさにそうですね。訪問医療にお坊さんが同行するケースもあって、それは、お坊さんが一緒にいるほうが、患者さんやご家族とのあいだの心理的な距離が縮まりやすいからなんだそうです。ブータンと日本では信仰の形態が違うので、そのまま同じ形でというわけにはいかないでしょうが、死や病気と向き合う場面においては特に、宗教者が関わることによるお役立ちというのがあるのではと感じています。