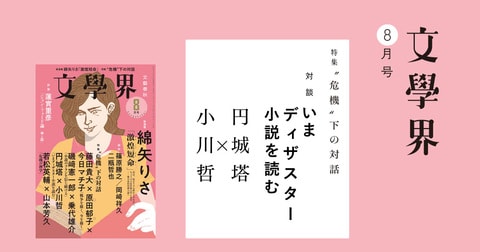小川 日本中を探したら、そんなふうにまだまだ使えるスペースをお持ちのお寺というのもあるんでしょうか。
松山 いっぱいあると思います。それこそ、三島由紀夫さんは妙心寺の修行道場に泊まり込んで『金閣寺』をお書きになったわけですし、お寺をひとつの仕事場として活用するというのは代々あった方式なんじゃないかと思います。いまの時代に合わせてWi-Fiを入れ、コーヒーメーカーのかわりにお抹茶をご用意したりしてね。
小川 それいいですねえ。
松山 お茶は目が覚めて、かつ気持ちが落ち着きますから。実は、お茶を中国から持ち込み日本に定着させたのは禅僧なんですよね。そういう昔ながらの智慧を使いながら、現代の皆さんにお役立てできることがあればいいなと思っています。
「リアル走馬灯」で記憶を繋ぐ
松山 伝統を生かして、その時代ごとに、臆せず何でも試していけたらいいですよね。テクノロジーが発達したいまに生きる宗教家として、出来ることは何でもしていきたい。
昔、禅僧が亡くなるときには遺偈というものをつくっていたんです。遺言ではなく、詩で遺すんです。そういう、生きた証の遺し方として、「リアル走馬灯」というものができないかなということも考えているんです。
小川 リアル走馬灯ですか。
松山 僧侶をしていると、お迎え現象について聞く機会が多いんです。ご両親や親しかった人が、亡くなる直前にお迎えに来てくれるというあれです。そのとき、昔体験したことがバーッと頭の中を駆け巡るという話があって。それを家族で共有できたらいいなと。布団から見上げる風景に、ともに生きてきた人々の姿を映し出し、傍らで見送るご家族にもその思い出を受け継いでもらう。人生って、長い時間をかけたそのすべてが人生じゃないですか。たとえば野球でも、九回裏2アウトまで勝っていたのに、逆転サヨナラ満塁ホームランで負ける。そういうこともあるわけで。
小川 ありますね。いい試合だったのに、最後の最後にっていう。
松山 でも、最後に打たれたからって、いい試合だったものがダメになるわけじゃない。
小川 本当にそう思います。小説でも、さんざんな人生を送ってきた人間の晩年、最期にちょっとした希望を書くとハッピーエンドということになってしまう。その逆もあって、主人公が最後に躓くと、ものすごくネガティブに受け取られてしまう。でも、そいつの人生はたぶん、概ね幸せだったんです。
松山 そういう全部をね、晩年だけじゃない、おじいちゃんやおばあちゃんの姿を見ることができたら、お孫さんとか、ご家族にとってもいいんじゃないかと思うんです。
先日、家族葬に参加させて頂いたんです。遺影はお孫さんが描いた似顔絵で、温かくてすごくいいお葬式でした。いまはもう、こうしなきゃいけないなんていうがんじがらめの世の中じゃないし、見栄を張る必要もない。逝く人と、見送る人。双方が想いを伝えきれたと感じられることが大切で、それがいちばん、残された皆さんにとっても重要だと思うんです。
小川 そうやって、変わっていけるってすごくいいですね。僕、前回の「別文ライブトーク」で、村山太一さんという、レストランのオーナーシェフの方にお話をうかがったんです。そこで村山さんが、飲食店はコロナの前から限界だったというようなことをおっしゃっていて。みんないろんな無理があることがわかっていた。だからこそ、変わろうと準備を始めていた人や、このタイミングで変わりたいと本気で思う人は、この機会にきっと変われるって。
今日、松山さんのお話を聞きながら、同じだなと思いました。お寺とか仏教って、ものすごく長い歴史を持ったものだけれど、折々に柔軟に変化してきているんですよね、きっと。変わるタイミングを逃さないことのほうが大切なのかも。
松山 そうありたいですね。
小川 あと、さっきおっしゃった「リアル走馬灯」ですけど、SF作家としては、空間そのものをみなで共有するのも素敵だなと思いました。ご本人の頭のなかにある記憶が走馬灯だとしたら、記憶しきれなかったものとか、逆にその時代、その場所のデジタルアーカイブから起こしたVR空間を見せてあげられたら、ご本人はもとより、ご家族もよりリアルに体験できる。テクノロジーを使って、体験の強度をあげていくことも目指してみたいですね。最期の日々の充実や、メモリーの残し方など、いまの時代ならではの在り方を考えていくのはとても面白そうです。

撮影:退蔵院、松本輝一