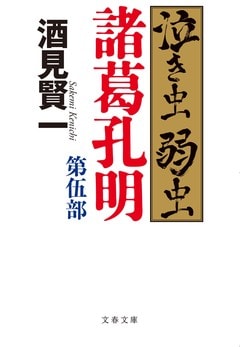そして例外的に門下に入れてもらった後、先生と直接話すことができるまでに十年はかかるといわれながら、案外と早くに先生と話すことになったのは、馬融が盧植のなかに大才を見たからであろう。
盧植は師に卒業を認めてもらった後は、自分の学塾をひらいた。第一次の党錮の禁(党人逮捕)はまぬがれたが、その後に霊帝から徴召された。宮中の図書館である「東観」に加わり、学者として過した。
その後、中央政府に失望し、郷里に帰って門をひらくが、このときあの劉備(十五歳)を教えてもいる。
黄巾の乱は各地でつづき、盧植は北中郎将(将軍)に任命されて、軍人として結構な働きを示した。隠棲して三年後、初平三年(一九二年)に死去したが、文人が学問の世界に安住していることができない時代の空気を、盧植の一生がよく伝えている。
皇甫嵩(こうほすう)は、盧植とは対照的に根っからの武官である。曾祖父の皇甫棱(りょう)は度遼(どりょう)将軍だったというように、武官の家柄の生まれだ。ただし、父親の皇甫節は、武から目をそらし、文を重んじた。皇甫嵩は叔父の皇甫規にあこがれた。皇甫規は、帝国に圧迫をかけてくる西羌(せいきょう)に対し、わずか八百の兵をもってのぞみ、西羌を退ぞかせた。
皇甫嵩は叔父へのあこがれを抱いたまま、父に対しては孝子であり、後漢では「孝」という道義が人を判断する規準だったから、難なく中央政府に迎えられた。羌族との戦いで叔父の下について参戦し、武人のあり方を大いに学んだらしい。
そのあたり、この時代の官人のありかたを、「皇甫嵩」一篇はこと細かに、しかも分かりやすく描いていて興趣つきない。
皇甫嵩は、いったん引退して郷里にこもった。「いまの政治には、正しい道がない」という批判が胸中にあり、数々の辟召をすべて断りつづけた。そして霊帝の勅使がやってきて天子の徴召を伝えたとき、はじめてそれに応じ、再び中央政府に入った。
黄巾の大乱が勃発すると、霊帝に献言して「党錮の禁」を解いてもらい、いっぽう自ら左中郎将として官軍をひきい、敵の首魁・張角を追いつめてもいる。張角が病死したと知るや、その墓をあばいて首を切り、京師に送るなど、けっこう荒っぽい事績もある。
「百戦百勝しても、戦うことなく相手を降伏させたことにおよばない」という彼の言葉が紹介されているが、それを読んで私は兵法書『孫子』を書いた孫武のことを思いだした。もちろん孫武は数百年前の大先達ではあるけれど、動乱の時代を生きるすぐれた武将は、そのような思想に至るものなのかもしれない。皇甫嵩はそんなことまで考えさせてくれた。