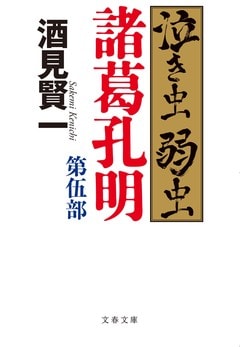何進はいわゆる外戚である。外戚が私欲のために権力を乱用するケースは後漢王朝でも何度か見られたが、何進にはそれがなかった。袁紹、劉表、王匡などが何進の辟召に素直に応じて中央の政府に入った。何進という一見は平凡にも見える人物の人気は思いのほか高かったのである。何進が身につけている謙譲さが人を惹きつけたのだ。自分には学問もないし、才気でこの地位についているわけではない。そういう思いが、人の話によく耳を傾ける姿勢を生んだ。
そして黄巾の乱の戦いで賊を平定するいっぽうで、宮廷に巣食う宦官の悪を正確に認知した。いつのまにか反宦官勢力の旗頭になって、同憂の官僚たちに圧倒的に支持された。
しかし、何進は結局のところ反宦官の戦いに敗れる。彼の献言によって新設された西園八校尉という霊帝直属の常備軍の頭領には蹇碩(けんせき)という宦官がつき、何進はその下の地位となった。すなわち霊帝は愚かな人間ではなかったにしろ、なお宦官への信頼のほうが大きかったのである。
霊帝の死後、何皇后は自分の子である辯を帝位につけるが、宦官一掃などということは思いもよらない。そういう状況のなかで、何進は張譲ら宦官たちの謀略によって暗殺される。中平六年(一八九年)の八月である。
何進という外戚としてはめずらしいほど誠実ひとすじの男の呟きが、この一篇から聞えてくるように私は思った。
《……おのれの教養のなさ、素姓の卑(いや)しさを自覚し、外戚の威をむやみにふりかざさず、属官の意見をよくきいた。ききすぎるがゆえに、決断が遅い、という欠点が生じたが、それでも信望を高めた。》
という一節からも、たしかに何進の呟きが聞えてくる。賢臣たちが、ふつうの人間である男を信じ、その男を清重(せいちよう)な武断派と見た。そのため何進は有力な才能を身のまわりに集め、改革を断行したが、結局は「窮鼠(きゅうそ)と化」した宦官の手にかかって死んだ。朝廷の頽廃が強く匂ってくるのである。
他の名臣たちについても一瞥してみよう。
盧植(ろしょく)は、学問の人。その点、何進と対極にあるような人物で、中央政府に入って活躍するのだが、それ以前の鄭玄(じょうげん)とのかかわり、また弟子となった馬融(ばゆう)の学者としてのありかたが描かれていて、興味津々たるものがあった。
後漢時代を通じても最高の学者とされる鄭玄とは、向うから近づいてきて知り合いとなり、話すうちに馬融という学者の門下に入ることに決心する。初め、「馬季長(融)は、腐儒ではないか」と否定していた男に学ぶ。いかにも、誰について学ぶか、思いまどっている若者の姿がここにあった。