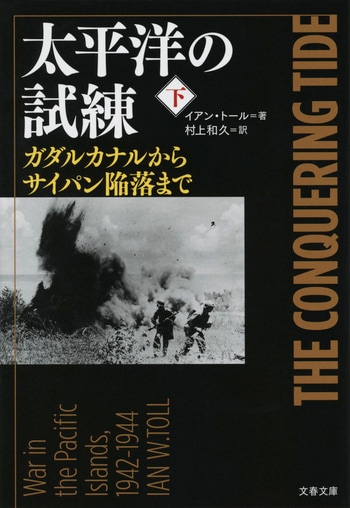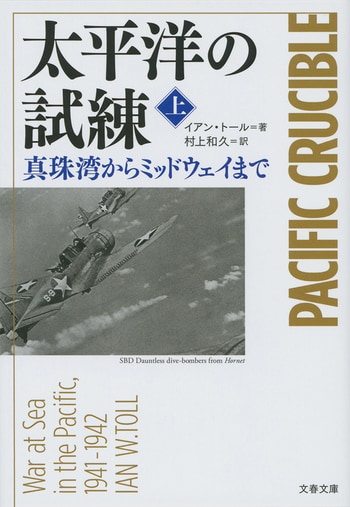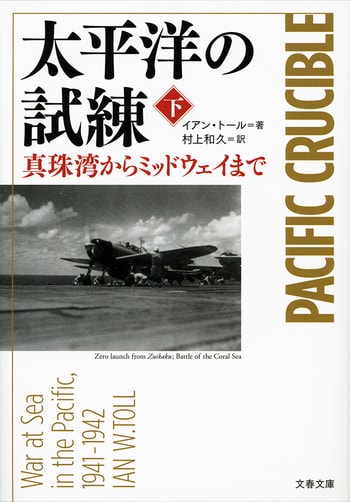その十月中旬はガダルカナル戦でもっともきびしい時期だった。バターン半島とウェーキ島の長い影が、ルンガ周辺防御陣地に投げかけられた。多くの兵士は呆然として、だるそうで、遠くのほうをぼんやりとながめていた。海兵隊員たちはそれを「千ヤード先を見る目」と呼んだ。飛行機を失った飛行士たちは、武器を手当たりしだいかき集めて、塹壕で歩兵に合流した。八月七日以来、包囲された海兵隊員は辛辣なユーモアと強固な団結心でみずからをはげましてきた。いまや彼らはだんだんと相手に八つ当たりをしたり、ささいないらだちの種をめぐって激しい言葉をかわすようになっていた。「誰もがミスをしていた」とトワイニング中佐は書いている。「命令がとどかなかった。通信が通じなかった。遂行が遅かった」(第五章)
第一次ソロモン海戦における日本の三川艦隊の赫々たる勝利はつとに知られているが、艦隊戦闘の経験が不足した連合軍水上艦隊にとって、ソロモン諸島の戦いはたやすいものではなかった。夜戦に長けた日本の水雷戦隊を相手にする、敵味方入り乱れての海戦は、どちらにとっても一歩まちがえば大敗北を喫する恐れがあった。
しかし、キング提督は、いかに大きな損害が出ようと、一歩も退くつもりはなかった。ガダルカナルを反攻拠点とする彼の大戦略がぶれることはなかった。山本五十六大将率いる連合艦隊は、この一歩も退けないチキンレースのような戦闘に、かけがえのない熟練の搭乗員を投入、その結果、熟練搭乗員はどんどん斃れていく。さらに、駆逐艦によるガダルカナルへの物資輸送作戦では多くの艦と乗組員が失われた。そしてガダルカナルを確保すると、キング提督はソロモン諸島を北上して、中部太平洋へ進攻する構想を思い描く。
ところが、それに待ったをかけたのは、ほかならぬマッカーサー将軍だった。フィリピンを追われたマッカーサーは、あくまでニューギニアからフィリピンに進攻する反攻ルートに兵力と資源を集中するよう要求し、中部太平洋路線のキングと対立する。
対立軸はキングとマッカーサーだけではない。対独戦を優先したい英軍と米陸軍首脳部は、太平洋での作戦にまわす資源を最小限にしようとする。上陸作戦を実施する米海軍と、実際に上陸する海兵隊は、どの時点で指揮権を引き継ぐかをめぐって対立する。日本の空襲を恐れる空母機動部隊と、できるだけ長く沖にとどまって空から掩護してもらいたい上陸部隊は、機動部隊が何日間沖にとどまるかでもめる。損害よりスピードを重視する海兵隊と、着実な前進を重視する陸軍の戦術のちがいは、指揮官の解任事件まで引き起こす。積極的な航空作戦を主張する航空畑の将校たちは、空母をなるべく失わないように慎重に行動する水上艦艇畑の指揮官を解任させようと、大統領と懇意の参謀将校を使ってホワイトハウスに電話をかけさせ、ワシントンで反乱まがいの裏工作をする。
日本の陸海軍の不仲と協力態勢の欠如が敗因のひとつだとはよくいわれるが、米軍にしたところで、内部にはこうしたさまざまないざこざがあったことを、本書は記録文書や当事者の証言で赤裸々に描いている。
とくにガダルカナル以降の戦いで米軍がはじめて実施した近代的な水陸両用強襲上陸作戦では、陸海空の三つの部隊を密接に連携させなければならない。米海軍と海兵隊も戦前から研究を重ねていたとはいえ、その準備と実施の複雑さは、従来の軍事作戦をはるかに上回り、そのコンセプトの正しさ自体が疑われるほどだったのである。
海を経由して陸上の敵を攻撃する水陸両用作戦は、ほかのどんな種類の軍事作戦よりも、軍間の摩擦をむき出しにして悪化させた。太平洋戦争は、史上最大で、もっとも血なまぐさく、もっとも多くの代償をはらい、もっとも大きな技術革新をともない、もっとも兵站的に複雑な水陸両用作戦だった。日本軍の征服の潮流を押し返すために、連合軍は島をひとつずつ占領し、赤道の両側で並行するふたつの大がかりな攻勢によって、何千キロもの大洋を越えて前進しなければならないだろう。陸海軍と海兵隊は、持続的で複雑な協力によって、いっしょに活動することを余儀なくされた。彼らは多くのまちがいを犯し、そこから学ぶために最善をつくすことになる。しかし、たとえ彼らの作戦が成功した場合でも、軍間の確執は、勝利でさえ癒せない傷を残した。(第一章)
米海軍と海兵隊も戦前から研究を重ねていたとはいえ、実戦でやってみると不具合が多発し、各部隊間の軋轢をさらけだすきっかけとなった。タラワ環礁の攻略作戦では事前の砲爆撃の不足から甚大な人的被害を出し、アメリカの世論の批判を浴びる。しかし、米軍はこうした失敗体験をフィードバックすることで、両用作戦の戦術をしだいにブラッシュアップしていくのである。
こうした内部での対立をうまく処理する現場トップのニミッツ太平洋艦隊司令長官の手際はじつに印象深い。ときに無理と思える任務を現場に課す典型的なトップダウン型のリーダーであるキング提督やマッカーサー将軍にたいして、ニミッツ提督はあらゆる人間の意見や異議、反論に耳をかたむけるボトムアップ型のリーダーだった。この組み合わせの妙味が、本書では数々の実例によってわかりやすく描かれている。