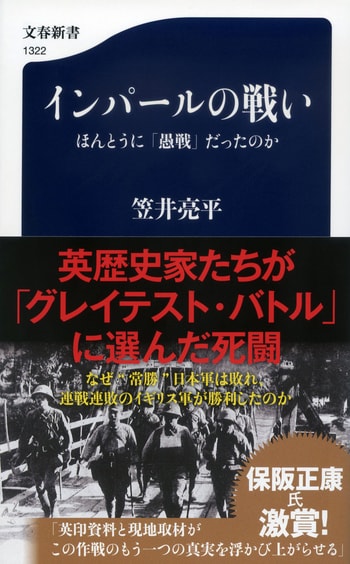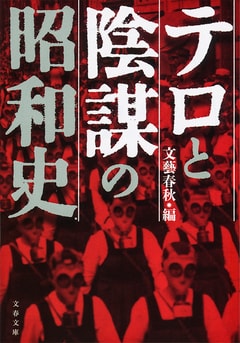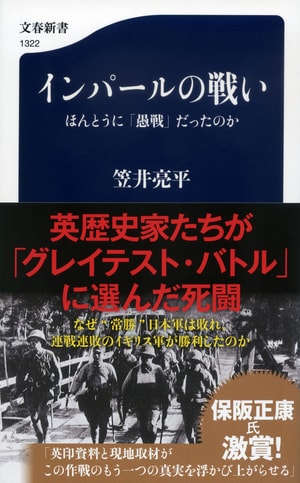
もうひとつは、扱われる「期間」をめぐる問題だ。「ウ号作戦」が実施された一九四四年三月から七月の間に焦点を当てる文献が多く、広くとっても大本営が作戦を認可した同年一月か、牟田口司令官が作戦を推進するべく兵棋演習を行った四三年六月あたりまでなのだ。たしかにその期間が「インパール作戦」と言ってしまえばそれまでだが、この戦いが持つ意味をより深く理解するためには、果たしてそれで十分なのか。もっと長いスパンで捉える必要があるのではないか――そんな気がしてならなかった。
さらに、「インド北東部」という場所とそこに住む人びとの存在があまり語られていないのではないか、という点もある。戦跡ガイドのヤイがこんなことを言っていた。「インパールの戦いは、あたかも誰も人が住んでいない土地で英印軍と日本軍が戦ったかのように伝えられることが多いのです。でも、そんなことはありません。戦場となった場所には、人びとが住み、生活の営みがあったのです」。わたしが感じていたことと、まさに一致していた。激戦が展開されるなか、現地の人びとはどのような影響を受けたのか。英印軍に協力した部族もいたし、逆に日本軍に協力した部族もいただろう。彼らはどんな思いから決断をしたのか。
一言でいえば、インパールの戦いをめぐる日本の議論には、他者の視点とより大きな観点が欠けているのではないか、ということなのだ。戦いの実態を詳細に検証することは必要にしても、その向きを外にも向けるべきなのである。その思いは、現地を訪問していっそう強まるばかりだった。
そこでわたしは、英印軍の視点から書かれた英国の文献やインド北東部の資料を集中的に渉猟し、再検討を加えることにした。元々所蔵していたINA側の資料にもあらためて当たってみたほか、インド北東部に詳しい専門家の話にも耳を傾けた。
その作業から、いくつか重要なことがわかってきた。
まず何と言っても、インパールの戦いに対する英印軍、さらには英国の確固たる位置づけだった。一九四一年一二月から四二年四月にかけて、アジアに駐留する英印軍は快進撃をつづける日本軍の前に惨めな敗北を喫した。マレー半島、香港、シンガポール、そしてビルマと、大英帝国の植民地はまたたく間に失われていった。その結果、インドは帝国の要というだけでなく、アジアにおける最後の砦になったのである。そこに日本軍から攻め込まれ、インパールなど北東部、さらに広い地域が占領される事態になれば、戦況面でも心理面でも深刻な打撃を被ることになる。折から過熱していたインド国内の独立運動との連動も危惧された。帝国の屋台骨が大きく揺らぎかねない状況にあったのである。
当然ながら英印軍はインド防衛だけでなく、反攻の機会も虎視眈々とうかがっていた。ビルマ奪還という目標は一九四二年春の撤退直後から、英印軍のなかで掲げられてきた。問題は、それをいつ、どうやって実施するかだった。ビルマ敗退戦で激しく消耗し、将兵の士気も低下した軍をどう立て直すかも課題だった。
現地で軍を率いることになったウィリアム・スリム将軍ら司令官は、「絶対に負けられない戦い」を制すべく、さまざまな措置を講じた。戦略の練り直し、新たな戦術の導入、将兵の戦意向上に向けた試み、それに現地部族との協力関係の再構築である。
一九四四年三月に日本軍がついにアラカン山系を越えてきたとき、英印軍は万全の状態を整えていた。実際、多くの局面で英印軍は有利に戦闘を展開した。とはいっても、あちこちで「誤算」が生じ、なかには全体の戦況を左右しかねないものもあった。日本軍の将兵は限られた装備と食糧にもかかわらず、あと少しというところまで英印軍を追い詰めた。その結果、「東のスターリングラード」「グレイテスト・バトル」と称されるほどの戦いに発展したのである。
では、激戦の勝敗を決したものは何だったのか。
それは「準備」と「情報」の差である、というのが筆者の考えだ。英印軍はビルマでの敗北から教訓を汲み取り、次の戦いを見据えて徹底的な準備に取り組むとともに、そのために必要な情報収集を行った。さらに、連合軍のアジア・太平洋戦線をいかに有利に進めていくかという戦略のなかにインド防衛・ビルマ奪還を位置付け、味方の損害を最小限に抑えるとともに日本軍の抵抗力を奪おうとした。チェスに例えれば、チェックメイトに持っていくべく敵をじりじりと追い詰めていくプロセスに似ていた。
一方の日本軍は、英国屈服を対米英戦終結に向けたカギと位置づけながらも、大英帝国の要であるインドにどう対処していくかについて戦略を持っていなかった。個々の軍人でビジョンを持っていた者はいたが、それが軍という集団としての共通認識になることはなかった。そもそもソ連や中国に目が向いていた陸軍にとって、インドはおろか南方に対する関心は低く、対米英戦が現実味を増すなかで慌てて情報収集に着手するという有様だった。
たしかにマレー半島で投降インド兵を組織して結成されたINAはあったし、卓越した独立運動指導者のスバース・チャンドラ・ボースも招聘した。F機関から岩畔機関を経て光機関にいたった対インド工作機関も、シンガポールやビルマ、インド・ビルマ(印緬)国境地域で秘密裏に活動を展開し、英印軍にとっては脅威となった。とはいえ、こうした個別の活動が一定の成果を挙げる一方で、インド北東部に進攻して英印軍と戦うことの意味が戦争指導全体のなかで的確に位置付けられることはなかった。
日本軍がインパール作戦を実行したのは、「一発逆転」に賭けたからだった。太平洋戦線で苦戦がつづくなか、インド北東部で輝かしい勝利を手にすることで一気に戦局を転換したいというねらいがあったのだ。牟田口司令官は作戦発起から二か月足らずの天長節(昭和天皇の誕生日である四月二九日)までにインパールを陥落させたいという目標を掲げていたが、そこにも皇軍の戦意高揚を図りたいという目論見があってこそだっただろう。
日本軍の期待を英印軍と同じように盤上ゲームに例えれば、オセロで起死回生の一手によってずらりと並ぶ相手の石を一気に裏返そうとする試みだったと言える。しかし、それはあまりに実行可能性を無視したものだったし、現実としても大失敗に終わったのである。
本書は、このような視点からインパールの戦いを捉え直そうとするものである。すでに読者は気づいていると思うが、本書では「インパール作戦」ではなく、あえて「インパールの戦い」としている。「インパール作戦」と言ってしまうと、どうしても日本側からの視点が主になってしまいがちという考えからだ。日本軍と英印軍を対比させるとともに、インド国民軍やインド北東部の諸部族といった日本では従来取り上げられることが少なかったファクターにも着目することで、この戦いに新たな光を当てたいと考えている。
(「序章 かつての激戦地に立って」より)