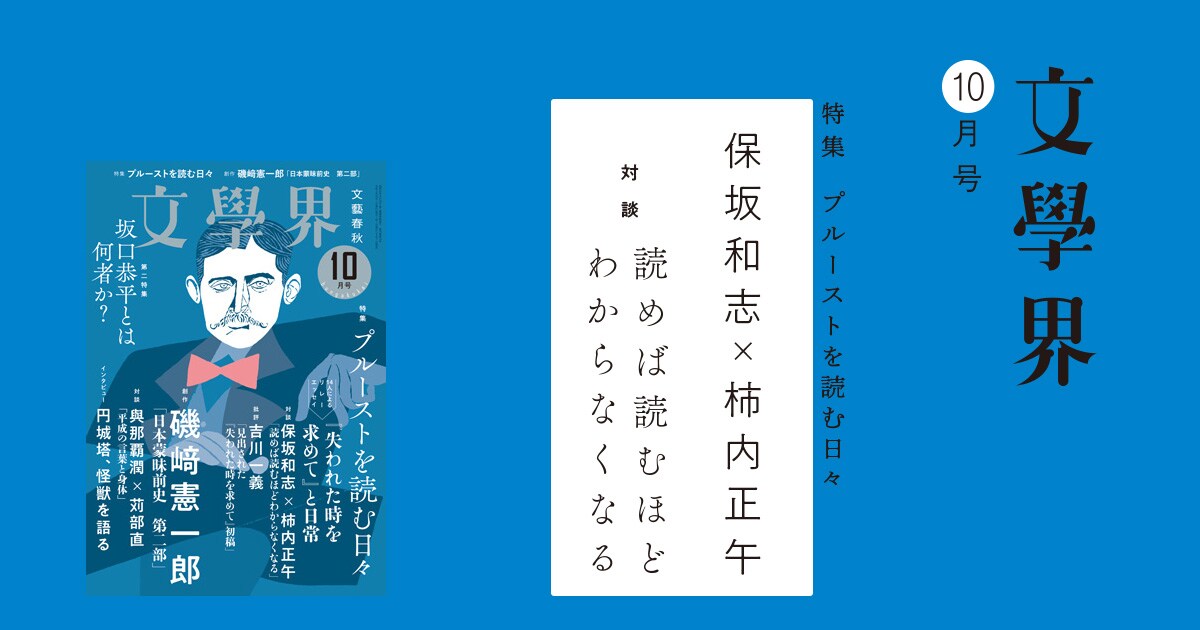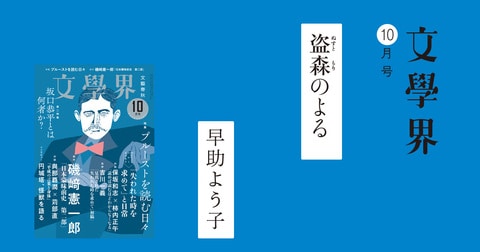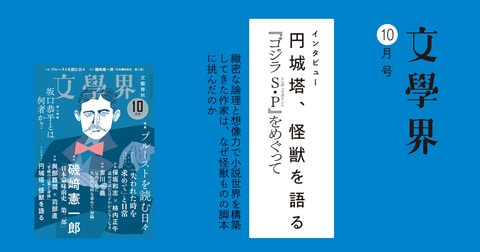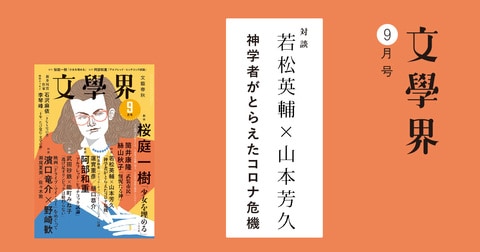保坂 手に取る物体としての形も書いてある中身も、流通形態によって限定されるんだよね。既存のルートで出版していないから、本を書いて出版するのはこういうもんだっていうことに縛られずに書いているなと思った。だから仕上げるために書くんじゃなくて、考えつづけられるように書く。考えを引っ張ってくれるように書くためには、出来上がりの形や、それが流通に乗せてもらえるのかどうかは気にしないで、とにかく自分の勝手にやる必要がある。そこで柿内さんの日記の形式は、すごく有力なやり方だなと思う。本を読む人は、本当は本を読みたいんじゃなくて、考えを与えてくれたり、リードしてくれたりするために読んでるということをよく考えさせてくれていい本だなと思いました。
柿内 嬉しいです。もともと本にする想定もなしに、毎日ブログでただ書くというところから始まっています。小学校低学年くらいからパソコンがある生活で、ブログなどで誰かが書いた文学観や小説の感想を読んでいました。ブログ特有なのかもしれないですが、小説の感想なのに、「読んで元気をもらいました」「明日も頑張ろう」みたいにまとめる感じがあって、子どもの頃からそれをずっと嘘だと思っていたんです。そんなわけないだろう、と。小説を読んで明日からの仕事や試験を頑張ろうとか思ったら、それは小説を読んでないはずだと。明日から頑張ろうなんて社会側に付いた言葉で語れなくなるようなところまで考えを進めていくために本を読むのに。
そして、そこに書かれていたプルーストが全然面白く思えなかったんです。たとえば150年前のフランスの風物や、当時のジェンダー観や戦争観から読み解くような歴史的な読み方も含めて、社会の側というか、人が構築したものの側の言葉にべったり張り付いている間は、その小説を読めていないんじゃないか。その違和感があったからこそ、みんなが偉大だと言っているプルーストを、ちゃんと自分で読んでみようというのが始まりにありました。とはいえ、本当に恥ずかしいんですけど、プルースト読み始めるまで、やたら長い1日の話だと思ってたんです。よく考えるとそれって『ユリシーズ』なんです。ジョイスとプルーストの区別すらついてなかった。
■プルースト文体と訳者
保坂 僕は75年に大学に入学してるんだけど、1年の後半くらいに生協の本屋さんで新潮社のケースに入った『失われた時を求めて』全巻揃いを友達としげしげ眺めながら、「これは有名な小説らしい」「もう一つ『ユリシーズ』っていうのもあるらしいんだ」って話したのを今ので思い出した。『失われた時を求めて』と『ユリシーズ』は、あの時から既にそびえ立っていて、今でも混乱するほどだと思うと面白いね。
僕はちくまで文庫が出る前だったから、新潮社の方で読んだ。文庫が出る前は全集しかなくて、とにかく重いし、何カ所か読んでみたんだけど翻訳が好きじゃなかった。新潮社の方は複数の人が訳してたから巻が変わる度に文体も少し変わるので、それに慣れるのに時間がかかった。あと、『失われた時を求めて』って面白いことに、昔はいろんな出版社の世界文学全集の中であっちこっちの巻が出てるんだよね。中公の「世界の文学」では確か『囚われの女』の巻が入っていた。だから読み比べて、いいと思うとそっちを読んで、必ずしも新潮社の箱入りで読み通したわけでもない。柿内さんはなんでちくま文庫版で読んだの? 僕は文庫だと吉川一義訳の方がいいと思うんだけど。
柿内 最初に読むぞって決めたときに、いろんな本屋さんで各版の1巻の冒頭何ページか読んで、どの訳でいこうかなと考えたんです。岩波文庫の吉川さん訳は親切すぎる感じがして、却下しました。一番読みにくかったのがちくま文庫の井上究一郎さんの訳でした。読みやすくていいはずがない、じゃないんですけど、もともとプルーストについて僕が持ってたイメージは、とにかく長いということと悪文ですごく評判が悪いということ。原文が悪文だといわれるような読みにくさなのであれば、読みやすい訳で読んでもしょうがないんじゃないかなと考えました。
あと、学生時代からレヴィ=ストロースとかフランス系の、のたくった文章を無理やり日本語に翻訳している文章が好きだったんです。フランス語で読めば多分重箱の構造ですっきりまとまってる思考が、日本語に訳すとこんなに訳わかんなくなるのかっていう、その訳わかんなさがよかった。井上さんの訳は無理やり読点で区切っていて、全然終わらない感じがしっくり来る訳のわからなさだったんですよね。今日のために、どんなことが書いてあったか思い出そうと集英社文庫の鈴木道彦訳の抄訳版をぱらぱら見ていたんですが、何読んでたかわかんなくなって何ページか戻って読み返すことが確実に少なくて、もっと訳わかんないまま読んでたいなとあらためて思いました。
保坂 僕が読んだ頃、鈴木道彦訳も出だしたんだけど、あれは読んだ感じが違和感があった。明解過ぎるっていうか、何か厚みがなくて軽快な感じがした。文章って不思議なことに、同じものを訳すのでも、今まで書かれたことを全部引き連れているような訳し方と、その場その場を処理しているような訳し方があって、亀山訳のドストエフスキーがその代表だよね。あの、そこ以前を引き連れない軽快さが読みやすくて今は売れるんだろうけど、前の訳で読んでるとドストエフスキーの感じがしない。
(7月8日、文藝春秋にて収録)
ほさか・かずし 一九五六年、山梨県生まれ。九〇年、『プレーンソング』でデビュー。九三年『草の上の朝食』で野間文芸新人賞、九五年「この人の閾」で芥川賞、九七年『季節の記憶』で平林たい子文学賞、谷崎潤一郎賞、二〇一三年『未明の闘争』で野間文芸賞、一八年、「こことよそ」で川端康成文学賞を受賞。『カンバセイション・ピース』『小説の自由』『猫がこなくなった』など著書多数。
かきない・しょうご 一九九一年生まれ。会社員。「町でいちばんの素人」を自称し、ZINEの制作など文筆を中心に活動。初の単著『プルーストを読む生活』(H.A.B)発売中。Podcast「ポイエティークRADIO」も毎週月曜配信中。
『プルーストを読む生活』の版元ページはこちら
この続きは、「文學界」10月号に全文掲載されています。