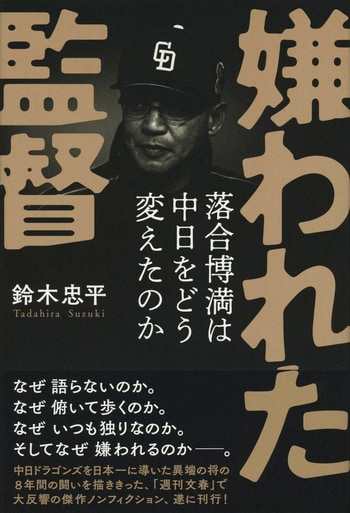8
高かった陽も傾きはじめ、部屋も寒くなってきた。暖かくしてもらえるよう、編集者は何度か該当部署に連絡を入れたが、なぜか一向に部屋の暖まる気配はない。
仕方なく、鈴木は持って来ていたダウン・ベストを、編集者は薄手のコートを羽織った。「寒いですよね。すみません」と苦笑いして謝りながら、編集者は初めて会った2年前の日のことを思い出していた。
年が明けたばかりの、やはり寒い日だったと記憶している。
銀座の喫茶店で編集者は初めて鈴木と会った。「はじめまして」と首をすくめた猫背の姿勢で、控えめに挨拶をする鈴木と、名刺交換をした。鈴木はNumber編集部を離れ、フリーになったばかりだった。新しい名刺の完成が間に合わなかったらしく、Number時代の名刺を差し出した。
その頃、編集者にはある野心があった。
それは、ノンフィクション、それも、痺れるようなスポーツ・ノンフィクションが読みたい、編集したい、というものだった。小説好きが高じて文藝編集者になったのだが、同時にノンフィクションも愛読し、編集もしていた。中学生の頃から「Number」の長年の読者であった編集者は、沢木耕太郎や山際淳司、後藤正治といった、スポーツ・ジャーナリズムの世界で一時代を築いた作家たちの作品を好んで読んでいた。
後に編集者になってから、それらが「ニュージャーナリズム」と呼ばれる、世界的な文芸運動のひとつであったと知った。
「ニュージャーナリズム」の特徴を乱暴にまとめてしまえば、文体として小説的な手法を取り入れ、取材で得た証言などを元に、各場面を臨場感たっぷりに描く、ということになる。つまり、シーンを獲得し、物語を構成する、ということだ。日本のノンフィクション・シーンの先駆者・柳田邦男はかつてこう述べたことがある。
「小説もノンフィクションも、射止めようとしている的は究極において同じものである」
ずっと小説の編集を続けていた編集者には、この言葉に深く共鳴するものがあった。しかし、当時の、2010年代後半のノンフィクション・シーンを見渡すと、そうした作品を見つけることは難しくなっていた。編集者には、その決定的な理由がなんなのかまでは分からなかった。ただ、学生時代に胸を熱くしたようなスポーツ・ノンフィクションをまた読みたいと願っていた。

初めて会ったばかりの鈴木に、編集者は概ねこのような想いを語った。ほとんど一方的に捲し立てていたように思う。普通、作家と編集者の関係であれば、作家が語り手、編集者が聞き手となることが多いのだが(「良い作家ほど、喋りも上手い」というのが編集者のひとつの持論であった)、鈴木は穏やかな様子で聞き役に廻っていた。
「鈴木さんが書いているものは悪くないけれど、試合の状況説明と取材で取ったコメントを並べるだけではつまらないですよ。題材にあった、色んな書き方にトライしないと」とか「長篇の本を書かないと、この世界では認められませんよ」などという、初対面の相手に対してはいささか無礼が過ぎる編集者の発言も、「そうですね」とにこやかに受け止めていた。それが肯定なのか否定なのか、あるいは大人の分別としての意味を持たない相槌なのか、編集者には掴みかねるところがあった。ただ、それでいいとも思っていた。
誰しも、社会人生活を10年も続け、失敗や成功を繰り返すうちに、仕事や仕事相手に対して、期待はするものの、同時に期待しすぎない、という気構えが自ずから出来上がるようになる。まして出版など、本来的に博打の性格を帯びたビジネスで、しかもヒットにならないケースの方が圧倒的に多い。だから、相手に過度に期待しすぎないようにするのが習いになる。そもそも、長篇を書き上げるのには多くの時間と労力を要するものであるから、その博打自体もいつ打てるか分かったものではないのだった。
いつか、一緒に長篇を作りましょう、と話してその日は別れた。期待しすぎずに、である。
それから1年ほどした2020年のある日、編集者は鈴木に対する見方を大きく変えることになる。
それは、ある長距離ランナーについての4ページの記事だった。
編集者は会社のデスクでその雑誌記事を読んだ時、2つの意味での驚きに打たれた。
ひとつは、その記事の出来栄えがあまりに酷かった、という驚きである。率直に言って、よくこれが商業雑誌に掲載されたな、というレベルのものだった。