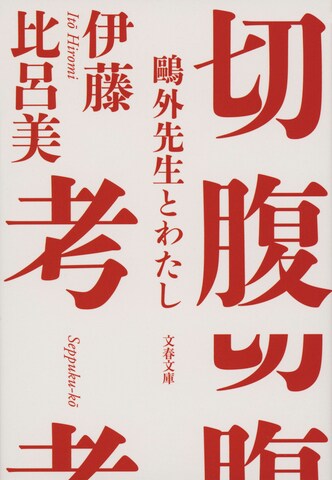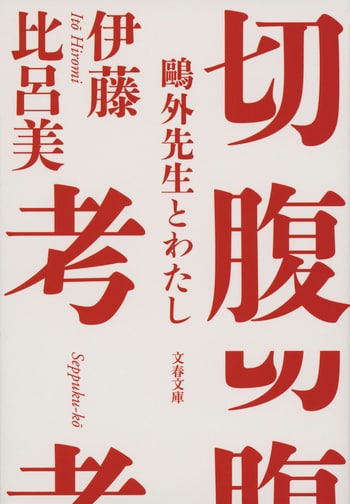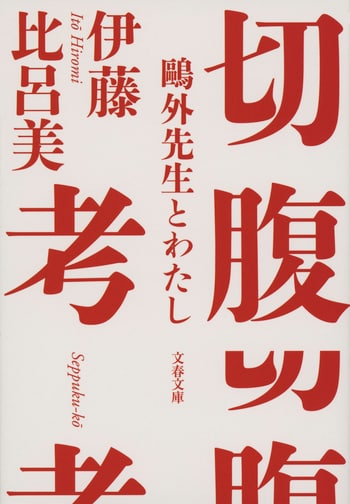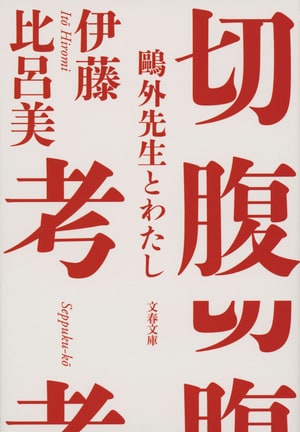
思うに、これはもしや『切腹考』ではなく、『切腹行』なのではなかろうか。説経節を現代語訳して「なまなましい、生きる死ぬるの仏教の世界に身を浸していた」詩人の人生それ自体が、ついに、説経節と分かちがたく混ざり合い、二十年がかりの迷いも深い切腹の道行きを語りだす。
この切腹行の長年の道連れが森鴎外。鴎外でなければならなかった。伊藤に寄り添う鴎外とは、「聖ジュリアン」や「阿部一族」を、原典から自身の言葉のリズムへと見事にトランスレートした鴎外である。「阿部一族」を書かずにいられず、書きながら「これがこの世間の秩序である、秩序であるはず」と悲鳴をあげて窒息して、それでも書きつづけてようやく生きのびた鴎外である。鴎外と連れ立っての道行きの歳月を語る伊藤の声には死の影も連れ添う。たとえば「どの坂もお城に向かう」と題された一文、これは何もかもが湿気にからみつかれた城下町熊本を巡り歩き、そこで繰り広げられた切腹を想い、痛いの苦しいのと言わずに無音で人の死を描く鴎外を語り、いつの日か何もかも壊してやると企むクスノキの巨木の群れの声を聴き、なまなましい、まがまがしい、「どの坂も死に向かう」かのようだ。
伊藤比呂美が言うには、鴎外は伊藤のような知的で我の強い女を繰り返し描いた。「同じ女の姿を、(中略)また一人また一人と書き表していくのである。まるで贖罪みたいに。そしてわたしもまた贖罪みたいに、自分の生きることを曝してきた。自分の生きることを日本語で曝しながら、日本語のわからない男をみつめてきた。
一押し押すと罪が消える。千僧供養である。
二押し押すと罪が消える。万僧供養である。
これまでにも為してきた、あの罪や、この罪を、滅したいがために、ここでこうしてこの男の死に目を看届けようとしている」
異郷で共に暮した男は死ぬ、伊藤はこの世という異郷にひとり、いつか覚えた呪文を思い出す、シューミョン、シューミョン、声明のようだ、祈りのようだ、呪いのようだ、シューミョン、シューミョン、何もかも、崩れ壊れてしまえばいい。まっ青な、虚空だけになるのがいい、呪詛する伊藤は、もう鴎外そのものになりつつある。そして私は、説経節「山椒太夫」を美しいリズムで「山椒大夫」へと書き換えたときに鴎外が加えた一節を想い起こす。「太郎は十六歳の時、逃亡を企てて捕えられた奴に、父が手ずから烙印をするのをじっと見ていて、一言も物を言わずに、ふいと家を出て行方が知れなくなった。今から十九年前の事である」。
行方知れずの太郎は、この世の軛に悲鳴をあげて書いて書いて逃げつづけた森林太郎である、伊藤比呂美である、あらゆる命を惜しみつつ「阿部一族」を書いた鴎外の、生涯最期の言葉、「森林太郎トシテ死セント欲ス」は、もはや伊藤比呂美自身の言葉のようでもある。自分は、自分として、「伊藤比呂美トシテ死セント欲ス」。
私はその声に涙した。
(『文學界』二〇一七年四月号より転載)