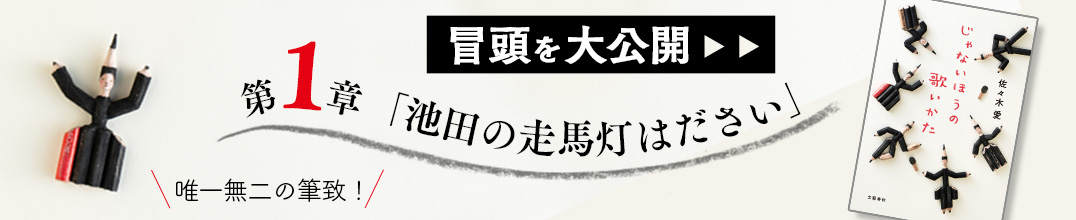『プルースト効果の実験と結果』で鮮烈なデビューを飾り、青春/恋愛小説界にその名を轟かせた佐々木愛さん。最新作『じゃないほうの歌いかた』が、2025年8月27日に発売になりました。
デビュー作の表題作は杉江松恋氏に「2018年恋愛小説短篇のベスト」と評され、第二作『料理なんて愛なんて』は第1回本屋が選ぶ恋愛小説大賞にノミネートされるなど、令和で最も注目されている恋愛小説家です。
最新作の舞台は、落合南長崎にある独立系カラオケ店「BIG NECO」。うだつのあがらない凡人たちの、人生の奇跡ときらめきを描く連作集です。関係者一同悶絶、ぜひこれだけは読んでいただきたい第2章「加賀はとっても頭がいい」の冒頭を公開します。
加賀はとっても頭がいい
今朝の染井さんの体温は、36.7度だったらしい。だからわたしと加賀は今夜、36.7度の湯につかる。
染井さんがグループラインに体温計の写真ばかりを投稿するようになってから、もう半年以上が経つ。36.7度、36.5度、36.8度――、だいたいこんな感じだ。こういうご時世だから、健康でなによりだと思う。染井さんの挙式も延期になっているのだが、実のところ、このまま染井さんの結婚そのものがなくなってしまえばいいと、わたしと加賀は思っている。
わが家の浴室を、都内のひとり暮らし向け物件にしてはやけに広いと、前の彼も言っていた。仕事から帰って、睡眠していない状態で過ごす時間が一番長いのは浴室。二年ほど前にそう気がついてから、バストイレ別、自動湯沸かし機付きの物件にこだわって、引っ越し先を探した。築二十二年だけれど、浴室とトイレだけがぴかぴかにリフォームされていたのが決め手になった。ほかの部分はしっかり二十二年分の時を重ねているので、リビング兼寝室、今は仕事部屋まで兼ねる一室と浴室を行き来するだけで、未来と過去を行ったり来たりする気分が味わえるのもまた、よいと思っていた。引っ越したころはまさか、週四でテレワークになるときがくるとは思ってもみなかった。
もうすぐ二十四時をまわる。37度に設定して、自動のお湯張りボタンを押した。加賀から「こちら準備開始しました」とメッセージが届いたので、すぐ「り」と返信する。最近の若者は「了解」を「り」だけで済ますのだと、二十四歳の加賀が教えてくれたから、三つだけ年上のわたしもその文化を取り入れているのだが、当の加賀の文面はいつもきちんとしている。
「お風呂が沸きました」
メロディーが鳴ったあとで澄んだ女性の音声が知らせてくれる。浴室のドアを開け、ちいさいピストルみたいな体温計を水面にかざす。数か月前に新しく買った非接触型というタイプの体温計は、水面の温度も測ることができるのだ。ピ。その一瞬で、計測は終わる。37.1度と表示されているので、水道から水を足して微調整していく。これが結構むずかしい。初日はスムーズにできたのだけれど、それはビギナーズラックというやつだったのだとやがて気づいた。
熱すぎる日は水を足す。まれに、ぬるすぎる日もあり、そのときは追い焚きをする。この調整になかなか時間がかかるので、最近では少しの差は大目に見るようになっているのだが、加賀は几帳面にやっているのだろうか。
加賀の風呂場に自動湯沸かし機は付いていなくて、昔ながらの蛇口から直に湯を落とすタイプだそうだ。それでも、温度調節にさほど苦労している様子はない。加賀という男はやはり、勘が鋭いのかもしれない。初めて会ったときの加賀の印象は、「野生のシカ」だった。細い身体に、チャコールグレーのTシャツと色褪せたジーンズ、自分で切ったみたいな短髪が馴染んでいた。生まれたときからTシャツ、ジーンズ、短髪の状態なんだと言われても納得できる雰囲気があり、よく聞こえそうな耳と奥に光が宿るつぶらな目が、より警戒心の強いシカを思わせた。
もう一度測ると36.7度だった。脱衣所へ戻って服を脱ぎ捨てる。このところ家にばかりいる日はブラジャーを着けなくなっていて、たったそれだけのことなのに、真っ裸になるまでの時間をものすごく節約できている気がする。
半分だけ閉じた風呂の蓋の上にスマートフォンを置き、つま先からそっと36.7度の水面に差し込む。太もも、腰、腹、胸、首と慎重に、なるべく音も立てぬように、少しずつ少しずつ沈ませてゆく。どうして毎回こんなに恐る恐ることを進めてしまうのか自分自身でもよくわかっていないけれど、なんとなく染井さんの体温の湯に大きな波を立ててはいけないような気がしている。両腕と顔だけを外に出して、つかりきる。気づけば腕に鳥肌が立っていた。36.7度の湯というのは、思っているよりずっとぬるい。夏でよかったと思う。
時計を確認してからハンズフリーで電話をかけると、加賀はすぐに出た。
「きょうは何してた」
約二十四時間ぶりに出す声だった。
「寝てた」と加賀が答える。
加賀は音の出せないトランペット奏者だ。三浪して音大に入ったものの、「なぜか音が出せなくなって」休学しているのだと出会ったころに聞いた。心理的なカウンセリングを受けたりしているが、進展はないようだ。高校時代にも一度、同じ事態におちいったことがあって、大事なコンクールに出そびれたと言っていた。
「サナは?」
「家で仕事して、ごはん食べて、ヨガをして、ラジオを聴いてた」
反響している加賀の声が、わたしの浴室でまた反響している。加賀の家は、古くて狭いらしい。かろうじてバストイレは別だが、浴槽は「銀色でほぼ正方形の、古き良きタイプのやつ」だと聞いたことがある。そこに、ひょろっと長い手足を折り曲げて収まる加賀のことは、想像しないことにしている。礼儀といえるのかわからないが、それに近いものだ。加賀もきっと、わたしの姿を思い浮かべたことなどないと思う。
染井さんの温度につかりながらわたしたちが思うのは染井さんのことだけで、頭の中に流れるのは染井さんが歌うあの曲だけだ。
加賀と知り合ったのは一昨年、つまり二○一九年の夏の終わりごろで、まだ世界は平和だった。染井さんが開くにぎやかな会合の二次会か三次会で、新宿のカラオケボックスにいた。
黙っていてもまわりに人が集まる染井さんには、人と人を結びつけることを自らの使命と思っているようなところがある。染井さんが中心となっている飲み仲間のグループラインには、七十二人が登録されているのだ(つまり染井さんはその七十二人に向けて毎朝、体温計の写真を載せている。わたしと加賀はグループにおける立ち位置を考えてとくに反応しないし、中心メンバー十数人が返信する何らかのコメントにかんしては読み飛ばしている)。
その夜も、染井さんの知り合いが友人を呼び、さらにその友人、そのまた知り合いが集まる混沌とした会だった。仲のよいメンバーが帰ってしまって、わたしはその時点で一時間以上誰とも話していないし歌ってもいなかったが、途中で帰るわけにはいかないと意地になって、隅に座り続けていた。染井さんがまだ、あの曲を歌っていなかったからだ。
誰かが十年以上前の名曲を歌っていて、誰かがそれにコーラスを入れて、誰かと誰かは顔を近づけ笑い合っていて、誰かは誰かにもたれて寝ていて、誰かは誰かに誰の何という曲を歌ってほしいと大声で訴え続けていて、誰かは飲み続け、誰かはタンバリンを振り続け、染井さんはただ、そのすべての真ん中にいた。
飲むわけでも歌うわけでも、ほほ笑むわけでもないわたしは浮いていたが、加賀もまた、浮いていた。
染井さんだけを見ていたくても、実際にそうするわけにはいかない。怪しまれないよう、馴染む程度に目線を動かすことも必要で、そうしているうちに加賀はわたしの視界でじわじわ存在感を高めた。
まわりが仕事帰りとわかる見た目だったのに対し、加賀は見るからに、頼りない種類の人だった。Tシャツ、ジーンズ、短髪、シカみたいな耳と目。テーブルの上は飲み放題のグラスで埋まっていたが、加賀の前にグラスはなく、最初からずっと、持参したらしい355ミリリットル缶のエナジードリンクをちびちび飲んでいた。やがて加賀と目が合った。いつもならすぐそらすが、加賀はそれこそ、広い広い草原で初めて自分以外のシカを発見したような目をしていた。わたしもシカだったっけと考えた少しの間、注視し合った。音楽が遠ざかり、加賀の周りに緑の草木が増えていくのが見えるような気がしたが、加賀がふっとうつむくと現実に戻った。不思議な人だと思った。
加賀はだんだんと奥の隅の、わたしの隣に押しやられてきた。
「これから徹夜とかするんですか」
染井さんが部屋を出たタイミングがあった。やっと気が抜けたわたしは、エナジードリンクの缶に目線をやりながら話しかけてみた。
「いえ、味が好きで」
と加賀は答えた。会話が成立した。野生動物が近寄ってきてくれたときみたいな、こそばゆい気持ちになった。
「味ですか」
「はい。あと、あなたと同じだと思うんですけど」
その時、染井さんが戻ってきて、そのまま入り口近くに腰かけた。加賀は続けた。
「ずっと見てなきゃいけないんで」
染井さんの前髪はさっきより立ち上がって、ワイシャツの首元が緩んでいるように見えた。トイレの鏡を見たんだろうか。染井さんのいる場所が、またぐんぐんと真ん中になっていく様を見ていたら、加賀も同じほうを同じような目で見ているらしいことに気づいて、わたしは加賀の横顔へと完全に視線を移した。歌詞が流れるモニターの青白い光を浴びる加賀は、目だけではなくて、広がった耳もつんとした鼻先も、染井さんのほうに向けていた。まさに、遠くの何かに神経を集中させるシカだった。
加賀が染井さんのほうを向いたまま何か言ったが、知らない曲がじゃまをして聞き取れなかった。
「はい?」
耳を寄せて聞き返すと、加賀はわたしのほうへ向き直った。
「たぶん俺とあなたは恋敵です。さっきから、同じ方向ばかり見てる」
こいがたきという響きが新鮮に聞こえた。
「あなた、名前は」
「サナ」
答えると、加賀は同情のにじむ目になって、言った。
「ああ、だからか。惜しかったね」
わたしは、それで全部わかった。
「じゃあ、あなたは」
と問いかける。
「エイタロウ」
「あれ、ぜんぜん惜しくないですね」
「そう思うでしょう。でもね」
加賀は内緒話をするみたいに、わたしの耳元へ口を寄せた。
「名字はカガなんだよ」
それから加賀は初めて笑った。眉が寄って苦笑いに限りなく近いのに、とても優しい笑い顔だった。
第1章「池田の走馬灯はださい」冒頭も公開中! こちらからどうぞ!