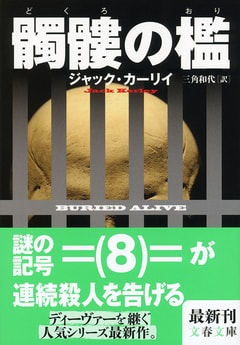そして最後を飾る「佳也子の屋根に雪ふりつむ」の舞台は二〇〇一年、福島。恋人との破局を苦にして自殺を図った佳也子は医師に救われたが、その医師が自宅で殺害される。現場の外に積もった雪には訪ねてきた刑事以外の足跡が存在せず、犯行が可能だったのは佳也子しかいない。窮地に陥った彼女の前に密室蒐集家が現れる。
「足跡のない殺人」ものの歴史に残る逸品である。私は先ほど、この作品を読んで驚嘆したと記したが、それは本作が密室の解明にとどまらず、極めて優れた犯人当てにもなっていたからだ。普通、短篇ミステリは登場人物が限定されているので、その中に犯人がいてもさほど意外とは感じない場合が大部分である。ところが、本作は登場人物が少ないにもかかわらず犯人が意外なのだ。このような短篇を書くことはなかなか出来るものではないのである。
これらの作品に目を通すと、著者は(自身も認めている通り)短篇型のミステリ作家だということがよくわかる。現時点での唯一の長篇『仮面幻双曲』は本格としてかなり凝った力作ではあるのだが、著者の持ち味である淡白なキャラクター描写が弱点となっている印象を受ける。だが短篇ではキャラクターを描き込む必要がないぶん、論理性と意外性という本格としての純粋な骨格の魅力が、読者にダイレクトに伝わるのだ。
ただ、意外性を重視したぶん、偶然に頼った部分がかなり見られるのも事実で、本書の評価が分かれるとすればこの点だろう。しかし、前記『2013本格ミステリ・ベスト10』所収のインタヴューで著者が名前を挙げている横溝正史や島田荘司の作品のように、偶然を多用した優れた本格ミステリの前例は数多くあり、偶然の要素自体が非難されるべきことではない。そして、本格ミステリとしての厳密な論理性を強調する場合ならば本来は反則であろう密室蒐集家という探偵役の設定が、偶然の連なりに伴う違和感を「こういう探偵が存在する世界ならばこんな神秘的な偶然が起きても仕方がない」と和らげているとも言えるのである。
現時点での著者の最新刊は、時効を迎えた事件を犯罪博物館の館長が解決する連作短篇集『赤い博物館』(二〇一五年、文藝春秋)。他にも本に纏められていない短篇のシリーズものが幾つかあるので、密室蒐集家シリーズが次に読める機会はいつになるのか、寡作な作家だけに気になるところだが、『2013本格ミステリ・ベスト10』のインタヴューで「密室蒐集家という設定は気に入っていますし、密室トリックもまだいくつかストックがありますので、これからも活躍させたいと思っています」と述べている以上、再登場の機会はあると信じたい。昭和初期が舞台の「柳の園」の時点で既に警察内部で伝説となっているのだから、明治や大正の頃から彼が活躍していたとしてもおかしくない。時空を超えた名探偵ならではの物語をまた読んでみたいではないか。