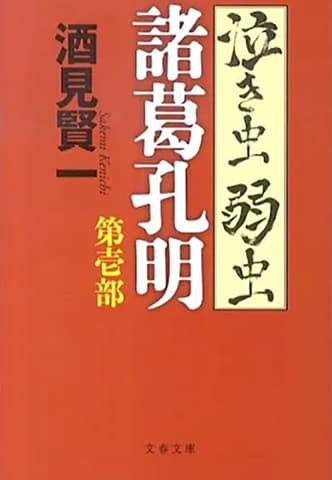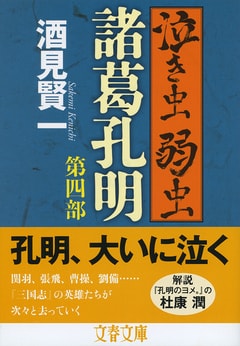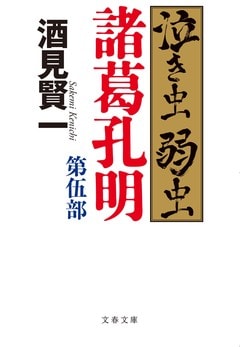「三国志演義」の系譜を継ぐ
酒見 最初は何も考えず書き始めたんですが、書いていくうちに講釈師、講談師の視点を意識するようになりました。
「三国志」というのは、そもそも講談だったり、俗講だったり、庶民の口承文芸なんですね。講釈師が聴衆を集めて、机をバンバン叩きながら劉備や孔明のお話をしていたわけで。
「三国志演義」成立以前の三国志ばなしのことを「説三分(せつさんぶん)」と呼ぶんですが、これは最低限、ストーリーラインの基本はあるにしても、講釈師たちが好き勝手にどんどんオリジナルな解釈を加えていったり、聴衆の反応を見て話を改変していったりする、無数の物語なんです。口承文芸というのはライヴですので、話をしていて聴衆の受けが悪かったら、「その頃、曹操はこんな悪巧みを……」というふうに、場が盛りあがるように話を作ったりすることもあったはずです。受けるように受けるようにと話は延びていったと思うんです。もちろん、その時代の現代語、はやり言葉などもどんどん取り入れ、世情や、大事件も織り込んだでしょうし。
こうして世に溢れていた無数の「三国志」を、十四世紀、明代になって羅貫中(らかんちゅう)が決定版として全百二十回の物語に整え、「三国志演義」をまとめるわけですが、「演義」の中には実在しない登場人物が何人かいるんです。これも講釈師が「そこで現れた○○が……」などと、ほんとうはそんな奴、現れてなんかいないのに、適当に調子のいいことを喋っているうちに、物語として定着してしまった結果ではないか。
ですので、まあ後付けの理屈なんですが、そういう意味でも『泣き虫弱虫諸葛孔明』は、「三国志演義」の系譜を継ぐものである、くらいは言えるのではないかと思っています。
――講釈師のスタイルを採用したということが、虚像を描くということともつながってくるのでしょうか。
酒見 講釈師の場合、聴衆にうけなかったら生活できないですからね。私もけっこう嘘ばっかり書いてますよ。正史の「三国志」や「演義」などですでに書かれてしまっている事柄は、なかなか勝手には変えにくいものですが、その場その場で融通無碍(ゆうずうむげ)にやっているところもあります。
たとえば、まったく無実績、経験なしの若者だった孔明がなぜ「臥竜」と呼ばれるのか。まだ二十七、八歳の若者に、なぜ劉備は三顧の礼を尽くすのか。このあたり、「三国志演義」では謎でも何でもなく当然のことのようにサラリと書かれているのですが、どう考えてもおかしなところだと思うんです。ところが文献にはその理由が書かれていない。この謎は今回の作品の大きなテーマでもあるんですが、自分が講談師になったつもりで、興味のおもむくままに謎を解いてみようという気持ちがありました。講談のようなことを、果たして小説でできるのかということですね。