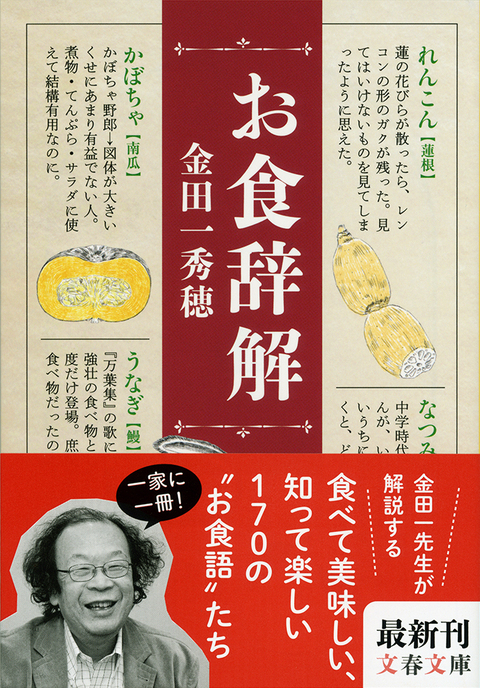食べるという動作を言葉で表わすだけでなく、何を食べるか、どのように料理するか、食べてみてどんな印象をもつか、ということも、言葉に換えたいことである。
日本は昔から、魚をよく食べたので、魚を表わす言葉が多い。魚偏の漢字は、中国ではなく、日本で作られた場合が多い。魚に関しては、関心が高かったのだ。逆に、漢字の本場である中国は、内陸に人が多かったので、海水魚は青魚、黄魚、紅魚ですましてしまうのが一般的である。そのかわり、韓国には、焼肉屋のメニューでもわかるように、牛や豚の身体の部位を細かく区別して言葉にしている。アイヌ語には、熊の小指の付け根を表わす特別な語がある。それが彼らの関心事だったのだ。
料理法についても、中国語は、あらゆる技と知恵を駆使して、区別する。焼き方は、英語が得意である。日本は新鮮な素材が手に入りやすく、あまり手を加えずに料理することが重んじられていたせいか、調理法についての語彙(ごい)は貧しいように思える。
食べた印象は味覚である。味覚は触覚の発達した感覚であり、主に口内で、知覚される。舌だけでなく、歯触りや喉ごしなどが、味と言われるものであるけれど、よく言われるように、人は大脳で食べるものでもあり、いつどこで誰とどんなものを食べるかによって、大きく影響を受ける。特に名前がどのくらい大切であるかは、本書で繰り返し述べてきたところである。ただし、その味を言葉で表わすことはできない。言葉の網は粗すぎる。開高健の才能と真面目さによっても、言葉から喚起させられた味は想像できても、開高に言葉を喚起させた味には、ついに到達できない。
言葉ができる以前も、私たちは何かを食べてきて、それを享受してきた。言葉という不思議な道具を使って、食べる行為を言葉に換えるよう、苦心してきた。食べる言葉の歴史は、営々たるその努力の跡である。
これからも今まで食べたことのないものや味が現われ、それを言葉に換えていくことを人はやめない。いろんな新しい食辞ができてきたら、それは私たちの食生活の豊かさを意味する。楽しみなのだ。
読んでいただいて多謝。
平成二十四年秋
(『「あとがき」にかえて』より)