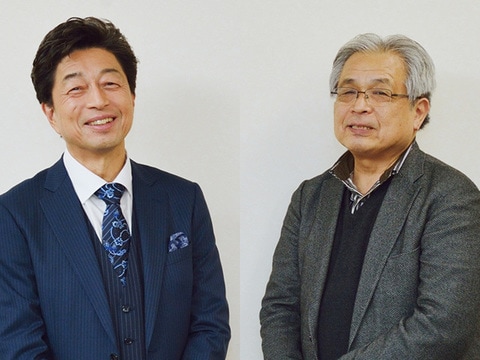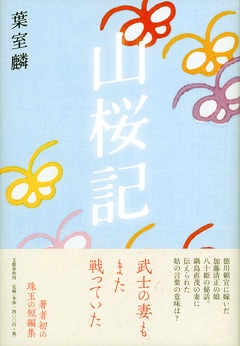家康は関ヶ原で勝利して、基盤である江戸で悠々と幕府を開いたかのように思いがちだが、これは江戸時代を通した見方だ。
関ヶ原の合戦は家康の勝利とされるが実際に石田三成ら西軍の将と戦い、打ち破ったのは福島正則、黒田長政、細川忠興ら豊臣系武将だった。
徳川秀忠率いる徳川の本軍は真田昌幸に阻まれて関ヶ原の合戦に間に合わなかった。家康は豊臣系大名の力で西軍を倒したものの、徳川軍として勝ったわけではなかった。
このため関ヶ原合戦の後、西国には広島の福島正則始め大領を与えられた豊臣系大名がひしめいた。しかも彼らは石田三成を憎みこそすれ、豊臣家を亡ぼすつもりはないのだ。
だからこそ家康は京ではなく、鎌倉幕府の古例にならい、東国で幕府を開かざるを得なかったのではないだろうか。
源頼朝が源氏ゆかりの鎌倉を本拠としたのとは違い、当時はまだ草深い関東の地という印象だった江戸で幕府を開くのは冒険だったと思える。
鎌倉幕府は、三代将軍源実朝が暗殺されると京から摂家の子弟や皇族を招いて摂家将軍、宮将軍とした。これは鎌倉幕府が滅亡する九代将軍まで続くのだ。
酒井忠清が皇族将軍を策したとすれば、自らを鎌倉幕府の執権北条氏になぞらえるつもりがあったのかもしれない。
草創期の江戸幕府にとってありえないことではなかった。だが、忠清は政争に敗れ、綱吉が五代将軍となった。
更紗屋はこの政治の渦に巻き込まれた笹舟のように沈んでいったのだ。
小説の背景に戻ると、綱吉の時代になるまで徳川家は、武権の頂点にいるという自負はあっても、日本国の首都を造っていくということにおいて、不安を抱いていたに違いない。
元禄時代になって好景気を迎え、ようやく自信が持てるようになったと思える。
綱吉は学問を好み、〈生類憐れみの令〉などで戦国時代の気風を残した殺伐たる風潮を改める文治政策に大きく舵を切った。
その中で最も重要だったのが京の文化を江戸にもたらすことだった。
大奥では公家の娘で才媛の右衛門佐(うえもんのすけ)が上臈付年寄として実力者となり、綱吉の側用人柳沢吉保の側室にも公家の娘であり、教養がある正親町町子(おおぎまちまちこ)がいた。
さらにおりんと友情で結ばれた清閑寺家の娘熙子(ひろこ)も大奥に入る。
あたかも江戸で元禄文化の花を開かせるために、京から素養が豊かではなやかな女人たちが呼び寄せられたかのようだ。
前作に続いて越後屋の三井八郎兵衛、俳人の松尾芭蕉ら元禄ならではの器の大きい人物が小説を彩る。
それとともに、本作を特徴づけるのは、上州沼田の大名真田家の圧政に苦しむ農民のために立ち上がった〈磔(はりつけ)茂左衛門〉こと杉木茂左衛門が将軍に直訴する顛末(てんまつ)が物語の軸となっていることだ。