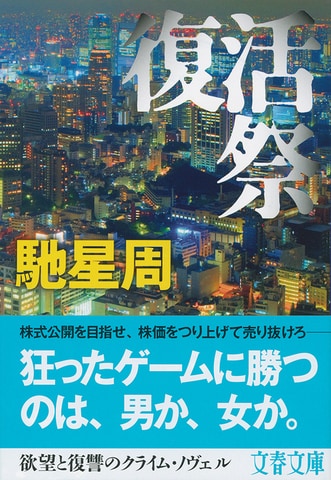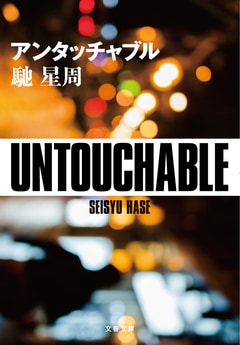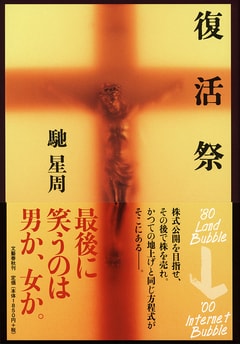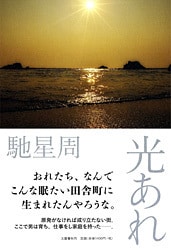そもそも『不夜城』が発表されたのは一九九六年の夏である。すでにバブルは弾けていたものの、盛り場の賑わいは衰えておらず、そんな新宿歌舞伎町を舞台としていたわけで、なぜ中国マフィアが覇権争いを行っていたかといえば、そこに稼ぎがあり、富を得られるからだろう。
馳星周はハメットやエルロイなど、アメリカのノワールと呼ばれる作家から多大な影響を受けていることは知られているが、かれらの小説もまた肥大した資本主義の光と影をさまざまな形で描いていることは言うまでもない。人間の本質をそこに映し出しているのだ。たとえば古典名作ノワールのひとつに、ホレス・マッコイ『彼らは廃馬を撃つ』(白水Uブックス)という小説がある。一九三五年に発表された長編で、大恐慌時代のハリウッドで行われたマラソン・ダンス大会に参加した若いカップルを描いた青春小説である。参加者は昼夜とわず何時間ものあいだダンスを踊り続ける。最後の一組が残るまで競技は続き、勝ち残ったペアだけが多額の賞金を受けとるのだ。その苛酷な生き残りゲームの果てに悲劇が待っていた。この解説のために『生誕祭』『復活祭』を一気に読み返しながら、ふとこの『彼らは廃馬を撃つ』を思い出した。バブル期であろうと不況下であろうとその本質が変わらない以上、ひとは金のためにひたすら踊り続けねばならない。大金を得られるのがほんのひとにぎりの者だけであったとしても、祭りは幾度も繰りかえされていくのだ。
さて、本作刊行ののち、馳星周は、あいかわらず精力的に新作を書き続けるだけではなく、以前にもまして異色作に取り組むようになった。原発マネーに依存する北海道の町を舞台にした『雪炎』(集英社)はまだ従来の路線といえるだろうが、直木賞候補になった『アンタッチャブル』(毎日新聞出版)は、コメディタッチの公安警察ものであり、デビュー二十周年にあたる二〇一六年刊行の『神奈備』(集英社)にいたっては山岳小説である。なにより驚いたのは、やはり二〇一六年に発表した『比ぶ者なき』(中央公論新社)だ。なんと藤原不比等をめぐる古代史ものなのだ。それまでもっぱら現代物を書いてきた作家が後年になり江戸や明治を舞台にした小説を書くようになった例はいくらもあるが、まさか馳星周がこの時代の歴史に挑戦するとは思いもしなかった。
もっとも最新作の『暗手』(角川書店)は、一九九八年に刊行された『夜光虫』(角川文庫)の主人公、加倉昭彦が再登場する。舞台はイタリア。サッカー賭博の八百長計画をめぐる暗黒小説だ。詳しくは触れないが、日本を舞台にした作品ではお目にかかれないガンファイトのシーンがあるなど、これまでにない要素を活かしている。初期作品を好むファンのかたにお薦めしたい。
このように近年の馳星周は、暗黒街を舞台にしたクライム・ノヴェルから、ジャンルの枠をさまざまな方向へとひろげ、次々と新境地をめざしている。これからどんな小説を書いてみせるか、ますます楽しみだ。できることなら、『復活祭』の続編ではなくとも、バブル崩壊から二十年がすぎ、経済格差がひろがるばかりか、若者の貧困が社会問題化している現代日本の闇を切り取った犯罪ものをぜひ読んでみたい。