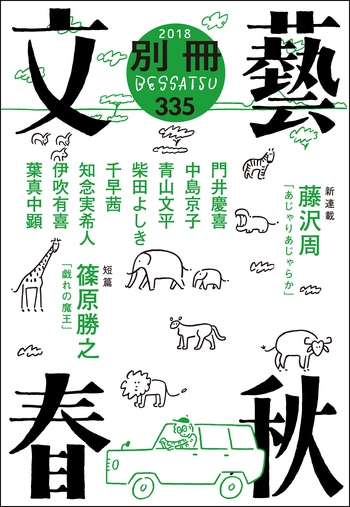それどころか、今日に限って言葉が甘いのは、やはり二十万石の御譜代からの招請を得て、ようやく「奥御手廻り御能」へ幾分なりとも動き出すことができたと感じているからか。目指す志賀藩から声が掛かったわけでも、志賀藩の能を取り仕切る三輪藩の望月出雲守景清殿から招かれたわけでもないが、剛とてじっと動かなかったものがごとりと揺らいだのかもしれぬという気にはなれている。とはいえ、又四郎までもがそのごとりをもたらしたのが鉄砲洲での養老と見なしている風なのが引っかかるし、それに、己れが内藤家からの御声掛かりを又四郎と八右衛門の二人と一になって喜んでいるかとなると心許ない。
奥能の演者に選ばれることは変わらぬ高い的である。岩船保が「ちゃんとした墓参りができる国」にしようとしていた国を成り立たせるためにも、保が遺した三つの言葉をたしかめるためにも的を射抜かなければならぬ。が、いまの剛にはそれに加えて己れが拐った保の能を取り戻すという的がある。この的もまた高い。鉄砲洲での養老ははっきりとその手がかりを得るために勤めたし、延岡内藤家の能もそのように勤めることになるだろう。同床異夢とまでは言わぬが、共に同じ夢を見ているとは言い難い。いつになく甘い能吏にもまた返す言葉に詰まる剛に、又四郎はつづけた。
「百回の稽古よりも、一回の本番でございます」
語りがいかにも唐突に響いて、一瞬、又四郎がなにを言っているのかわからない。
「本番の舞台を勤めるごとに、演者は変わります」
戸惑う剛に構わず、又四郎は言葉を繋げる。
「御藩主の養老も変わったのではありますまいか」
どうやら、又四郎は甘くなったわけではないらしい。速い養老をただ称えているのではなく、額面どおり、「百回の稽古よりも、一回の本番」を言いたいようだ。「内々の能」とはいえ、鉄砲洲での養老は剛が初めて見処のある本物の能舞台で勤めた「本番」だった。つまりは、養老を舞って剛の能が変わったと言っているのだろうが、なんでいまそれを語らねばならぬのかが見えてこない。
「逆に、本番を勤めなければ変わることはむずかしゅうございます」
ともあれ、剛は聞く。耳に気を集める。相手は鵜飼又四郎だ。要る話をするときは決まって要らぬ話から入る者だ。
「百回、稽古を重ねても、視るのは百人の己れだけです。つまりは、己れ独りの目でしか視ておらない。己れがいいとする己れしか視ていません。己れがいいとする間合い、己れがいいとする向き……それらを延々となぞることになる」
野宮での独りの稽古で最も恐れたのが、それだった。だからこそ、保の能と離れることはありえなかった。