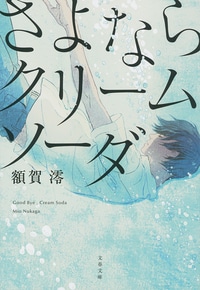
第二に「解法」がないこと。用意された問題がない以上、「こうすれば解ける」というような、定まった解法も存在しません。つまり、問題を自分でつくり出す過程で、その問題の解答方法もまた自分で編み出さねばならないのです。長く美術予備校講師をしていた経験から言えるのですが、美大受験におけるセオリーを質問してくるタイプの高校生は、だいたい伸び悩みます。「石膏デッサンはこう描けばいい」とか「◯◯大学の油絵科なら画面構成をこうすればまず落ちない」とか、確かに受験レベルでの定石はないとも言えないのですが、そうした小手先のテクニックをマスターすることに終始した学生は、美大に合格してから苦労するのです。「あれ? 誰も答え方を教えてくれないぞ?」と。
第三に「正解」がないこと。問題も解法もないわけですから、正解が成立するはずもありません。「こう表現すれば正しい」といったものはないのです。美大受験時によく課されるデッサンの試験などでは、さすがに「最低限このレベルは描けなければならない」といった基準という意味での解答は存在しますが、学問としての芸術はそうした模範解答を決して用意はしてくれません。なぜなら、芸術とは客観的な正しさを追い求めるものではないからです。むしろその真逆であって、求められるのは芸術を学ぶ個々人がそれぞれに見つけた答えであり、なおかつその答えが私たちのまだ知らないもの、見たことがないものであればあるほど、価値があるとされるのです。
どうでしょう? 芸術という学問の苦しさが想像できるでしょうか?















