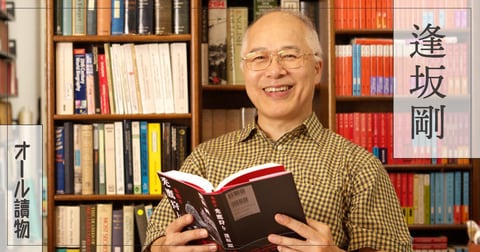「池波正太郎の小説に悪女はいない」と、私は思っている。
“悪女”という設定の女性はいるが、中身をじっくり読めば、愚かだったり貪欲だったり哀れだったり、あるいは男に欺されたり情に搦め捕られて深間にはまったりした挙げ句“悪女”と呼ばれるに至った、謂わば“事情によって悪の道に踏み込んだ”女性たちであって、どす黒い闇を心に秘めた、本当の意味で恐ろしい女というのは、まず登場しない。
言い換えると、池波正太郎は女性に関しては“性善説”を信じていたのだと思う。
映画通としても知られる池波正太郎はあるエッセイの中で、「グロリア」(ジョン・カサヴェテス監督、ジーナ・ローランズ主演)の劇中、マフィアのボスがグロリアを評して「女というのは、みんな母親なのさ」と呟く台詞に、強い共感を示していた、と記憶している。
どうして池波正太郎は“女人性善説”に傾いたのか?
それはひとえに本人と母との関係、そして初体験の女性の影響だったと思う。
実は、私は池波正太郎の随筆と映画評論の大ファンで、学生時代から熟読していた。小説作品を読むようになったのは四十を過ぎてからなので、著者についての予備知識ありまくりで、作品を読んでいると自然と、そこかしこにお母さんと彼女の影響を感じないではいられなかった。
池波正太郎のお母さんは池波さんが七歳の頃離婚し、池波さんを実家に預け、それから再婚し、弟をもうけてまた離婚、下の子と一緒に実家に戻り、その後は、一家の大黒柱として働き続けた。給料が入ると、まずは自分一人で寿司屋に入って握りを食べた。「女ひとりで一家を背負っていたんだ。たまに、好きなおすしでも食べなくちゃあ、はたらけるもんじゃないよ」と仰っていたそうで、まことに正直でサッパリしている。
そして初体験の女性は、吉原の娼妓だった。当時は公娼制度があって、売春は合法である。小学校卒業後、株屋に就職した池波さんは、やがて大人の世界の仲間入りをする。
その頃、吉原では登楼して一度相手が決まると、その店では他の娼妓を指名することは出来なかったという。池波さんもその不文律を忠実に守った。
池波さんにとって初体験の彼女は、単に性の相手ではなく、姉であり、ある意味人生の師でもあったらしい。酒の呑み方、お金の使い方、酒席や仕事上で気をつけなくてはならない事柄、若い人がハマりそうな悪の罠、つまり“人生に必要なこと”は、すべて彼女が教えてくれたそうだ。そして最初の一年は「お母さんが心配なさるから、泊まってはいけません」と、必ず家に帰したそうな……おっと、池波調になってしまった。
池波さんが入営したとき、お母さんは「息子が本当にお世話になりました」と、彼女を訪ねてお礼を言ったという。亡くなったうちの母はこのエピソードを「文部省推薦のお女郎さん」と称した。