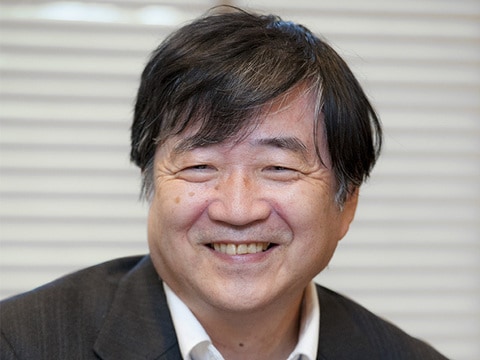北村薫『いとま申して 『童話』の人びと』を読み終える。無類の面白さ。とはいえ、この面白さをどう説明したらいいんだろう……と考えましたが、しばしば脱線するNHKの朝ドラ(あちらも正式名称は〈連続テレビ“小説”〉なのでした)だと取り敢えずは考えてもらっていいんじゃないか、と思います。
ただしドラマなら、主人公が出会わない人物には基本的に登場の機会がなく、その人物を登場させたいなら無理にでも主人公に出会わせなければなりませんが、この作品では出会いません。出会ってもわずか数度だったりします。その代わり、この小説で人びとの結節点になっているのが、おもに『童話』という児童文学誌の存在です。そもそも北村氏のお父上を主人公と考えてみるなら、前半の淀川長治、後半の千代田愛三は端役も端役ですが(前者はお父上と出会ってすらいない)、どちらも強烈な印象を残します。また、人びとを無理に出会わせていないので、この作品を構成する空間がとても広く感じられる。
ちょっと意外だったのは、本書は殊更に世相を切り取ろうとした作品ではなかったことです。時の流れのなかで、いろんなことがありながらも、一人ひとりがそれぞれの居場所で歩いてゆく姿を描こうとしています。評伝とも昭和史とも歴史小説とも少しずつ違うのは、そういうところでしょう。面白かった。
とても広く感じられた、作品を構成する空間──それこそが作者の描き出した“時代”なのだ。昭和という、大きな時代のことではない。作者の父から見た、あるいは第一巻に限って言うなら雑誌『童話』を中心とした時代だ。本書の帯などに使用されている「小さな昭和史」とは、このように切り取られたひとつの時代の経過を指す言葉だろう。
その時代のなかには、西條八十のような巨星がいれば、巨星になるはるか前の淀川長治がいて、千代田愛三のように志半ばで消えた星もいる。そういう星々の軌跡が交差する逸話を読むのはとても楽しい。巨星同士であれば尚更。そのような喜びを読者に与えてくれる作品としては、山田風太郎の一連の〈明治もの〉を真っ先に思い出す。
だが、交差しなかったとしても、矢張り彼らは同じ時を生き、同じ時代をつくり上げているのだ。そのことの素晴らしさを発見し、それを実作として描きおおせていることが『いとま申して』の発明であり、大きな魅力のひとつだと思う。交差しなくても、それぞれに歩みを進める無数の星々の軌跡は、ひとつになって時代をつくる。その煌めき。その雄大さ。
第二巻『慶應本科と折口信夫』ではおもに〈生活と勉学、観劇〉が描かれる。慶應の予科から本科に進んだ演彦青年は、かの泰斗、折口信夫(おりくちしのぶ)の教えを受ける。また友人の影響を受け歌舞伎を好むようになり、しばしば歌舞伎座へ足を運ぶ。そのうちに宮本家はひとつの深い悲しみに遭遇する。その後も世界的不況、父の借金、そして就職難と、暗い現実が次第に演彦の前に現れる。
金がなく、就職口も決まらないまま、観劇に行くことに義姉はいい顔をしない。それでも観に行く。国文学を学ぶ演彦にとって、観劇は学問を深めるために必要だからだ。ただしそうは言っても、同時に楽しみのためでもあるから後ろめたい。しかし観に行く。気持ちは痛いほどわかるが、本だってたくさん買っているし、そんなに散財していいのか、鰻なんか食べて大丈夫なのか、とはらはらさせられる。