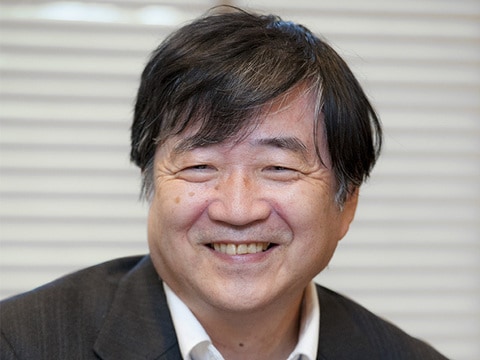このように、第二巻が最も日記に沿って進められるため、演彦は前巻よりも主人公らしくなり、比較的オーソドックスな小説の味わいを楽しめる。しかし多くの資料を参照することで得られた同時代人のエピソードが随所に挟み込まれ(甘粕正彦(あまかすまさひこ)の名前まで登場したときには驚かされた)、矢張り一筋縄ではゆかない。なかでもクローズアップされるのは、当時人気絶頂を迎えていた歌舞伎役者、五代目中村福助だ。時の流れに先駆けようとするかのように生き、大輪の花を咲かせながらやがて時に追いつかれる福助の姿は鮮やかな印象を残す。
初読時は読み進めながら、どうして多くの歌舞伎役者のなかで五代目福助がクローズアップされたのか少々不思議に感じていたが、結末まで読んで納得した。このとき彼ほど“時”を象徴する役者はほかにいなかったからだ。そのことは作者自身も明記している。ただし第二巻を再読したとき、もうひとつ理由を見つけた気がした。手元不如意ゆえに観劇を断念していたら、演彦は五代目福助の絶頂期を目にすることはできなかったはずなのだ。彼は間に合ったのである。
第三巻『小萩のかんざし』は、取り敢えずは〈文学探偵と時〉の巻、と言っておきたい。やや不思議なタイトルは『源平魁躑躅(げんぺいさきがけつつじ)』の無官太夫(むかんのたゆう)敦盛から採られたものだが、このタイトルにどんな意味が籠められていたのかは、最後まで読んでのお楽しみ、としておく。
『いとま申して』は完結編である本書において凄まじい達成を見せる。第一巻の終盤、さながら鎌鼬(かまいたち)のように演彦の眼前を通過し、その登場の鮮やかさの割に第二巻では比較的淡い印象だった演彦の師、折口信夫に、ついに作者が斬り込んでゆくのだ。『六の宮の姫君』『太宰治の辞書』などで実在の作家や作品に関する謎解きを描いてきた作者が今回挑む謎、それが折口信夫その人、なのである。北村作品には文学探偵趣向のものが数あるが、本巻はその濃密さ、達成度で『六の宮の姫君』と並んで最上位に属する。
就職口が見つからず、大学院に進んだ演彦の日々を引き続き描いてゆく一方で、作者は折口信夫と、彼を取り巻く人びとを、唖然とさせられるほどの膨大な量の資料を駆使し、じっくりと炙り出してゆく(その過程で往年のミステリファンなら誰もが知る、ある人物の名前が登場するのもうれしい)。そうして炙り出される折口信夫の大きさには、ただただ圧倒されるしかない。書き進める作者の筆にも、あたかも本丸に乗り込むかのような緊迫感が漂っている──というのは、迫力に引きずられすぎた感想だろうか。しかし、第一巻が『童話』とその時代を描くものであったなら、本巻はまさに折口信夫とその周囲を描くものなのだ。