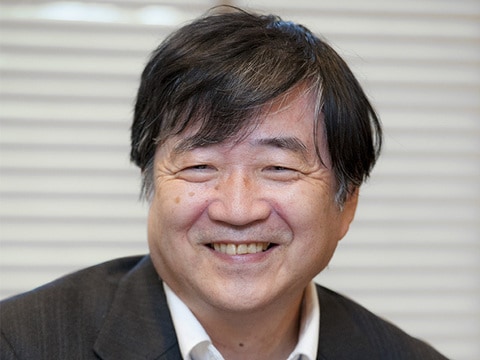折口の、他人に対する徹底的な好き嫌い。「欲しければワンといいなさい」のくだり、相手を組み敷くかのような仇名のつけ方。このようにしか人間と関わることができなかったのか、と思う。作者は「実は、思いやりのある人なのだ」とも書く。そうなのだろう、さまざまな面があってこその人間だ(個人的には、沖縄出身の島袋全幸に向けた「これを読んで怒りたまえ」という発言に、折口の良い面がよく現れているように感じた)。だからこそ、信奉者の愛さえ量るような言動が哀しい。横山重、中山太郎、佐佐木信綱の三人との遣り取りから浮かび上がる折口のおそろしさは苛烈なほどだ。と同時に、天賦の才を持つ人間の、強烈な自負を感じさせる。これだからこそ天才なのだ。これだからこそ天才の仕事が成り立つのだ。折口信夫は人間である前に、天才であったのかも知れない。そして巷間言われるように、天才は孤独だ。本巻ではその孤独もまた描かれる。
本巻には折口と並び、もうひとり記憶に残る人物が登場する。前述の横山重だ。彼も作者曰く「付き合いのため心にもないことをいうような、当たり前の人間ではない。もっと困った男なのだ」。その一方で、横山は不思議な魅力を持つ人物でもあったようだ。
長井光美や藤原弘、そして、本を読むために生まれたような太田武夫が、さらには仮名草子を得意とする森武之助が、そして『竹取物語』に熱意を燃やし『竹取』だけで百冊は見比べて来たという新井信之などが、横山のもとに次々と集まって来るところは、まるで『水滸伝』の豪傑集合のようだ。(本文二五〇ページより)
ひとを集めることができる、ひとを引き寄せることができる人物だったのだろう。その業績に比してあまりに不遇な評価の人物ではあるが、復刻校訂に専心する彼の実直さは、本巻にある種の明るさをもたらしている。その横山の連載「書物捜索」に目を通し、折口信夫が口にしたというひとことには胸を打たれた。これは、横山にとっても当の折口にとっても、大いなる救いとなる言葉だろう。幻の『竹取物語』をめぐる横山と新井信之の遣り取りも心に残るエピソードで、いずれは『書物捜索』を手にしてみたい、と感じさせられる。
そして──終盤、ついに演彦の日記は途切れ、描かれてきたひとつの時代にゆっくりと幕が降り始める。同時に、時間をかけてこの大長編を綴ってきたからこそ書けるような言葉が小説内に頻出する。「その人が、いつまでもその人らしいのはいいものだ」「色々な表情を見せる川の流れも、やがては大きな海に行き着く」「はてしない時の彼方に、この言葉を綴り、刻んだ人がいる」……さらにここで、作者はある小さな驚きを用意している。ここは北村薫の作家性が最も美しく現れた箇所だろう。続いて紹介される手紙の文面、「たとえ今度のこの時かぎりとしても 生きていたうれしさを感じます」……長い長い作品を読み進めてきた読者に対する、作者からのプレゼントのようにも感じられる暖かな場面だ。