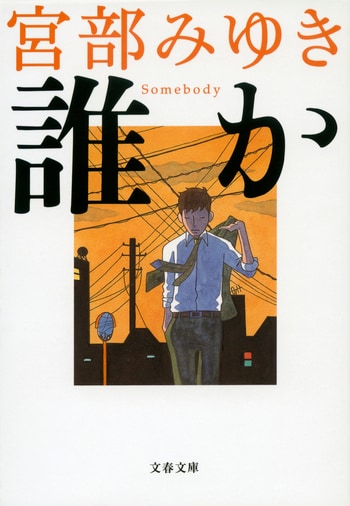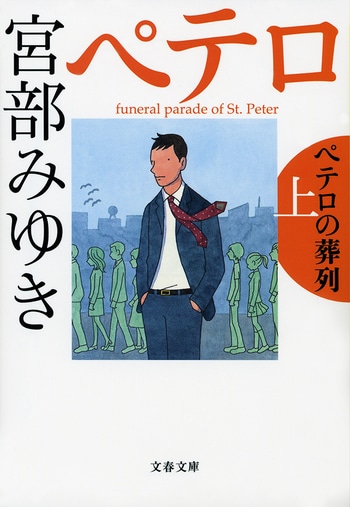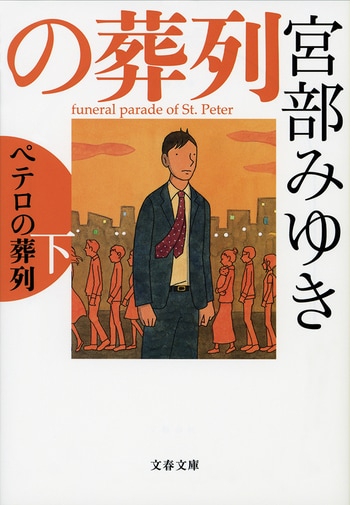アルバート・サムスン・シリーズは主人公による一人称叙述形式と謎解きの関心を融合させた理想的な私立探偵小説であり、『沈黙のセールスマン』は中でも屈指の名作として支持者も多い長篇である。私立探偵といってもサムスンは強面のタフガイなどではなく、人はいいが無力極まりない普通の中年男性だ。このサムスンと、ジョエル・コーエン監督の映画「ファーゴ」で謎解き役を務めた、フランシス・マクドーマンド演じる警察署長マージ・ガンダーソンのイメージが合流したところで生まれたのが杉村三郎だと宮部は語っている。
『沈黙のセールスマン』は個人が対峙する敵という形で企業の非人間性を描き出す物語なのだが、杉村の調査は別のものを浮かび上がらせる。「不愉快で毒虫のいるジャングルの地図」のような人間関係だ。本シリーズの特徴はここにあり、杉村の目は、見かけはごく平穏に見える日常の中から醜悪な要素を見つけ出すのである。無知や強欲は、時として危険な凶器と化す。自分と同じ心が他者にもあることに鈍感であるために、モノのように人間を扱って傷つけてしまうのである。杉村はそうした愚かな人間の引き起こした事件を見聞してしまう探偵だ。そして、「目」でしかない彼にできることは、悲劇を傍観することだけなのである。
続く「華燭」(「オール讀物」二〇一八年三月号)には一転してコミカルな味わいがある。複雑な事情から面識のない女性の結婚式に出席することになった杉村は、二組の披露宴が同時に開催不能になるという異常な事態に遭遇する。主要な場面のほとんどがホテルの内部だけで展開する、一幕物の舞台劇のような中篇である。この作品で注目してもらいたいのは、伏線の置き方だ。物語の中盤、動き続ける事態に読者が気を取られている隙に、作者は大事な情報をさっと舞台の隅に置いてしまう。その大胆さ、さりげなさ。宮部みゆきがミステリー短篇の名手たる所以はここにある。
本篇でも杉村が「目」であることが重要な意味を持つ。
――私の目に見えないだけで、この部屋の天井には何かいるのだろうか。何か厭らしいもの。汚らわしいもの。忌まわしいもの。加奈(かな)さんはそれを凝視しているのか。
これは話が折り返し点を過ぎたところに出てくる文章だ。高校生である「加奈さん」の目には、大人である自分とは違った風景が見えているのだろうか、と杉村が考える場面だ。
話の流れからは少し外れるのだが、ここで杉村が「私の目に見えないだけで」と考えていることが私には興味深かった。杉村こそはまさしく「目には入っているのに見えていない」観察者の役割を担った主人公だからだ。すべての情報はそこにあるのに、正しくその意味を読み取れないために真相には到達できない。だから悲劇が起きてしまうこともある。彼はそうした主人公なのだが、こうした無力さというのは、すべての情報を読者に対してあらかじめ開示することが求められる、ミステリーのフェアプレイ原則を作者が忠実に守っていることの証でもあるのだ。読者は杉村と「目」を共有することで物語世界に自分も立ち会う。
表題作の「昨日がなければ明日もない」(「オール讀物」二〇一八年十一月号)は、身勝手な女性によって周囲の者が振り回されていくという性格喜劇の要素を備えた一篇だ。喜劇の部分は、人により悲劇でもあるだろう。吉川英治文学賞を贈られた『名もなき毒』もそうした物語であったが、人間関係の網は、特異点が生じることによって歪んでいく。宮部はそうした現象を「毒」とかつて表現した。病理のように負性の心理が伝播していく現象が本篇でもまた描かれているのである。