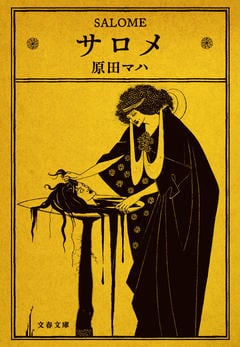恐る恐る送った脚本
山田 最初、映像化は難しいと思ったけれど、僕にとってはどうしてもあきらめられない。そのうちに、僕は昔から僕自身が体験した撮影所の時代、つまり日本映画の歴史の中でも、一番盛んだった、元気のあった時代をもう一回追体験できるように描くことを考えました。それは前々から一度やってみたいと思っていたことでした。
このダメなおじいさんだって、青年時代があって、元気で血気盛んな、能力のある人間だったかもしれない。それが結局その能力を、映画監督として、あるいは脚本家として発揮することができないままに、失意の人生を送るようになったんだけど、彼のキラキラした、しかしちょっと不安定な青春時代というものを映画の中に含めてみたらどうなるか―。その頃から、「待てよ、これはもしかしたら僕はできるかもしれないな」と思って。だけど、一応書き上げたものが、原作と全くと言っていいぐらい違ってきちゃった。

原田 はい(笑)。
山田 こんなものを原作者がうんと言うだろうかと。とんでもないと言って突き返されてもしょうがないなと。非常に不安でした。恐る恐る脚本をお送りしたところ、とっても原田さんが褒めてくださった。
原田 本当に感動しました。おととしの六月ごろ、私がパリに行っている時に、真夜中に担当編集者さんからメールが来て、「脚本の第一稿ができあがりました。正直原作と全く違います」と。
山田 そうおっしゃったわけ?
原田 そうです。ただ、もう読むだけで山田洋次映画が立ち上がってくる。それがその編集者の初見の感想だと。「これをどう思われるかはマハさん次第なので、まずは読んでみてください」という前文があって、それに添付されていたんです。時差があって、真夜中の三時ぐらいに目が覚めてから読み始めたら一時間くらいで一気に読んじゃって。明け方に読み終えて、うわ~っと泣いていました。やっぱり山田監督はすごいと、本当に感動したんです。だからすぐに、プロデューサーさん宛てに返事を書いて。
山田 それがあのメール?
原田 そうです。本当に素晴らしいと。「大きな変更だけど、これは見事な変更だと思います」と。一番感動したのは、例えば通り一遍に原作をなぞって脚本にするということは簡単にできると思うんですけれども、そうではなくて、山田監督が原作を一回取り込まれて、ご自分のものにされたうえでアウトプットされている。その時に、違うクリエーション(創作)になるって実は難しくて、なかなかできないと思うんです。原作者に対する遠慮もあるだろうし。でも、それを思い切ってなさったというのは、私は何よりうれしかったですね。それで、面白かったので、もうこれは文句がないなと。そんなことをこちらから申し上げるのも本当に僭越なぐらい、私にとってはキネマの神様そのもののような方なので。でも、そういう遠慮はなく、本当に純粋に楽しませていただいたので、すぐに返事をしたら、プロデューサーさんが大喜びで。「メチャクチャ監督が喜んでらっしゃいました」と。
山田 ホッとしたんだよね。あっ、よかったなと思いました。
原田 監督ほどの方がそんな、と思うんですけど。
山田 それで、そのメールを印刷してシナリオに差してスタッフに全部読んでもらいました。原作を読んだ人もいるわけだから、「違うじゃねえか」とならないように(笑)。

志村けんさんへの思い
山田 主役のゴウを演じるはずだった志村けんさんが亡くなって一年になりますが、滑稽なことばかりやっている老人というのを、志村さんなら見事にやっただろうと思うと本当に残念です。彼には前々から興味があったんですが、本人は映画をやる気持ちはもともとあんまりなかったみたい。テレビと舞台が彼の仕事だった。だけど、思い切って一度会って、オファーしてみたら、「やりましょう」と。かなりの年齢でもって初めて映画の主役をやるからには、誰だって相当な覚悟が要る。一流のコメディアンですからね。これで恥をかくわけにいかないですよ。だから、相当な気持ちで引き受けてくれたなという思いもあるし、僕はとても楽しみにしていたんです。だから、彼があっという間にコロナで亡くなって、あの時は本当に呆然としました。
原田 去年の一月ぐらいにプロデューサーさんたちが、また私のところに来られて、「いよいよこれからですね。志村さんももうすぐ七十歳になられて」という話をしていた、その二カ月後、三月一日からクランクインされたんですよね。そのニュースを逐一ご連絡いただいていましたし、脚本読みの録音とかも送ってくださったりして、いよいよいい感じで進んでいると思っていた矢先の三月十七日に、パリがロックダウンになって、そのあとに志村さんの訃報に接しました。
山田 撮影も途中で二カ月も休まなきゃいけなかったから、大変でした。だけど、これもキネマの神様が助けてくれたのかな。ゴウ役が沢田研二という全く対照的な、天下の三枚目から天下の二枚目に飛躍して。それはそれで非常によかった。やっぱり神様の応援だと思います。そう簡単に引き受けられる役じゃないと思うんだけど、志村けんとの友情もあったんじゃないのかな。「やりましょう」と言ってくれた時は、本当にうれしかったですね。原田さんの返事をもらった時に次いで、「ああ、よかった」と思った。こんな奇妙な体験は、五十年以上映画を作っていて初めてでした。