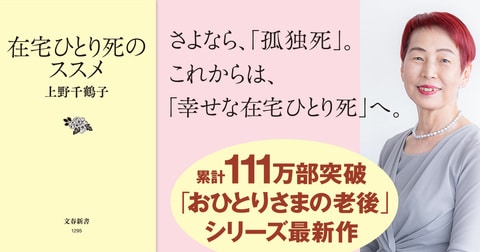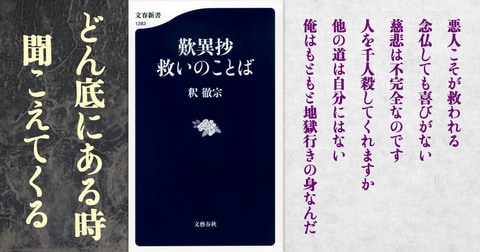和歌は「勅撰和歌集」を頂点とする朝廷と貴族の「雅」の文芸で、滑稽味のある和歌は「誹(俳)諧歌」と呼ばれ『古今和歌集』に載っています。
「和歌の子」「俳諧の母」とされ、俳諧へ橋渡しをしたのが「連歌」です。しかし、平安から鎌倉時代は和歌の余興に過ぎず、南北朝から室町時代にかけて最盛期を迎えます。公卿の二条良基がルールブックとして「応安式目」を制定したことで文芸的地位が高まり、『新撰菟玖波集』で有名な飯尾宗祇が純正連歌の正風を完成させるにいたって、「雅」の地位を確立します。ただし、優美な「有心連歌」が正統とされ、滑稽な「無心連歌」(俳諧体)は異端視されました。
その「連歌」も式目の束縛を受けて衰退し、代わって登場したのが、「無心連歌」の系統を引く「俳諧連歌(俳諧)」です。室町後期の山崎宗鑑、荒木田守武という先駆者により礎が築かれ、江戸時代になって松永貞徳の貞門、西山宗因の談林へと展開します。その後、悪ふざけの談林が、言語遊戯にとどまる貞門を圧倒したものの、宗因の連歌への逆行や井原西鶴の浮世草子への転向により、拡散・衰微していきました。
そこへ登場したのが芭蕉です。格調高い貞門派の北村季吟のもと、上級武士の傍らで出発した芭蕉は、やがて談林へと傾倒していきます。しかし、その悲願は、談林派のような町人の旦那衆の遊び芸を担う俳諧師にとどまることなく、彼らとは一線を画し、「俗」の文芸だった俳諧を和歌の地位まで高めることでした。「雅」と「俗」の対立から歩を進め、両者の総合に努めたのです。
日本の文芸は二つの心情の系譜を持ちます。悲惨な人生を嘆き悲しむ和歌の主軸「あはれ」と、笑いで悲惨な人生に対峙する俳諧の主軸「をかし」です。悪ふざけではない本来の知的な機知や諧謔の笑いは決して卑下されるものではありません。したがって、本来俳諧と和歌は兄弟と言ってよいはずですが、俳諧は和歌と対等なものとしては認知されませんでした。何故か。母体の連歌が和歌の余興から出発したことや、初期の俳諧が幼稚な滑稽詩だったこと、さらに貞門・談林俳諧が和歌など古典のもじりに終始する低級な言語遊戯だったこと、そして点取俳諧という堕落、連句が一座の遊びの文芸として過小評価されたことなど、様々な理由があります。
連句からその発句が独立し、正岡子規の命名で俳句と呼ばれる時代になって評価は高まったものの、戦後は「第二芸術」として痛烈に批判されました。それでも不思議なことに、俳句は文芸の一ジャンルとして決して揺るぎません。なぜでしょうか。俳句には、その高い詩精神への畏敬がやまない芭蕉のDNAが今も脈々と流れていることを、誰もが感じ取るからだと思われます。芭蕉なくば、俳句は今も和歌の庶子的な屈辱に甘んじているかもしれません。
俳諧にはこのような時代背景があります。それではこれから「俳聖」と称えられる芭蕉の真の素顔と旅の足跡を見ていきましょう。
(「まえがき」より)