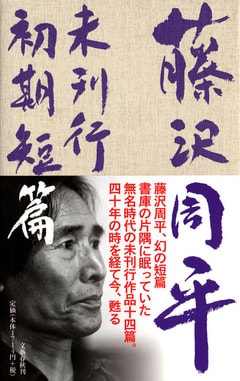『回天の門』は一九七九(昭和五十四)年十一月、藤沢周平五十一歳のとき文藝春秋から刊行された。藤沢作品としては最長の評伝的歴史小説のひとつである。
広い平野部を持つ羽州荘内地方の物成りはよい。だがそれは「一年の三分の一が風雪に閉ざされる土地」だからこその豊かな水のおかげである。清川村はその荘内領の東端、最上川が平野に出る手前の咽喉部にあり、荘内領から江戸への主出口である。参勤交代の行列も清川から隣藩新庄領までは舟を仕立てる。
清河八郎は、その地で酒造業を営む豪農斎藤家の長男として天保元年(一八三〇)に生まれ、元司と命名された。斎藤家は藩から十一人扶持で遇されているものの武士ではない。すなわち藩の後ろ楯を持たぬまま、自らの弁舌と剣を恃(たの)んで世に驥足(きそく)を展(の)ばすべくつとめる清河八郎の三十三年の生涯を、藤沢周平は千百五十枚分の紙幅を費やしてえがいた。
元司は九歳で鶴ヶ岡城下の伯父の家に預けられて学塾に通った。しかし三年後に破門されたのは、持ち前の反抗心と人の意表に出たがる性格、藤沢周平いうところの「“ど”不敵」ゆえであった。
「“ど”不敵」とは、風雪と身分制の重みに身をかがめて生きる東北農民に、時折その反動として出現する性格である。年長者に廓通いを咎められた十三歳の元司が、「面白すぎて、少しこわくなりました」と述懐したような早熟さと大胆さもそのあらわれである。要するに斎藤元司は、少年時代からその土地と豪農の惣領息子という立場に倦(う)んでいたのである。
若くして朽ちかけた元司の心を刺激したのは、弘化三年(一八四六)夏、斎藤家の食客となった旅の絵師、藤本鉄石であった。みごとな南画を描く鉄石は、元司に時勢の知識をも伝えた。それは、前年江戸伝馬町の牢から逃亡した蘭学者高野長英の話であったり、四年前清国の壊滅的敗北で終ったアヘン戦争の話であったりした。江戸に行きたい、広い世界に出たいとかねてから望んでいた元司を鉄石は励まし、元司の顔には「波瀾が現われている」といった。のち文久元年(一八六一)、幕府がまわした手配書に、その「波瀾が現われた」容貌がしるされている。
「歳三十位。中丈」「太り候方。顔角張。総髪。色白く鼻高く眼するどし」
このとき三十一歳、彼は幕府警察組織の手先の首を一刀のもとに刎(は)ね、お尋ね者となっていた。