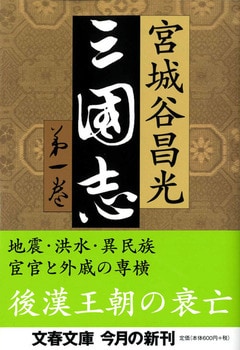2
作家が、この大長篇を楊震(ようしん)の「四知」という言葉から始めたいと早くから考えていた、というのも、この本物の歴史小説への志と深くかかわっている、と私には思われる。
このことは、二〇〇一年の(最初の)インタビューで、「『三国志』を始めるならこの言葉から入りたいとずっと考えてきたんです」と語られているのだが、私たちはすでに大長篇の第一巻に、楊震の「四知」があつかわれている部分をもっている。そこに就いて「四知」から宮城谷『三国志』が始められる意味を考えてみたい。
楊震が現われるのは二世紀の初めで、後漢王朝がいちじるしく衰退してゆく時期よりも少し前のことである。鄧太后が宮廷の中心にいた。
楊震は地方在住の学者として生きていたが、五十歳に至って「天命を知」り、州都の役所に出仕した。そういう男がやがて中央政界の要職に押しあげられて、七十歳を過ぎて司徒に任命された。これは王朝の首相という地位である。
「四知」の逸話は、楊震が荊州刺史であったときのことである。楊震が推挙して昌邑の令になった王密が訪ねてきた。久闊を叙したのち、王密は懐から黄金十斤を取りだして楊震の前に置いた。楊震は、「君はわたしがどういう人間であるのかわかってくれないのは、どうしたことか」という意味のことをいって、これをしりぞけようとした。しかし王密はさらに言葉を重ねて、「暮夜(ぼや)のことです。たれも知りません」といった。
そこに至って楊震は表情をきびしくして、「天知る。地知る。我(われ)知る。子(なんじ)知る。たれも知らないとどうして謂(い)えるのか」
と返した。これが四知である。小説では、次のような地の文がつづいている。
《どんな密事でも天が知り、地が知り、当事者が知っている。それが悪事であれば露見しないことがあろうか。》
《悪事ばかりでなく善行もやはり四者が知るのではあるまいか。》
そういうエピソードである。
楊震は名門の出身ではない。父親は地方の私塾の先生にすぎず、五十歳で官界に入り、ついには宰相にまで昇りつめたのだから、抜擢された秀才官僚の見本のような人、といえるだろう。そういう官僚たちと、皇帝たちを取り巻く宦官(かんがん)たちとの対立が、後漢王朝の構図になったのは、ずいぶん早く二世紀の初めからその芽があったという史観がここにはある。歴史を劇的なエピソードの連なりとしてでなく、もっと大きな人間の時間の流れとしてとらえる思想がこの作家には厳然としてある、というべきだろう。