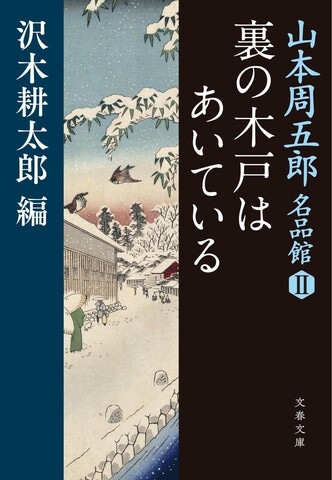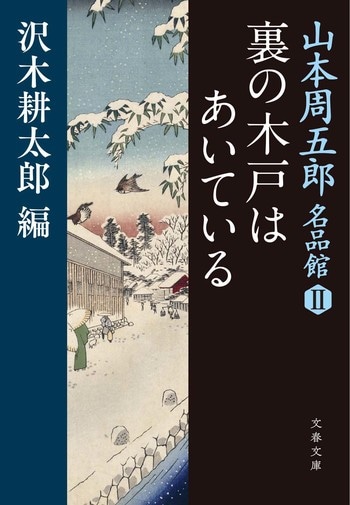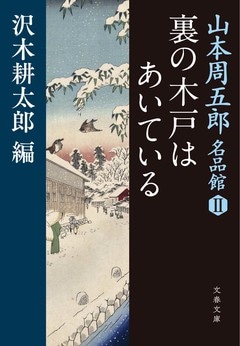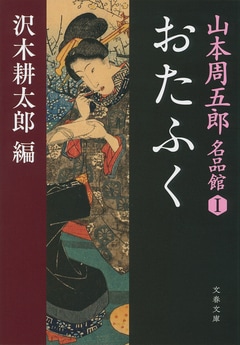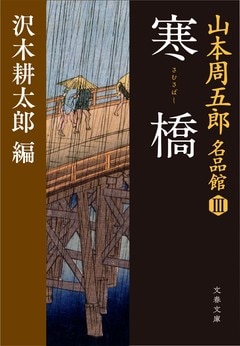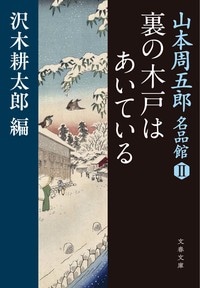
「裏の木戸はあいている」
ある城下町のひとりの武士が、自宅の裏庭に非常用の金庫のようなものを設置し、誰でもそこから金を取り出し使うことができることにする。利子は不要で、元金も返せるときに返せばよいと。いつしか、それは貧しい市井の人々の「救急箱」のようなものになっていた。
それはひとりの武士、高林喜兵衛の幼い頃の苦い記憶から出発したものだった。わずかな金があれば死ななくても済んだ出入りの職人の一家を、大人たちは言葉だけで何もしなかったために死なせてしまった。自分だけは、できることをしよう、と思い決めたのだ。
しかし、そこに、エゴイスティックで卑しい義兄が登場して、その「救急箱」の存続が危うくなりかかる。
ここに出てくる卑小な存在としての義兄の十四郎は、山本周五郎の短編に比較的よく登場してくる人間類型である。真っ当に生きている人間の前に、さまざまな理由から自堕落に生きることになってしまった人間が立ちはだかる。
それに対して主人公たちは愚かしいほど彼らの更生を信じようとする。その結果、立ち直っていくというパターンが多いが、もちろん山本周五郎である。それが単純なハッピーエンドを迎えるだけの物語にするはずはない。
この「裏の木戸はあいている」の十四郎の場合はどうか。
《それでも彼は逃げなかった》
どちらとも言えないような終わり方をするが、希望の火は灯されることになる。少なくとも、高林喜兵衛のヒューマニズムはぎりぎりのところで敗北しないということになるのだ。
しかし。
金があまり潤沢ではない高林家で、家禄の高い実家の法事のためにと高価な帯を新調してしまう妻がいる。そういう見栄は捨ててほしいと言う高林喜兵衛に対して、妻が鋭く反撃する。わたしのやっていることが見栄で、あなたのやっていることが見栄でないと言えるのですか、と。
確かに、意地と見栄との違いには不分明さが存在する。さすがの高林喜兵衛も妻の一撃の前には沈黙せざるを得ないところにこの物語の別のおもしろさが隠れていたりもする。
3へ続く