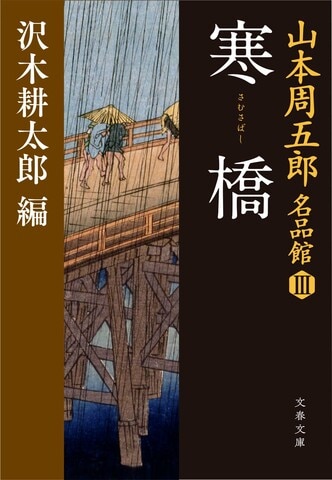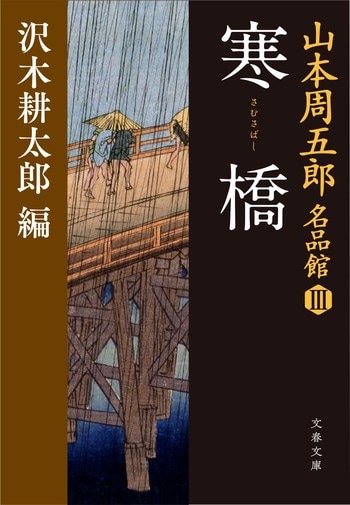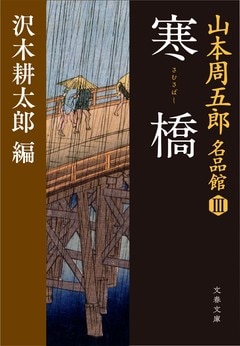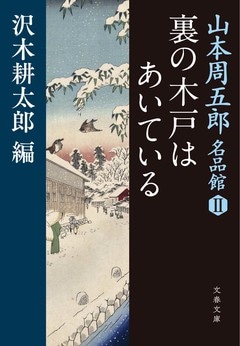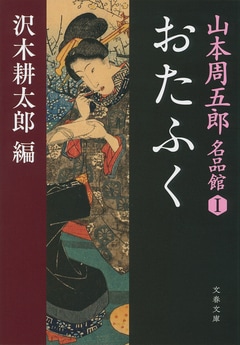「落葉の隣り」
描かれるのは、同じ長屋に住む三人の幼なじみの長い歳月である。三人のうちわけは男二人に女一人。この人数の配分は、若い男女の友情と愛情の交錯を描く物語における「黄金比」のようなものであるかもしれない。
主人公の繁次は、親友になった参吉のことを、自分より数段上の人間だと思い、おひさが好きになるのも当然だと引き下がる。
だが、成人して蒔絵職人になった参吉が、いかがわしい品を作っていると知った繁次は、初めて親友をありのままの姿の人間として見ることができるようになる。
繁次はおひさに言う。
《「あいつはもうだめだ、参吉はいい腕を持っているが、その腕のいいのが仇になった」》
もちろん、この「落葉の隣り」は、『さぶ』に連なる若者の友情物語ではあるが、同時に、山本周五郎の職人観、仕事観がよく出ている作品でもある。
腕がいいだけでも、目端が利くだけでも、真にいい職人にはなれない。たとえば「ちゃん」の重吉は、酔っ払ったあげくにこう言ったりする。
《「身についた能の、高い低いはしようがねえ、けれども、低かろうと、高かろうと、精いっぱい力いっぱい、ごまかしのない、嘘いつわりのない仕事をする、おらあ、それだけを守り本尊にしてやって来た、ところが、それが間違いだっていうんだ、時勢が変った、そんな仕事はいまの世間にゃあ通用しねえ、そんなことをしていちゃあ、女房子が可哀そうだっていうんだ」》
繁次が、この重吉につながる職人になりそうな予感を漂わせながら「落葉の隣り」は終わっているが、最後の台詞は「これからどっちへいったらいいんだ」という絶望的なものになっている。