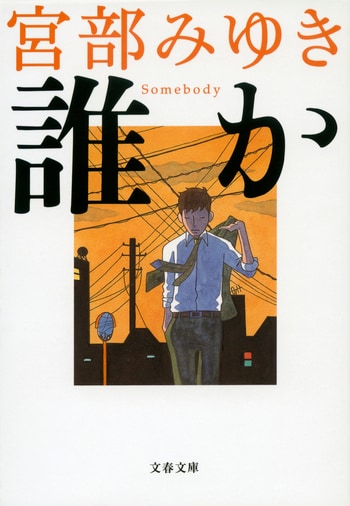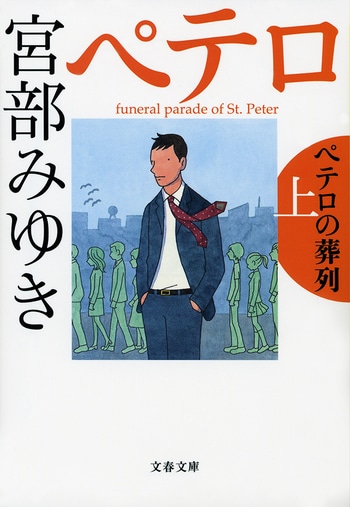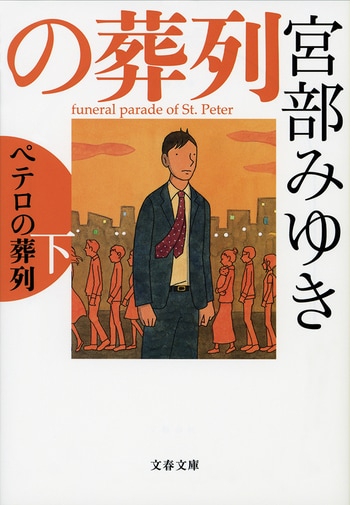実際に「二重身」が書かれたのは大震災から四年半が経ってからのことである。作者は発生直後よりは冷静に事態を俯瞰することができただろう。しかし、東日本大震災が起こらなかったとしても、社会が動いていく中でその歪みを直視する役目を杉村は担っていたはずである。彼という主人公が創造されたのは、まさにそのためだからだ。
十年近い準備期間をとって宮部は杉村三郎という人物に肉付けを行い、「目」の役割を担わせるために世界へと送り出した。社会そのものを揺るがすような天変地異が起きたのは人智を超えた大いなる偶然であった。宮部が漠然と感じていた杉村という「目」の必要性は、この出来事によってさらに高められたといえる。『希望荘』以降の短篇に明確な日付が記されるようになったのは、この連作に現代日本の姿を写し取りたいという、クロニクル記述への欲求が強まったためではないだろうか。かつてスウェーデンの作家マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールーは警察小説のマルティン・ベック・シリーズを書くことで、変わりゆく祖国の姿を記録に留めようとした。この先書かれていくであろう杉村三郎の連作も、同様の役目を担うことになる可能性がある。
「二重身」で杉村は、ある人物から「未曽有の大災害による悲劇に、感情的に揺さぶられる部分を脇に置く」べきであるという助言を受けている。それが最終的には彼に真相を見破らせることになるのだが、事件の推移に心を奪われるな、というのはアマチュア時代の杉村には難しいことであった。それは冷静な第三者、すなわち傍観者に徹せられる探偵の職業的な能力だからである。この教えを受けて事件を解決したことにより、杉村は探偵としてまた成長を遂げ、次の段階へと進んでいく。