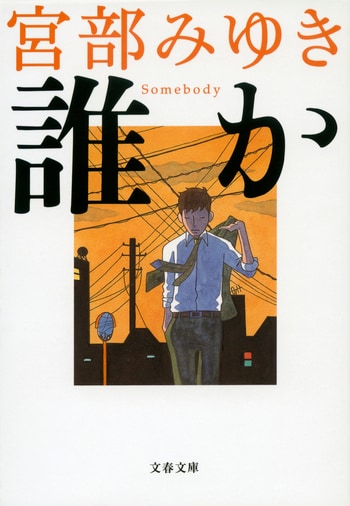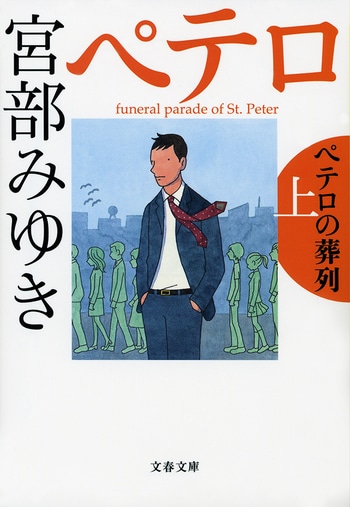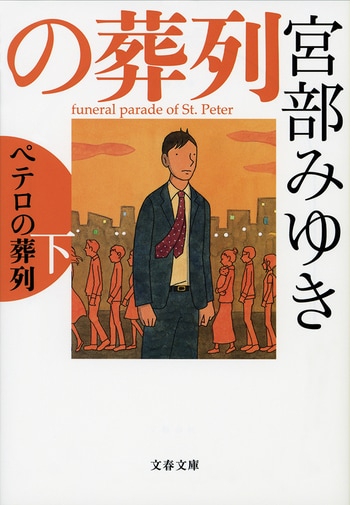『希望荘』という作品集を見渡して改めて思うのは、やはり杉村三郎シリーズは心の受容器が鈍くなってしまった人たちの物語だということである。そうした人々は自身が毒を垂れ流していても気づかず、あるいはそれを構うことなしに続けて周囲の人々を傷つける。収録作以外では、「オール讀物」二〇一八年三月号掲載の「華燭」が、そうした人々の行為が奇怪な事態を発生させるという一篇である。
本書の中でもっとも明るさを感じさせるのは表題作だ。人はいつでも変わりうると信じた者を話の中心に置いているからである。しかし、それ以外の三篇の結末には、人の愚かさに対する諦念を感じざるをえない。たとえば「聖域」は生きにくい世の中で救済を求める者たちの話なのだが、彼らの中にも自身のエゴイズムを顧みることがない人間が紛れ込む。その人物と対話して推理を告げたあと杉村は、会見の場所がコーヒーショップであったために「当分、コーヒーの香りを嗅ぐのも嫌だ」と嘆くのである。しかし探偵を職業としてしまった杉村には、自らの役目を投げ出すことはもう許されない。そして、家族という心の避難場所もどこにもないのである。「聖域」は悔恨の後味を残す一文でしめくくられる。この苦さも、以前のシリーズより強まった要素の一つである。
過去の長篇をお読みになった方は、『誰か』が美空ひばりの「車屋さん」、『名もなき毒』が「丘を越えて」の唄でしめくくられていたことをご記憶だろう。それは暗く、重い現実を見た後に訪れたひとときの慰めだった。どんなに辛いことがあってもそれは一過性のもので、現実は再び明るさを取り戻させてくれるだけの弾力性を持っている。まして杉村には愛する妻と娘がいたのだ。しかし彼は、『ペテロの葬列』でそうした幸せを手放してしまったのである。彼の耳に明るい唄が届いても、もうそこに慰めを見出すことはできない。