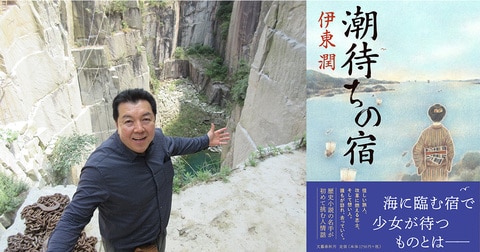隣で医家が何か言っているが、その言葉は頭を素通りしていく。
三幡が三歳の時に行われた「髪置き」の日のことを、政子はよく覚えている。「髪置き」とは、幼児が髪を伸ばし始める三歳の頃、無事な生育を願って行われる儀式のことだ。その時、頼朝はもちろんのこと、大姫と頼家もそれぞれの乳父の家から集まって食事をした。ただそれだけのことだが、頼朝一家にとっては一年に何度もあることではない。この時ばかりは乳母や女房たちも次の間に下がっているので、政子は子供たちと話をしながら、晴れ着が汚れないよう、三幡の世話を焼いていた。
――あの時が、私の幸せの頂点だったのかもしれない。
その時になって、ようやく法印の声が耳に届いた。
「尼御台様、三幡様は――」
「ああ、分かっておる。三幡は亡くなったのだな」
「残念ですが、身罷られました」
神妙な顔で法印や薬師が下がり、背後から女房たちのすすり泣きが聞こえてきた。だが政子だけは、三幡が亡骸になったという実感がわかない。
――もはや悲しみの涙も乾いたのか。
三幡の顔を見ていると、ただ眠っているとしか思えない。
建久十年三月二日、頼朝の四十九日の仏事を執り行ってから三日後のことだった。三幡が風病(風邪)にかかったとの報告が入り、急いで三幡の住む中原親能の屋敷に行ったが、三幡は少しばかり熱があるだけで元気にしており、政子は歓談して帰ってきた。