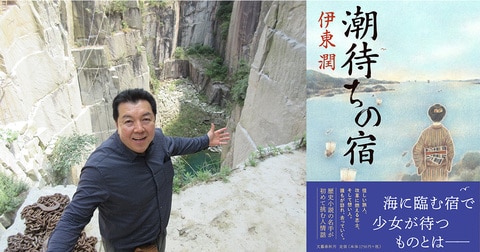この時、政子にも相談があったので、異存がない旨を伝えた。
ただしこの制度は、十三人の宿老が一堂に会して合議するのではなく、数名が評議し、その結果を頼家に提示し、裁決を仰ぐという方式だったため、頼家に最終決定権は委ねられていた。
だが頼家は、この制度に不満を示した。頼家の側近たちの存在意義がなくなるからだ。それでも最終決定権は握っている上、あくまで頼家が将軍として政務に慣れるまでの暫定的措置とすることで、ようやく納得した。
「それほど多忙なら、境目相論などの些細なものは宿老たちに任せればよいではありませんか」
「母上、たとえ小さな村であっても、入会地や水源の権利は村人にとって死活問題です。それらに目を通し、証文などをじっくりと吟味した上で裁可を下すのが、それがしの仕事です」
そこまで言われてしまっては、返す言葉がない。
「分かりました。もはや致し方なきことです。この子の冥福を祈って下さい」
頼家は数珠を取り出すと、しばし手を合わせた。
「可哀想な妹でした。冥福を祈っております」
そう言い残すと、頼家は立ち上がった。
「えっ、それだけですか」
「それ以外、何ができるのです」
「せめて葬儀の差配など、直々に執り行ってはいただけないですか」
「それがしは将軍ですぞ」