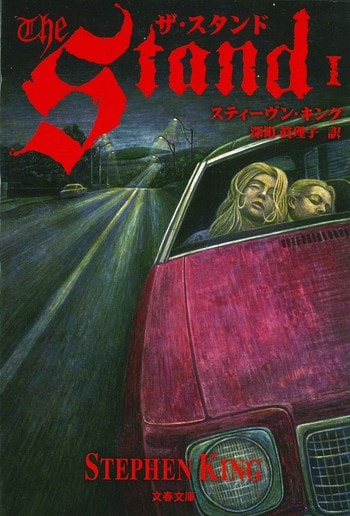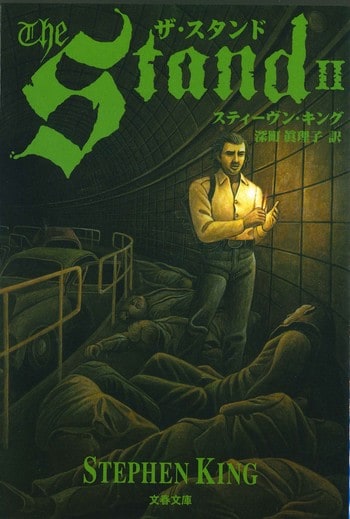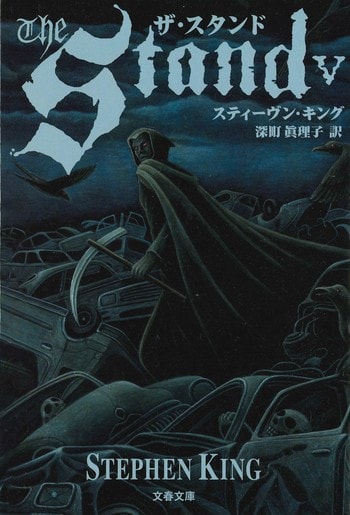ところでいま、“吸血鬼を招いた”と述べたが、なぜ吸血鬼は招待されないと他人の家(領域)に入れないのだろうか?
一説には、吸血鬼は悪魔だと考えられている。悪魔は狡猾である。奴の誘惑はとてつもなく巧妙だ。自分がとがめられることなく相手に罪を犯させる。「自分は何も悪いことはしてません、あんたが自ら進んでしたことです、文句を言わないでください、いわば自業自得です」というわけだ。悪魔は不法侵入をしない。礼節を保つ。相手が門戸を開いて、足を踏み入れるのを許可してくれるのを待つ。悪魔は悪くない、咎(とが)は誤った判断をくだした相手にある。そんな罪を犯した相手に罰をくわえるのが悪魔の役割だ。魂を地獄に封じ込める=吸血鬼化するという刑罰である。
本書では、この“吸血鬼を招き入れる”ということがひとつの重要なキー概念になっている。このことは、ストレイカーがマーステン館と店舗を購入してジェルーサレムズ・ロットに入り込むさいの不動産屋との契約の方法からすでに語られている。あるいは、吸血鬼となった友人がマーク・ペトリーの二階の寝室に訪れる有名な場面。
要するに、誘惑VS自己抑制力、運命VS自由意志の問題である。人間の行動には自由意志があるのか、それともすでに運命によって決定づけられているのか。これは自己責任の問題にかかわってくる。悪と善のいずれかを自己の意志で選択できるなら、そこに責任とそれにともなう義務が生じる。だが、悪を行おうが善をなそうが、はなから決まっている(運命づけられている)のなら、なんら自己責任は生じない。責任がいっさい生じないのなら、モラルも必要ないのでは? といった、人間が秩序だった社会を営むうえで根源的な問題が、そこにはある。ちなみに、この“吸血鬼を招き入れる”ことを問題化した作品として、ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィスト『MORSE──モールス』(映画化『ぼくのエリ 200歳の少女』)がある。
『呪われた町』以降は従来の『吸血鬼ドラキュラ』型=外部からの侵略者としてのヴァンパイア小説は敬遠されるようになった。キングがそのタイプの吸血鬼物語を『呪われた町』で総決算し、結果的に終止符を打った形になったからだ。つまり、キングはドラキュラ・タイプの物語の金字塔を打ち建てたのだ。後続の作家たちは、その聳(そび)え立つ塔を前にして首を垂れて退散するしかない。この塔を凌駕する建築物を設計することは不可能だ、と思い知らされながら。