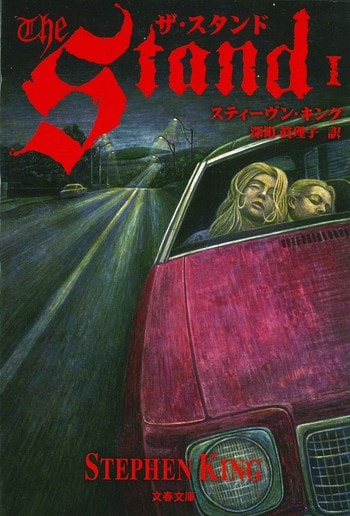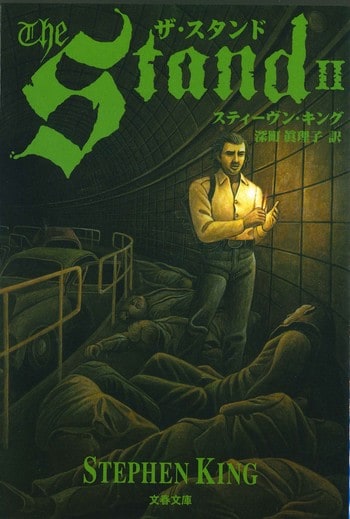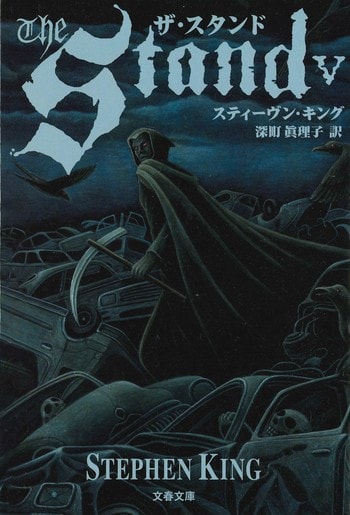話を元に戻すと、悪霊に取り憑かれた場所(バッドプレース)としてのマーステン館は、のちの『IT』のニーボルト通り二九番地の廃屋や〈ダークタワー〉四巻『荒地』のダッチ・ヒル館、そして『シャイニング』のオーバールック・ホテルなどの原型である。本書で下敷きになっているのは、シャーリー・ジャクソンの名作『丘の屋敷』(五九年、本書中では『丘の上の幽霊屋敷』)だ。
マーステン館の借主にして〈バーロー&ストレイカー商会〉の表(昼)の顔であるストレイカーの中古家具店主としての御婦人方の受けの良さと働きぶりは、『ニードフル・シングス』の謎の雑貨店の主人リーランド・ゴーントに通じる。『ニードフル・シングス』は、キングのお気に入りの架空の町キャッスル・ロックが崩壊に至るまでの悪夢を語っているが、スモール・タウンものとしての『呪われた町』の発展形態として推奨したい。
前半の物語から一転して、『呪われた町』の後半は、いうまでもなく『吸血鬼ドラキュラ』タイプの吸血鬼ホラーである。
キングが本書のアイデアを得たのは、妻と友人との三人で昼食をとっているさいの雑談からだった。現代アメリカにドラキュラ伯爵が蘇ってやってきたらどうかな? とキングが切り出したら、妻のタビサがこう答えた。「不法移民としてすぐにつかまるか、大都会でタクシーにはねられてしまうかね」すると友人がこう言った。「でも、メイン州の辺鄙(へんぴ)な田舎町にやってきたら、どうなるかわからないんじゃないかな」
そう、人口千人から三千人ていどのスモール・タウンでは何が起きても外部には気づかれない。広大な全米に散在する無数のスモール・タウンは一種の陸の孤島、隔絶された空間なのだ。誰かがいなくなっても、また見知らぬ誰かが現れてもたいしたことじゃない。たとえ死者が蘇っても。
一方、内部では田舎の村社会の噂・ゴシップ好きは尋常ではない。またたくまに噂は広まる。その伝染性の強さはさながら流行り病。吸血鬼というウィルスが爆発的に感染するにはもってこいの舞台だ。
『呪われた町』がおもしろいのは、『吸血鬼ドラキュラ』の衣裳を現代風にしながら、吸血鬼を伝統的な他者としての悪、外からの侵略者としての脅威として描くよりも、すでに悪霊に取り憑かれている場所が住民そのものとなっている町での内なる悪の万華鏡をメインに語っている点だ。つまり吸血鬼がジェルーサレムズ・ロットを植民地化するために目をつけたのではない。そのスモール・タウンに昔から潜む邪悪な精霊が吸血鬼を招いたのである。邪悪な精霊、それはかつてカルト教団が崇めていた〈蛆〉かもしれない。その〈蛆〉が別の形態をとると、デリーという名のスモール・タウンの地下に太古から潜む『IT』として表象される。