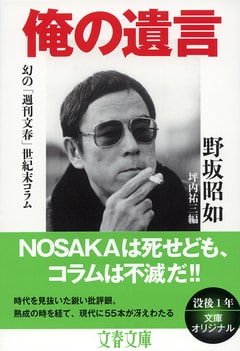『靖国』は、日本人から戦争の記憶が薄れないかぎり、ずっと読み継がれるべき近代日本文化史の傑作である。そんな大げさな言い方を著者は大っ嫌いだろうが、構わずに、そう断言してしまおう。戦争の記憶を喪失することがあってはいけないのだから。
東京っ子の著者が、東京のど真ん中(のすぐそば)の「土地の記憶」をあの手この手で引き出した、これは東京本の傑作でもある。本の人であり、酒の人であった著者のホームグラウンドは「本の街」神保町と「酒の巷」新宿だった。二つの町を繋ぐ靖国通りの中間(といってもずっとずっと神保町寄り)に聳えるのが靖国神社の大鳥居で、界隈には九段坂と日本武道館がある。『靖国』はそのすべてを含む。「靖国問題」という議論の立て方ではけっして見えてこない広い展望が、大らかに開けている。
『靖国』は、二〇二〇年に六十一歳で急逝した坪内祐三の初期の代表作であり、本来はデビュー作として着々と準備されていたのではと想像される。書き惜しみ、出し惜しみしているうちに、たちまち売れっ子の評論家となり、次々と雑誌に書いた原稿が、一九九七年に評論集『ストリートワイズ』(晶文社)、読書コラム集『シブい本』(文藝春秋)となって先に出てしまった。それで心ならずも三冊目の著作となって、二十世紀末の一九九九年に出たのではなかろうか。
坪内祐三が生前に出した数十冊の著書のうち、書下ろしはたった二冊しかない。マガジン・ライターを自称した著者らしいといえばらしい。その二冊とは本書『靖国』(新潮社)と『新書百冊』(新潮新書、二〇〇三)で、後者は新潮新書創刊のラインアップの一冊。読書案内を兼ねた読書自叙伝にして「出版情況文化史」というユニークなものだった。養老孟司『バカの壁』、磯田道史『武士の家計簿』と一緒に書店に並んだ本なのだ。
『新書百冊』は「一種の出たとこ勝負で執筆」(著者あとがき)されたが、『靖国』は「構想十年」という、ありがちな謳い文句をつけても誇大広告に該当しない、慎重に準備された書下ろしだった。「プロローグ 招魂斎庭が駐車場に変わる時」に書かれているように、そもそもの始まりは一九八九年、「東京人」編集者時代の散策途中の「怒り」である。「怒り」というと大げさかもしれない。本文では「私は酷(ひど)いと思った。まったく反射的に」、「静かなる衝撃を受けた」としか書かれていない。その「衝撃」を刊行までの十年間持続させたのは、著者特有の激しい怒りが渦巻いたからとしか思えない。
一九八九年は昭和から平成へと変わった年で、「歴史」がことさらに振り返られた年だった。「プロローグ」を執筆した一九九五年とは、戦後五十年の節目の年で、八月十五日には自民・社会・さきがけ政権の村山富市首相の所謂「村山談話」が閣議決定され、発表された。そのニュースを見ながら執筆をしていたのだろう。インタビュー「歴史の物差しのひとつとして」(評論集『右であれ左であれ、思想はネットでは伝わらない。』所収)で、一九九五年当時の執筆の様子を明かしている。
「その夏はすごく暑かったから、パンツ一丁で執筆したのを覚えています。戦後七十年[二〇一五年]の今振り返ると、靖国神社はずっと問題にされていたかのように錯覚する人もいるかもしれませんが、戦後五十年の夏にはまったく問題になっていなかった。それなのに、何で自分はパンツ一丁で『靖国』を書いているんだろうと思っていたのを覚えています」
一九九五年とは「村山談話」だけでなく、阪神淡路大震災とオウム真理教の地下鉄サリン事件の年であった。坪内祐三は昭和三十三年(一九五八)生まれで、オウム真理教では本部前で刺し殺された村井秀夫が同い年である。坪内には『慶応三年生まれ 七人の旋毛(つむじ)曲り』という夏目漱石、宮武外骨、南方熊楠、幸田露伴、正岡子規、尾崎紅葉、斎藤緑雨の「同い年」七人組の評伝もある。同い年とか同学年とかに、異常なほど興味を持っていた坪内だが、マイケル・ジャクソンも同い年、「花の中三トリオ」の山口百恵、森昌子、桜田淳子が同学年になる。同い年のもう一人のスーパースターについては、その現役引退に際して、この年に原稿を書いている。「原辰徳の口にした「聖域」」(「諸君!」一九九六・一、『ストリートワイズ』所収)で、原辰徳が読売ジャイアンツの現役選手だった十五年間を以下のようにまとめている。
「極端なことを言えば、この十五年間[一九八一~一九九五]は、私たちが、過去との繋がり、つまり「歴史」を次々と失って行く過程でもあった。「歴史」を失った私たちの前には、常に、永遠の「現在」が広がる。(略)八〇年代で例外的に「歴史」を感じさせた出来事は、八九年の昭和天皇の崩御だった。日常の中から「歴史」を失いつつあった時、それを不安に思う人びとは、たとえそれがフィクションに過ぎなくとも―いやもともと「歴史」だとか「伝統」だとかにはフィクションがつきものではないか―かろうじて残る「歴史」に触れようとした。自分たちが「歴史」の一員であることを、昭和天皇の生涯を通して確認しようとした」