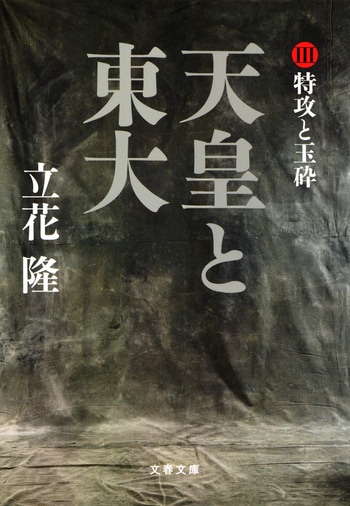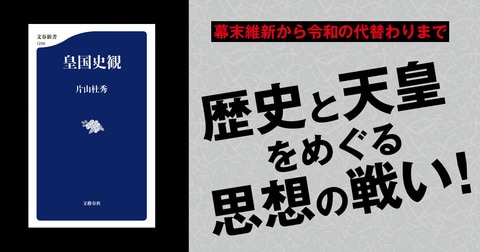兵器開発に加わった工学部
ではまず、平賀譲総長のお膝元である東大工学部の終戦の日の様子を描いてみよう。当時1年生だった第一工学部造兵学科の青木三策(元東海大学工学部教授・元群馬県中小企業振興公社顧問/昭和23年卒)はこう証言する。
「上級生は勤労動員などで学校にいませんでしたが、私たち1年生は動員されず、夏休期間中も、みっちり授業がありました。8月15日、1時限目は吉識雅夫先生の船舶工学の授業だった。吉識先生は、戦後日本を世界一の造船大国に導く立役者となった高名な方で、このときは博士号を取得したばかりの新進気鋭の教授でした。
授業が終わったとき、吉識先生が、『昼に重大な発表があるから、皆、安田講堂へ集合しなさい』と、伝えられた。それで、同じクラスの石井(平八郎/富士通顧問)らと安田講堂へ向かったのです。
それが、終戦の詔勅だったわけですが、ガーガーと雑音がうるさくて、何を放送しているのか、私には内容を理解することはできませんでした。クラスメイトのだれかが、『おお、戦争に負けたんだ』と、口走って、そうか、と思った。頭の中が真っ白になりました。負けるだろう、と思ってはいても、本当に負けたらどうなるのか、想像などしていませんでしたし。ただし、正直なところホッとしました。これで、空襲はなくなる。それだけでも救いでした。詔勅の内容がどうだったかというより、これからますます食えなくなりそうだから、しっかり勉強しなくては、と気を引き締めたものです。
安田講堂を出た後、石井と、『宮城へ行ってみよう』と好奇心にかられるまま、出かけました。皇居には、土下座している人の姿もあったが、人影はまばらで、なんだか平然としているな、と感じたのを覚えています。靖国神社へも行ってみましたが、ここも静かなもので、騒ぎらしきものはありませんでした。
私や石井は、第一工学部の造兵学科を専攻していましたが、終戦となって、造兵学科は廃止されました。それでも、兵器というのは、そのものが精密機械であり、その時代の最先端技術が集約されているから応用はきく。学科名は精密加工学科(昭和21年)、精密工学科(昭和22年)と変わりましたが、勉強自体は従来通りでした。たとえば、魚雷には制御工学が関わっているから、それを別の機械工学に活かすことができるわけです」
芋づる式に捕まるかも
同じく工学部1年で船舶工学科の土屋孟(元海外漁業協力財団勤務/昭和23年卒)も安田講堂にいた。
「8月15日は、午前中、講義に出ていたと思います。教務室から連絡があって、昼に重大な発表があるから、安田講堂に集るように言われました。その頃、本郷の東大構内には、工学部の1年生くらいしかいませんでしたよ。文科系の学生は学徒動員で軍隊へ徴用されていましたから。
安田講堂に入って、私は1階の真ん中から少し後ろのあたりに席をとりました。壇上には、ラジオが置いてあって、その後方には、内田祥三総長が立っていました。(へえ、あれが総長か)と思った。どんな服装だったか、ハッキリとは覚えていませんが、後にも先にも内田総長の顔を見たのはその時だけです。どんな発表があるのか、ソ連が宣戦布告してきたから今度はソ連も相手にしなければならないのか、と思っていたら、放送が始まった。
玉音放送は、私はわりあい明瞭に聞こえました。雑音でよく聞き取れなかった、という話が一般的ですが、そうではありませんでした。戦争に負けた、ということもわかった。
(とうとう、負けたか。勝てる戦争じゃないと思ってはいたが。アメリカ軍が上陸してくれば死ぬしかないのか)
そんなことを漠然と考えていましたね。
放送の後で内田総長が演説しましたが、立派な内容ではなかった、という印象しか残っていません。もともと内田総長は建築の専門家で、喋るほうは得意じゃなかったし、敗戦という事実が、衝撃的でしたから、放心状態というか、頭のなかは空白でした。
総長の演説が終わって、私は船舶工学科の教室に向かった。吉識先生は、
『これから、どういう話になるかわからないが、造船は戦争と関係が深い。芋づる式にみんな捕まるといけないから、とりあえず、故郷に帰りなさい。これから、各自、黒板に行き先を書いて、ノートに写し、全員写し終えたら、黒板を消して帰りなさい』
と、言われ、その通りにしました。私らの同期は、地方出身者が多かった。しかも、学科試験が廃止され、選考で入ってきているから、地方出身者はそれぞれの高校では1番か2番の優秀な連中です。私は故郷に帰れ、と言われても、東京の出身です。千駄木町の住所を書きましたけど、そんなことを言われると不安でしたね。
いったん、自宅待機して、10月には呼び出しがあり、講義が再開された。船舶工学すなわち造船は、海軍が作ったものだから廃止になるのではないか、という噂がありました。造兵、火薬、航空機学科は実際に廃止されました。造船も危なかったが、紙一重のところで残されたと聞きました。
昭和21年2月11日、安田講堂で紀元節の式典が開催され、南原繁総長が演説した。その頃、私は戦争に負けた日本は奴隷になるのではないか、と真剣に思っていました。南原総長も、たしか、そのような心理について触れていましたよ。
『もしわれわれにしてなほ茫然自失虚脱の状態に止まるならば、われらを待つてゐるものは奴隷の不幸と、遂に民族の滅亡である』 (『新日本文化の創造』)
この演説を聞いて、(そうだ。国を立て直さなくちゃいけない。そのためには意識を変えなくては。これからは科学技術だ。それなくしては、日本はたち行かない)と強く思いました」
石油工学科の増産能力
当時の日本は石油不足に悩まされていたが、日本の石油産出能力については、当時1年生の椎名清(元関東天然瓦斯開発監査役/石油工学科/昭和22年卒)の話に、その一端を見ることができる。
「昭和19年から勤労動員で新潟の帝国石油に行き、職工として井戸を掘りました。大学で習ったことを役立てるというより、ただの肉体労働です。石油もある程度は出ましたが、燃料になるほどではなかった。こんなことをしていて国のためになるんだろうか、と同級生たちと話したのを覚えています。
私が勉強していたのは、石油工学の採油についてです。どう井戸を掘って石油を取るかという勉強をしていたわけです。石油工学科は、戦時下で海外、特に南方へ送る技術者を養成するという意味があったのだと思います。しかし、今から考えると、学問のレベルが低かったように思います。空襲で授業ができないことも多く、ノートを出せば単位をもらえるといった状況でした。
玉音放送は安田講堂で聞きました。夏休みで授業はなかったと思いますので、なぜ学校にいたのかは思い出せません。講堂に集まれという指示があって移動したら、人でいっぱいでした。学生や先生、事務員もいました。整列はしていませんでしたが、座席には座らず、みんな立っていました。
玉音放送を聞いているときは、陛下の声なのだという意識はありましたが、内容ははっきりとは聞き取れませんでした。ただ敗戦だということはわかりました。なかには泣いている人もいました。ただ、先生たちは前の年から『この戦争はもうだめだ』と言っていましたので、敗戦が驚きという雰囲気はありませんでした。私は、空襲などでつらい思いをしていたので、やっと終わってよかったという気持ちがありましたね。理工系は文系みたいに戦場に行っていないので、戦場で亡くなった仲間たちに比べたら、戦争そのものの深刻さというのはわかっていなかったかもしれません。
戦時中から、工学部は石炭や金属、化学、造船という花形分野に人気があり、石油には優秀な人は来ませんでしたが、戦後はますます『石油なんかダメだ』と言って、応用化学や医学に転科した人もいました。入学したときは20人ぐらいだった同級生が、卒業時には10人ぐらいになっていましたから。
石油工学科というのは東大にしかなかったので、卒業するとみんな石油関連会社の一線に出ました。復興期に石炭中心から石油中心に変わっていったのは幸運でしたし、日本の経済成長を支えているという意味で仕事のやりがいもありました」
陸海軍の委託学生制度
しかし、本郷のキャンパスで終戦を迎えることができたのは、ほんの一部だけだった。多くは陸軍や海軍の委託学生、または勤労動員で大学を離れていた。
「玉音放送は平塚の海軍第二火薬廠で聞きました。自分の意志で海軍の委託学生になり、昭和20年1月から働きました。配属された第二火薬廠は火薬をつくる研究所で、教官の1人は東大の教授でした。学生は1年上も合わせ計20人ぐらいが行っていました。学校の指示でこの研究所に行ったわけですが、軍と学校とはいろいろと関係があったのでしょう。当時は物資が無いので、花火に使うような火薬で兵器用の弾薬を作る研究を手伝いました。火薬の防湿についての研究もやりました」(木村靖/元日本カーリット常務/第一工学部火薬学科/昭和21年卒)
「昭和18年秋に半年早く一高を卒業させられ、東大の冶金学科に入りました。昭和20年の1月か2月、海軍の委託学生として、神奈川の航空技術廠に通い始め、月30円程度の手当てを受け取っていました。寮が金沢八景にありましたが、後に空襲で焼け、私の知人も死にました。
航空技術廠には製鋼所があり、航空機用の特殊鋼を作っていました。私はそこで、現場の工員に教えてもらいながら、石灰石を炉の中に放り込むなどの作業を工員たちと一緒にやっていたのです。石灰の質が悪く、製鋼は大変でした。終戦の知らせもここで聞きました。このとき作っていた鋼は、結局終戦までには間に合わず、使われることはありませんでした」(木寺淳/元商工省製鉄課長・元川崎製鉄常務/第一工学部冶金学科/昭和21年卒)
航空機のプロペラ設計に従事
「昭和20年の1月末までは大学で勉強をしていました。2月1日になり、陸軍の委託学生として市谷の航空本部に行くと、『ちゃんと勉強をしろ』と訓示を受けました。いま思うと、すでに上の人は、日本が負けることがわかっていたのだと思います。
訓示を受けた後、立川にあった陸軍の航空技術研究所に移りました。研究所といっても、座って研究をしていたのではありません。最初の2カ月は教練を受け、その後、プロペラの設計に携わりました。また、航空機の設計をやるうえでは操縦も知っておいた方がいいということで、飛行訓練を受けさせられました。千葉や伊丹などの飛行場を転々とし、ほとんど落ち着く間もありませんでした。
私が飛行訓練で留守の間に立川の研究所が空襲にあい、20年7月に山梨県甲府の近くの中巨摩の高等女学校に疎開しました。私は飛行訓練を終えて、その女学校でプロペラの研究や強度の計算などをしました。
8月1日に、教官の指示で、本郷の教室に資料をもらいに行きました。授業はやっていませんでしたし、先生も疎開したり、技術将校として陸海軍に出たりして、教室はからっぽでした。学校には事務職の人たちがいて、図書館から必要な書類を取ってもらいました。
本郷から中巨摩に戻る途中の8月3日か4日、八王子で空襲にあいました。列車が止まり、駅の南側のどぶ川に浸かって一晩を過ごしました。川は周囲の火災で熱くなっており、死ぬ思いでした。
立川の研究所にはいろいろな大学からの学生が計50人ぐらいいました。東大からは私ともう1人の同級生がいました。私の同級生は15人ほどですが、よほど体の悪い人を除いて、ほとんど全員が委託学生になっていたように思います。
玉音放送は、中巨摩の女学校近くの宿舎で聞きました。何を言っているか、全然聞こえませんでしたが、陸軍少佐から『戦争に負けた』と説明がありました。このころには私も、広島、長崎に原爆が落とされたことや、ソ連が侵攻していることなども知っていました。
大学には20年10月末に戻りましたが、まだ先生も学生もあまりいませんでした。12月に、学校に集まるよう大学から招集がかかりました。
私がいた応用数学科はもとは航空学科でした。それが、GHQの方針で応用数学科に名前が変更されたのです。復学したときは3年生で、教授からは、翌21年9月に卒業したいのなら、何でもいいから卒論を書けと言われました」(伊藤孝一/元南山大学経営学部教授/第一工学部応用数学科/昭和21年卒)