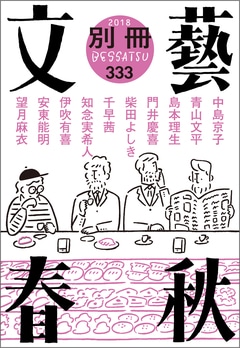全さんはときどき窓を開け、煙草を吸った。そのたび、ぬるくて甘い風が流れてきた。三木さんは自分からは声を発しないけれど、全さんの動きに気を配っているのが左肩のわずかな緊張でわかった。師弟という単語が自然に浮かんだ。全さんは仕事の場では厳しいのかもしれない。
「ここでいい」という全さんの声で車が停まった。ぬうっと手が伸びてきて「寝てただろ、降りるぞ」と頭を掴まれる。慌ててリュックを背負いなおす。
ドアを開ける全さんを三木さんが見つめていた。忠実な飼い犬のような横顔だった。「先生」とまっすぐな声をあげる。
「持ってる。心配するな」
「カメラは?」
「いらん」
三木さんのくっきりした黒い眉がかすかにゆがんだ。「わかりました」の途中で私は外にひっぱりだされ、全さんが車のドアを勢いよく閉めた。ライトバンはなにごともなかったかのように去っていく。全さんはふり返りもせず、青になったばかりの横断歩道を渡っていく。
慌てて追いかけ早足で横に並ぶと、「幸枝ちゃんの住所は?」と訊かれた。
「違います。あの人の、実家の、住所です」
全さんは「あの人」のところで目をすがめたが、手をだして「住所は」と繰り返した。
「山形です」
「それは知ってる」
横断歩道を渡ったところで立ち止まり、リュックからのろのろと年賀状を取りだす。私の年賀状の束に父が毎年そっと入れてくれるそれには、印刷された干支の絵と新年の言葉しかなく、差出人の意図をはかりかねた。もっとも意図など特になく、例年の習いで送っているだけに過ぎないのかもしれないが、その住所を見ては止まってしまう自分の手がわずらわしかった。
「鶴岡市の・・・・・・」
読みあげようとすると、素早く奪い取られた。駅へ向かう人たちの視線を感じる。
「庄内か」と顎先で頷き、「海側からと山側から、どっちがいい?」と私を見る。
「海」と反射的に答えてしまい、「え、ほんとうに行くんですか?」と全さんに詰め寄った。全さんは応じず、すっと体をそらすと、改札横のみどりの窓口に消えてしまった。
長く待った気がした。気になってずっと自動ドアを見つめていたが、中に入ることはできなかった。しばらく経って全さんが出てきた。私を見て、「あ」と口を半びらきにする。